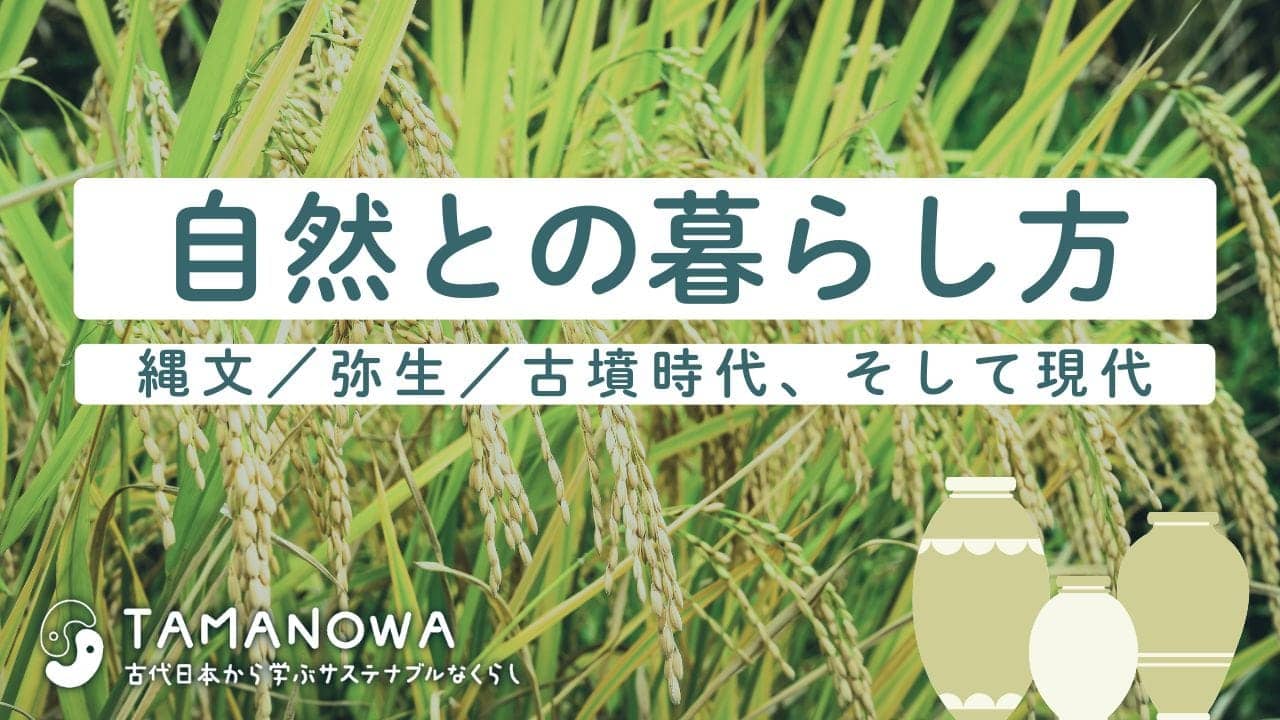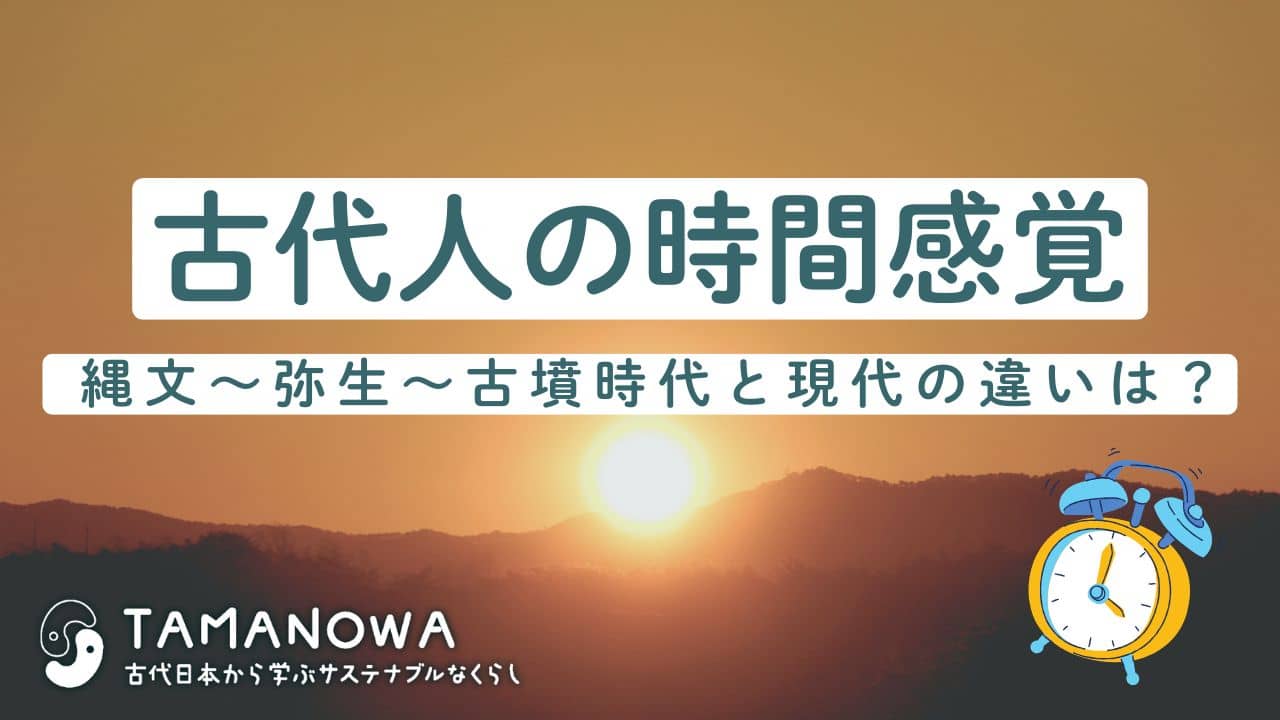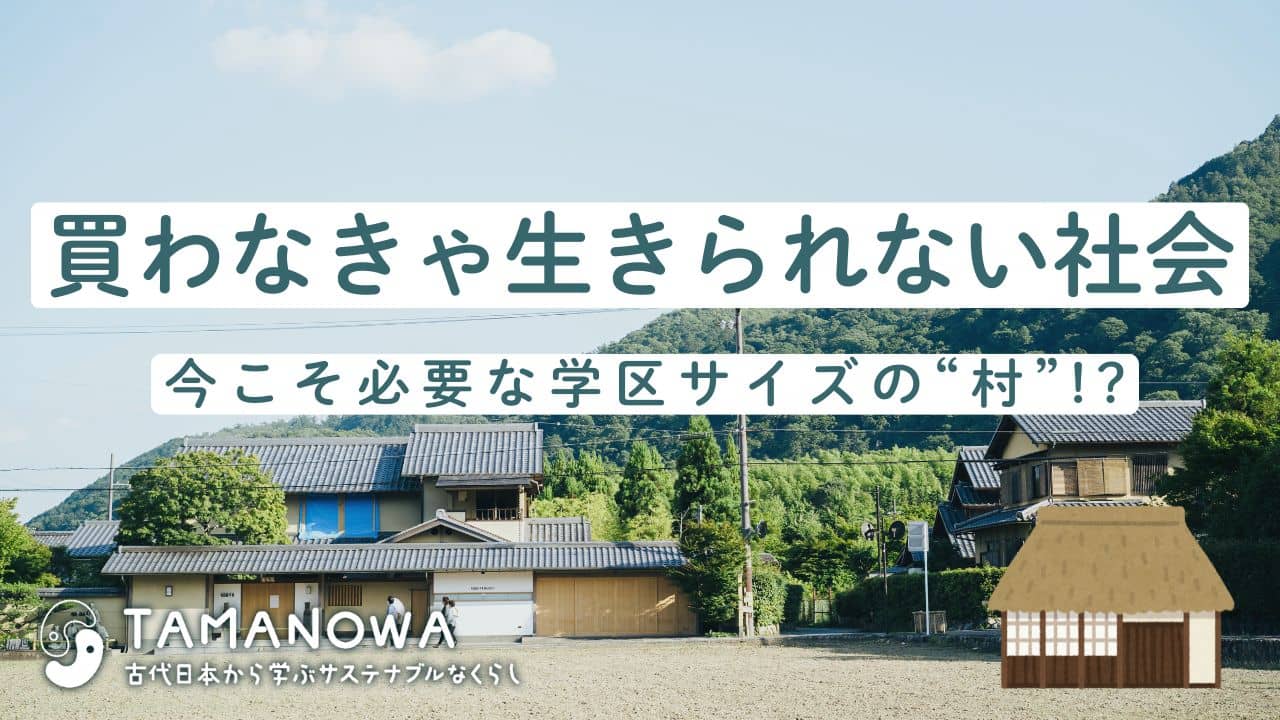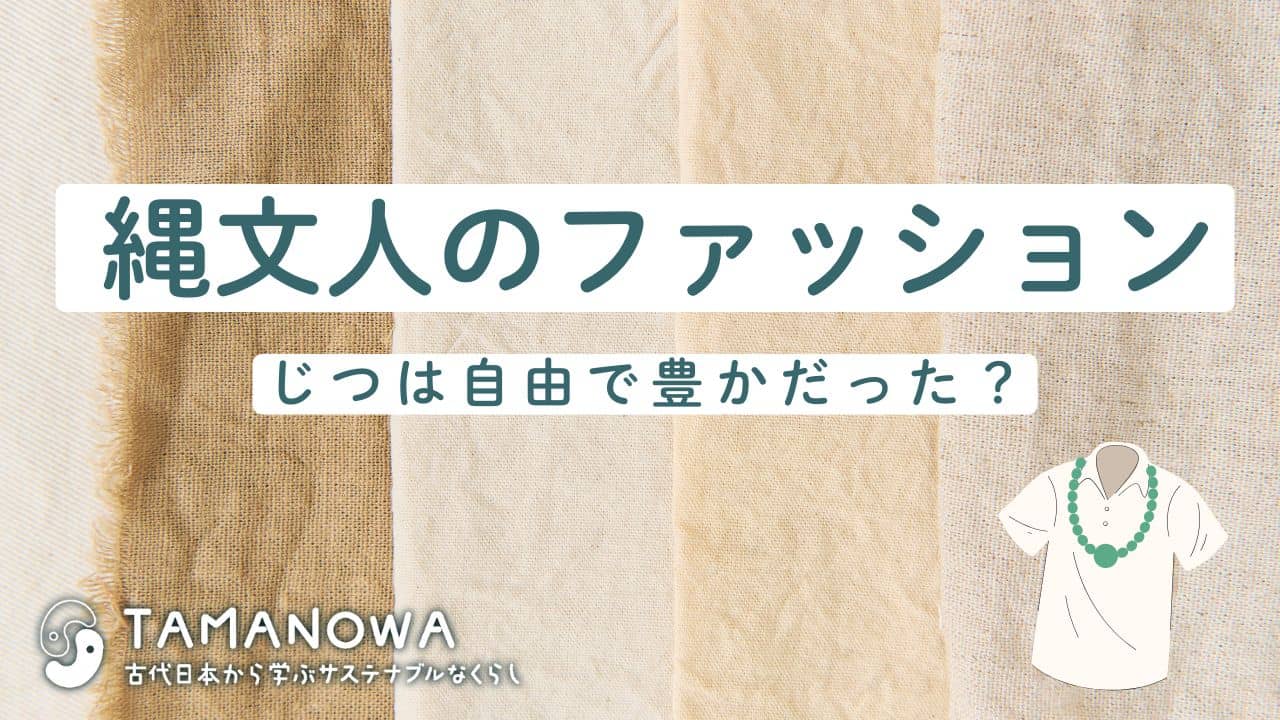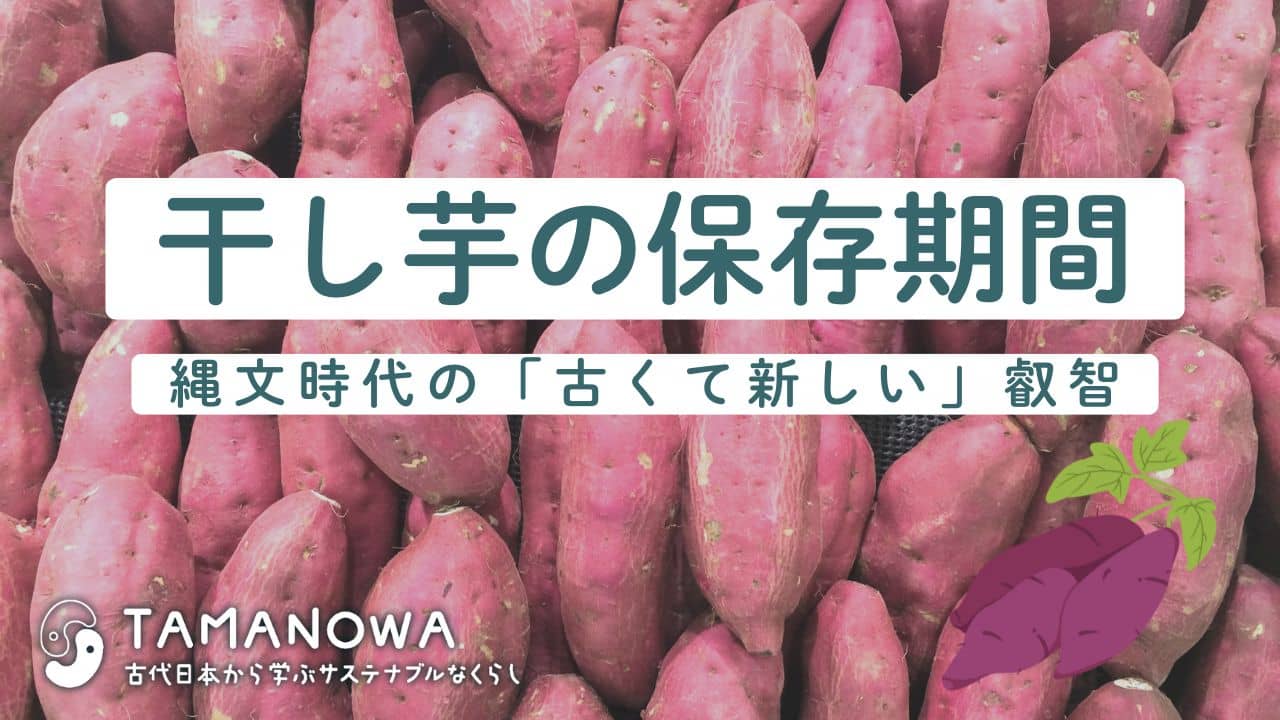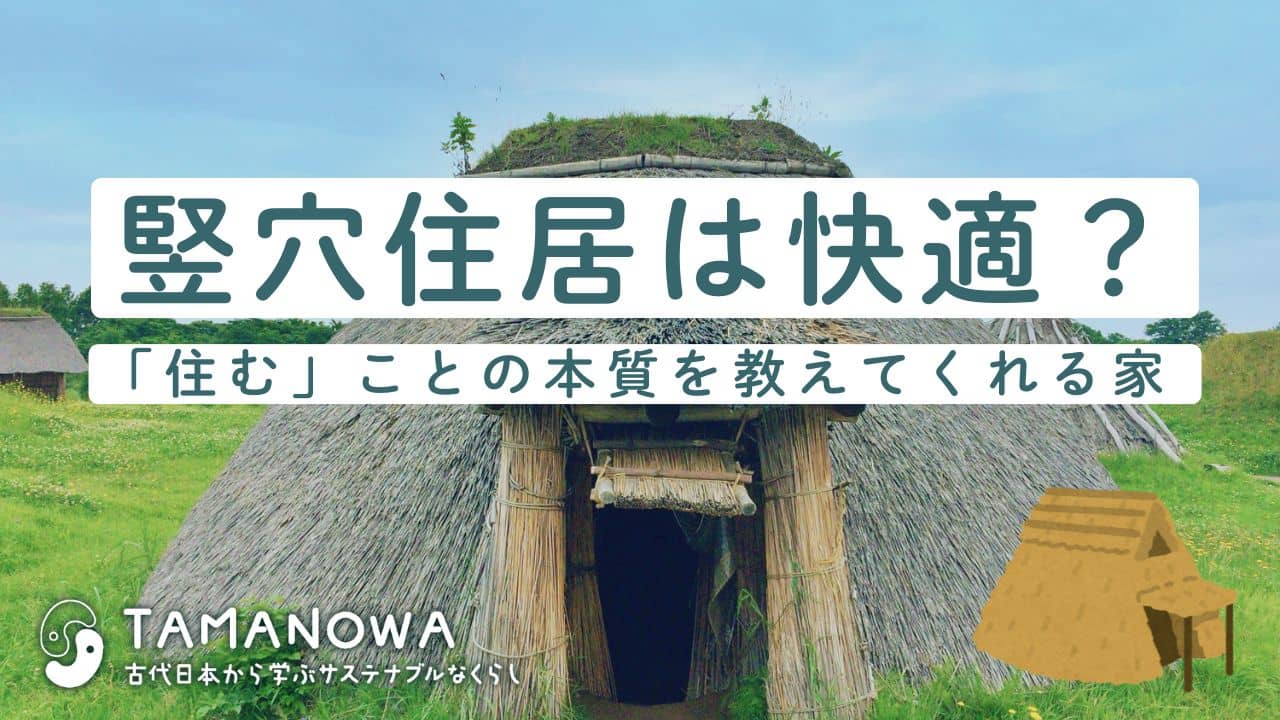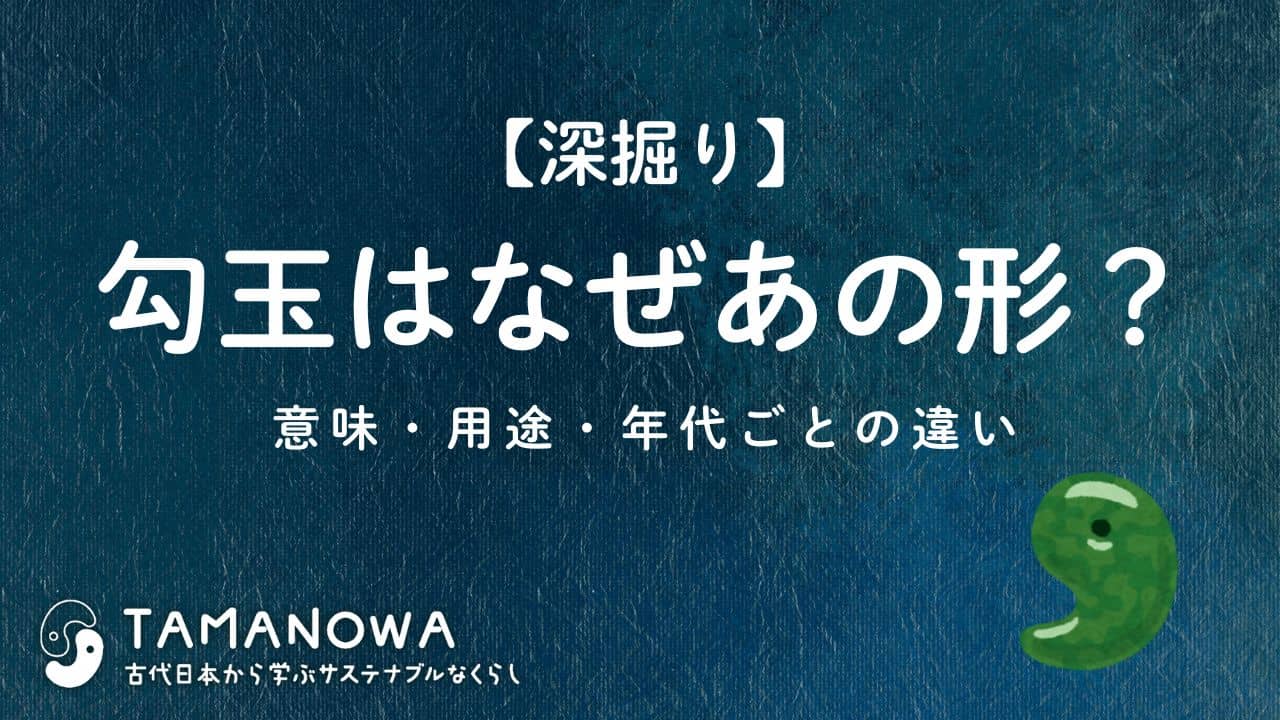「縄文」「弥生」「古墳」と聞いて、あなたはどんなイメージを思い浮かべるでしょうか?
もしかすると、縄文は土器と土偶、弥生は稲作、古墳は前方後円墳……そんなふうに、学校で習ったキーワードがまず思い浮かぶかもしれません。
今回の記事では、「それぞれの時代の人たちが、自然とどう関わっていたか」という点について、深掘りして解説していきます。
現代との「自然観」の違いに、びっくりするかもしれません!
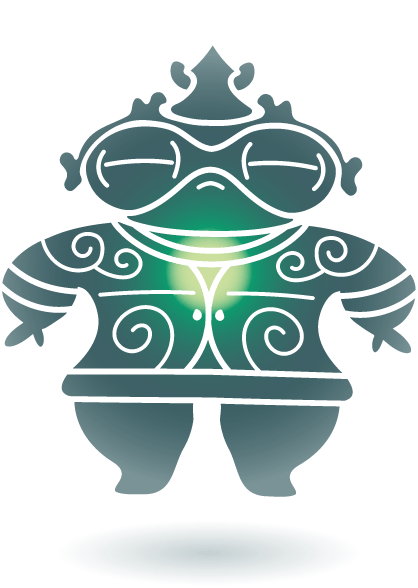
シャコー
縄文〜弥生〜古墳時代のおおまかな特徴
「縄文」「弥生」「古墳」。
これらは、当時の人びとの暮らし方やものの考え方の特徴に注目して、後の時代に名づけられた呼び名です。
つまり、昔の人たちが「いまは縄文時代だ」と思って暮らしていたわけではありません。
あとから土器の模様や道具の変化、集落の構造などをもとに、「このあたりは同じ特徴がある」と区切って名づけたのが、私たちが今使っている時代区分なのです。
では、その「特徴」とは、どのようなものだったのでしょうか?
後ほど深掘りしますが、ざっくり言うとこんな感じ。
まず、縄文時代。
これは今からおよそ1万6千年前、西暦でいうと紀元前14000年ごろに始まり、紀元前300年ごろまで続いたとされています。
狩りや漁、木の実や山菜の採集によって暮らし、自然と寄り添うような生活が営まれていました。
次に弥生時代。
これは紀元前300年ごろから紀元250年ごろまでの期間で、日本列島に稲作が広まり、人びとは田んぼをつくって米を育てはじめます。
自然から得るだけでなく、自然を育て、管理するという発想が強くなっていきました。
そして古墳時代。
およそ4世紀(西暦250年ごろ)から7世紀(西暦600年ごろ)まで続いたこの時代は、大きな権力をもつ人物が現れ、自然を象徴するような巨大な古墳が築かれました。
人びとは自然を思い通りに作り変える力を持ちはじめたと考えられます。
このように、三つの時代はそれぞれ「自然との付き合い方」がまったく異なっていたのです。
いま私たちが暮らしている現代も、自然との関係はあります。
ただしそれは、電気をスイッチでつけたり、水を蛇口から出したり、自然そのものを意識することなく過ごせる環境です。
現代は「自然」はどこか遠くて、実感のない存在になりつつあるのかもしれません。
この記事では、縄文・弥生・古墳という三つの時代の自然との関わり方を比べながら、現代のわたしたちにとっての自然との距離について、あらためて考えてみたいと思います。
まずは、最も古く、自然のそばで暮らしていた縄文時代から見ていきましょう。
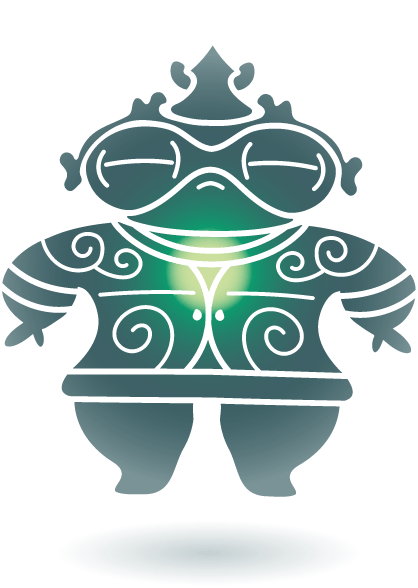
シャコー
それぞれの時代が、ちがう“自然とのつきあい方”をしていたなんて、おもしろいのデス!
縄文時代:自然と一体で暮らすということ
縄文時代は、今からおよそ1万6000年前から紀元前300年ごろまで続いた、とても長い時代です。
名前の由来は、土器に見られる「縄の文様」から。けれど、模様よりも注目したいのは、そこで営まれていた暮らし方です。
縄文人たちは、森や川、海といった自然の中で生きていました。主な食べものは、木の実や山菜、魚、貝、獣の肉など。
縄文人は、自然の恵みを必要な分だけ受け取りながら、それ以上は取りすぎないという姿勢で暮らしていたと考えられています。
当時の住まいは「竪穴住居(たてあなじゅうきょ)」と呼ばれるもので、地面を少し掘り、柱を立てて屋根をかけたシンプルな構造でした。
木や土、草など、身のまわりにある素材を上手に活かしながら、自然とともに過ごしていたのです。
また、道具や装飾品には、単なる実用性を超えた「美しさ」や「意味」が込められていました。
たとえば土偶(どぐう)や耳飾りなどには、祈りや自然への感謝といった気持ちがこめられていたと考えられています。
これはつまり、縄文人たちにとって自然は、ただの「資源」ではなく、「共に生きる存在」だったということです。
太陽や月、山や木、すべてのものに“いのち”があると信じ、感謝とともに接していた。そんな精神性が、暮らしのすみずみにまで行き渡っていたのではないでしょうか。
このような生活は、一見すると不便で大変そうに思えるかもしれません。
けれど、「足るを知る」暮らしには、現代ではなかなか感じられない種類の安心感や、自然とのつながりからくる深い充足感があったのではないかと想像されます。
このように、自然と一体になって暮らすというのが、縄文時代のもっとも大きな特徴です。次の弥生時代になると、この関係が少しずつ変わっていきます。
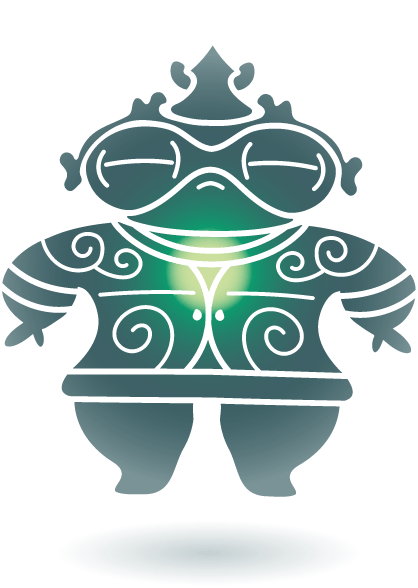
シャコー
なんだか、風の音まで聞こえてきそうな世界デス。
ゆっくり息を吸って、次に進む準備はいいデスか?
弥生時代:自然を管理し、育てるという発想
弥生時代は、今から約2300年前、紀元前300年ごろから始まり、3世紀ごろまで続いたとされます。
縄文時代と大きく異なるのは、人々の暮らしの中心に「稲作(いなさく)」が登場したことです。
稲作は、自然にあるものを“狩る”や“拾う”のではなく、自分たちで“育てて増やす”という考え方にもとづいています。これは、自然との関わり方の根本的な変化を意味していました。
水と土地のコントロール
水田で米をつくるには、田んぼを作り、水を引き、季節や気候を読みながら管理する必要があります。つまり、自然のままではなく、ある程度コントロールする必要が出てきたのです。
この過程で、人々は水路や畦(あぜ)を整え、共同で農作業をするようになり、集落ごとの役割分担やリーダーの登場といった社会の変化も生まれました。
自然と人のあいだに「距離」が生まれ始めたのも、この時代かもしれません。
暮らしの変化
食べ物を「貯める」ことも可能になり、人口も少しずつ増えていきました。道具も金属製のものが広まり、作業効率は飛躍的に向上しました。
また、貯蔵や所有といった概念が生まれたことで、「誰がどれだけ持っているか」という不均衡が見えるようになり、身分や格差のはじまりとも言われます。
このように、弥生時代の人々は自然に「働きかける」ことを通じて暮らしを発展させていきました。
それは自然を支配しようとするものではなく、「いかに自然のリズムに寄り添いながら成果を得るか」を模索した、いわば“共存型のマネジメント”だったとも言えるでしょう。
縄文とのちがいは
縄文人が「自然と一緒に生きていく」ことを第一にしていたのに対し、弥生の人々は「自然を少しずつ整えて、自分たちの暮らしに合わせていく」という方向に進んでいきました。
これは、現代の農業にもつながる発想です。人間が自然に働きかける力を持ち始めた、その原点が弥生時代なのです。
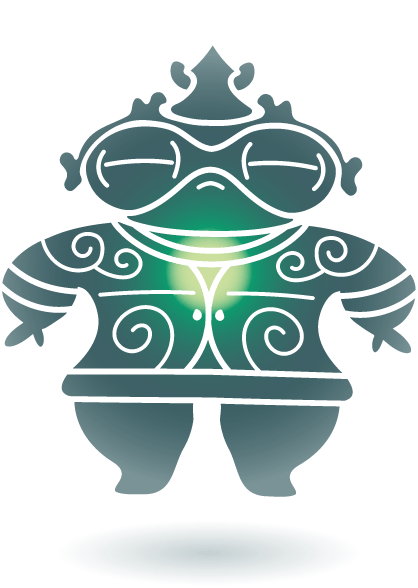
シャコー
ついに農具クワが登場デス。
畑づくりはたいへんだけど、ごはんはうれしいデスね〜。
お次は…もっとスゴい時代がやってくるデスよ!
古墳時代:自然を超える“かたち”をつくる時代
古墳時代は、今からおよそ1700年前、西暦250年ごろから600年ごろまでの時代です。その名のとおり、この時代を象徴するのは「古墳」、つまり大きな墳墓の存在です。
この時代、人々は自然の地形を活かしながらも、大規模な土木工事によって人工の“かたち”を作り出しました。
古墳時代は自然の中に人の力を誇示する巨大な構造物を築いたという点で、人類史上のひとつの転換点といえるでしょう。
巨大な構造物を自然の中に置く
全長200メートルを超える前方後円墳など、巨大な古墳は、周囲の自然環境の中でもひときわ目立つ存在でした。自然の中に人工的な造形を持ち込むことで、「人が自然を超える存在になりつつある」という象徴的な意味合いを持ち始めたのです。
実際、古墳の築造には風水や地形、方角といった自然の要素が取り入れられ、自然との調和を前提とした設計が行われていました。
権力の誕生と一極集中
古墳を作るためには、膨大な人手と資源が必要でした。つまり、それだけの力を持つ首長や王が存在していたことを意味します。
支配者が存在し、その権威を「かたち」として見せることが重要になってきたのです。
自然と共に生きるというより、「自然の中に自らの存在を刻む」という態度。これが古墳時代における自然との関わり方でした。
自然観の変化
縄文時代には「自然に属している」という感覚、弥生時代には「自然を管理する」という態度、そして古墳時代には「自然の中に自らの力を示す」という段階へと移り変わっていきました。
この変化の中には、自然との距離が少しずつ広がっていく感覚もあります。
人が自然を“舞台”とし始める、そんな時代だったのかもしれません。
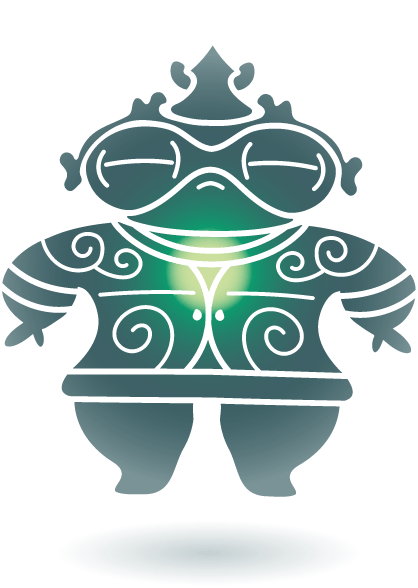
シャコー
自然と人の関係が、ずいぶん変わってきたデスね。
お墓まで巨大にしちゃうなんて、ちょっとロマン感じるデス〜。
そして現代:自然の“仕組み”に、まるごと依存する暮らしへ
現代のわたしたちは、一見すると自然とは無縁の生活を送っているように思えるかもしれません。
電気、水道、ガス、通信、物流……生きるために必要なあらゆるものが、目に見えない仕組みの中に組み込まれ、自動的に供給されています。
しかし、その「見えない仕組み」の根底には、膨大な自然の資源と、それを管理・運用するインフラの存在があります。そして私たちは、その仕組みの維持を当然の前提として生活しています。
自然と離れた感覚
縄文時代の人びとは、森の中で食料を採り、土器を焼き、自然と共に暮らしていました。弥生時代には稲作を通じて自然をコントロールし、古墳時代には人工のかたちで自然に印を刻みました。
では現代はどうでしょうか。
私たちは、自然の気まぐれに振り回されることなく、空調の効いた部屋で生活し、スーパーに並ぶ加工品を食べ、都市に張り巡らされたインフラに守られて生きています。自然は、どこか遠くの存在になってしまったのです。
しかし、地震・台風・集中豪雨などの自然災害に見舞われたとき、わたしたちはその「遠くに感じていた自然」が、実は暮らしの足元にあったことに気づかされます。
電気が止まり、水が止まり、ガソリンが供給されない――それだけで、普段の暮らしは一瞬で崩れてしまいます。
依存構造のリスク
現代の生活は、高度に発展した社会インフラに支えられています。便利さの裏側には、集中管理されたエネルギー供給、遠隔地からの食料輸送、上下水道のネットワークがあります。
この仕組みが止まったとき、わたしたちの暮らしはどれだけ持ちこたえられるでしょうか?
例えば、大規模な地震が起きたとき。
停電・断水・ガソリン供給停止・物流混乱……それが数日から数週間続くだけで、都市生活はすぐに機能不全に陥ります。
このような非常時に備えることはもちろん大切ですが、そもそも「自分の暮らしを、自分の手の届く範囲に取り戻していく」という視点は、これからますます重要になっていくのではないでしょうか。
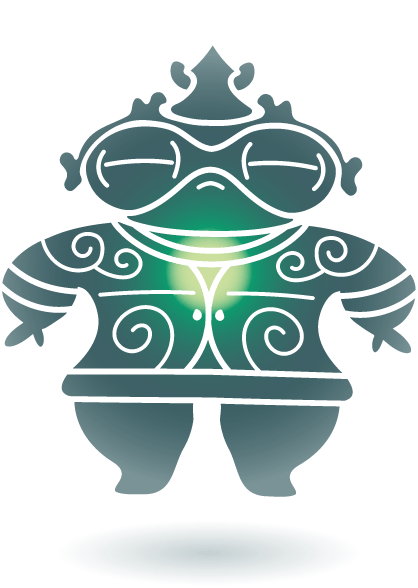
シャコー
電気も水も、気がつけば誰か任せになってるデス…。
でも知っておくだけで、暮らしがちょっとたくましくなる気がするデスよ!
おわりに:自然との距離を、もう一度考えてみる
縄文、弥生、古墳、そして現代。
人と自然との関わり方は、時代ごとに姿を変えてきました。自然に溶け込んで暮らした縄文、自然を利用して育て始めた弥生、自然を超える象徴を築いた古墳。
そして現代は、自然の仕組みを“外部化”し、見えなくしてしまった時代といえるかもしれません。
私たちは、自然を「遠ざけた」のではなく、「見えにくくした」だけなのかもしれません。その距離の曖昧さこそが、現代の不安定さの根っこにあるようにも感じられます。
では、どうすれば自然との距離を取り戻せるのでしょうか。
今からできる、静かな一歩
これは、大きな生活革命の話ではありません。
便利さを手放してすべてを自給自足にする必要もありません。むしろ、ほんの少しずつ、自分の暮らしの中で「関われる領域」を取り戻していくこと。
たとえば、次のようなことから始めてみるのはいかがでしょうか。
- 野菜を一種類、プランターで育ててみる
- 土器や道具の作り方を調べて、子どもと一緒にまねしてみる
- 雨水をバケツで受けて、庭やベランダに撒いてみる
- 散歩中に季節の草花を観察して、名前を覚えてみる
- 「これはどこから来たのか?」を買い物のたびに考えてみる
どれも、今すぐ始められることです。そしてそれは、目には見えなくても、「生きる」ということの感覚を、すこしずつ手のひらに取り戻していく行為なのだと思います。
自然とともにあった時代の記憶は、決して過去だけのものではありません。それは、今の暮らしにこそ、静かに呼び戻されるべき知恵や視点なのかもしれません。
たまのわでは、そうした視点に立ちながら、古代の知恵と現代の暮らしを結ぶヒントを、これからも静かに発信していきます。
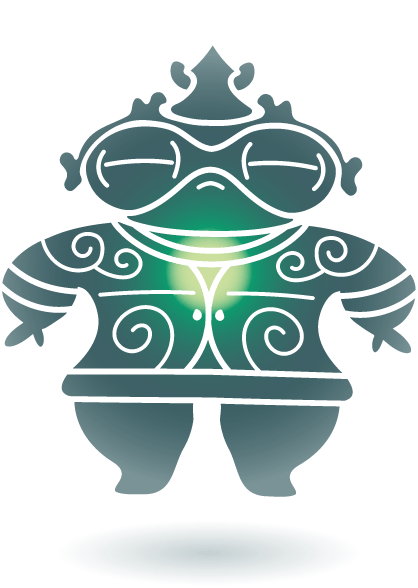
シャコー
遠い昔のことみたいだけど、じつは今にもつながっている話デスよね〜。
ちょっとずつでも、自分の暮らしのなかで思い出していけたらステキデス!