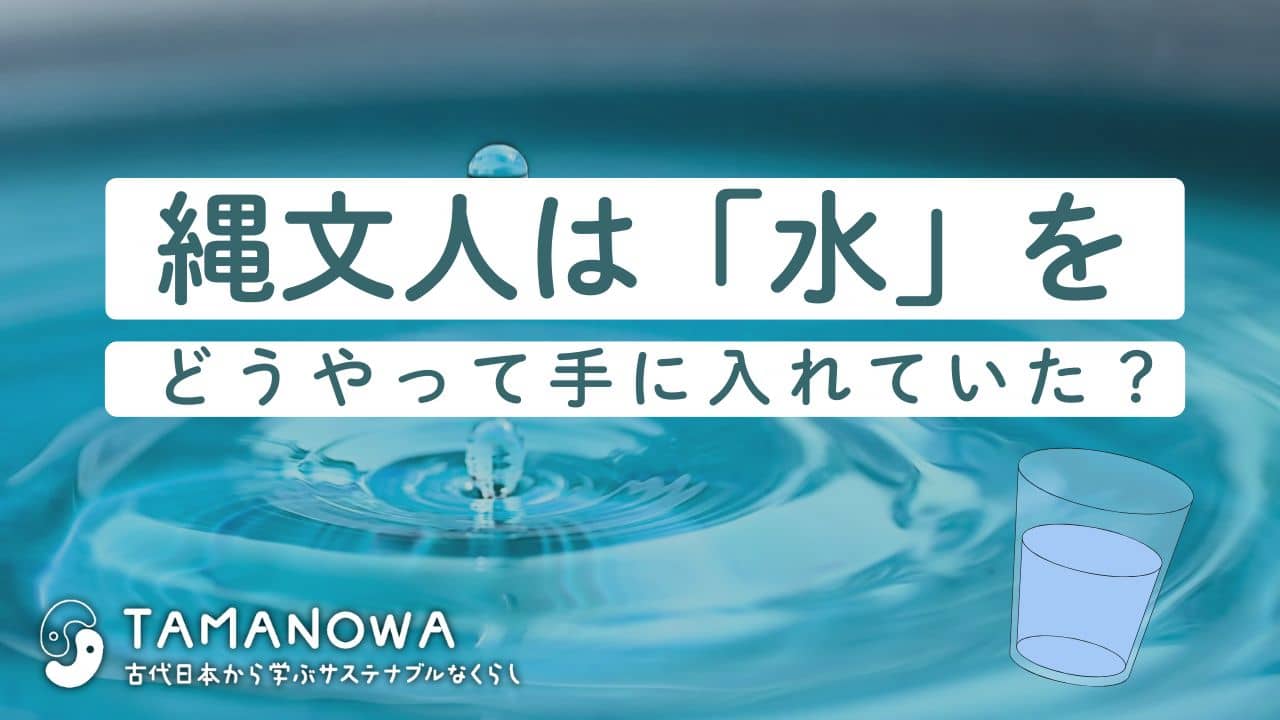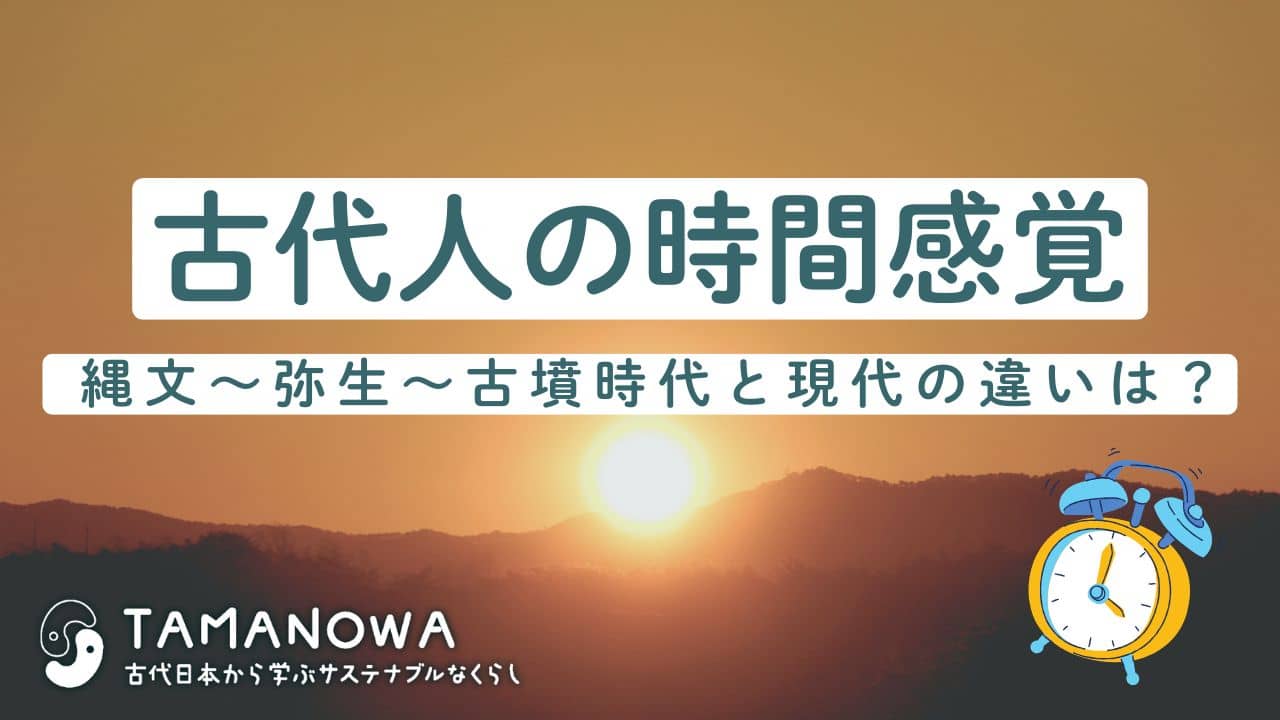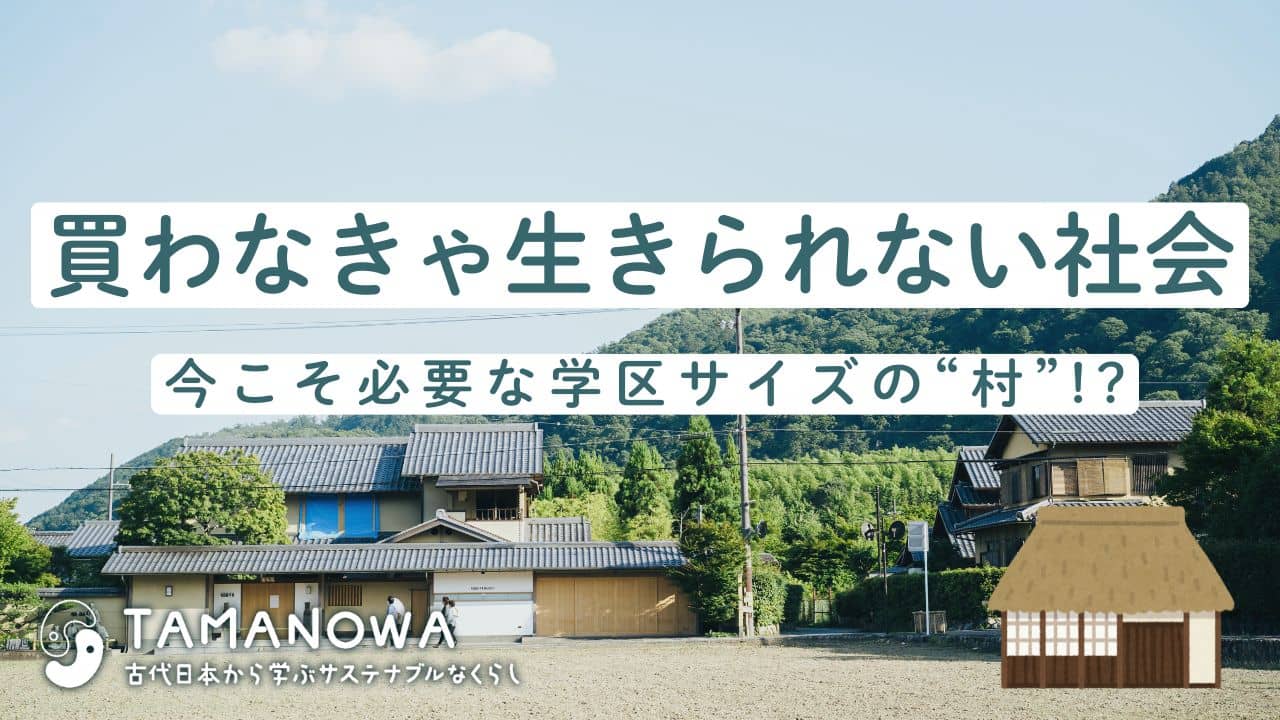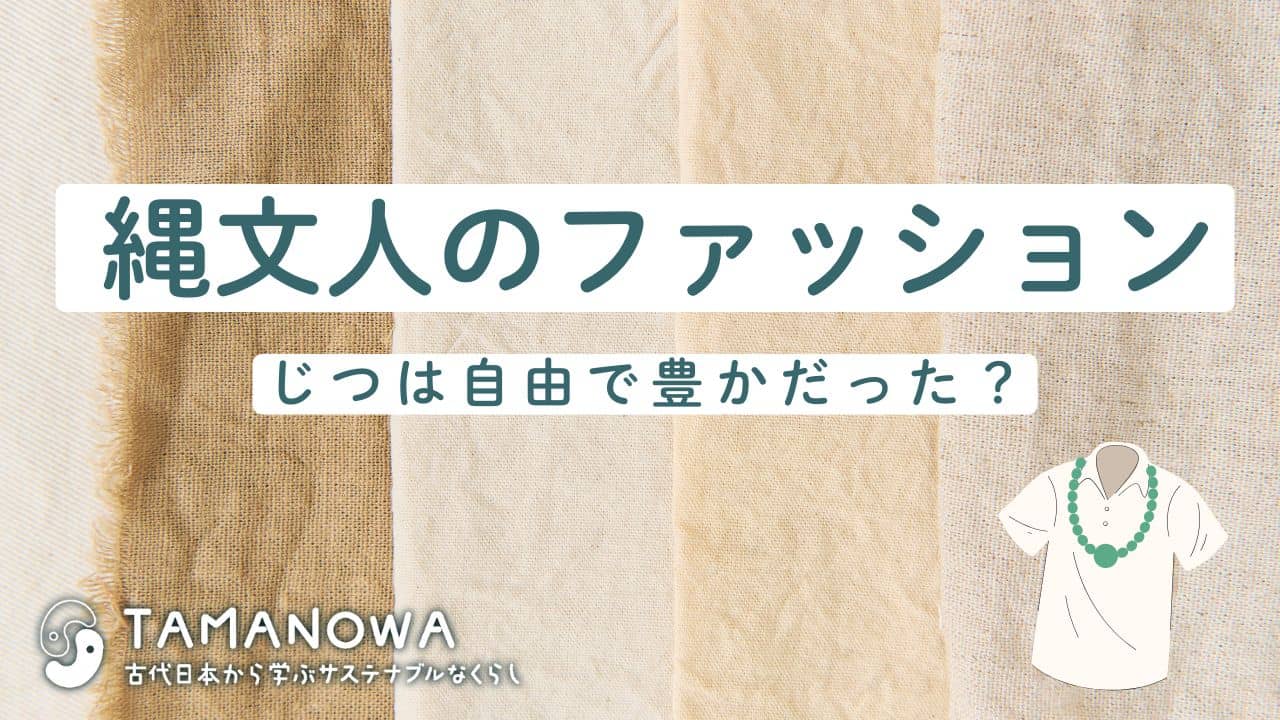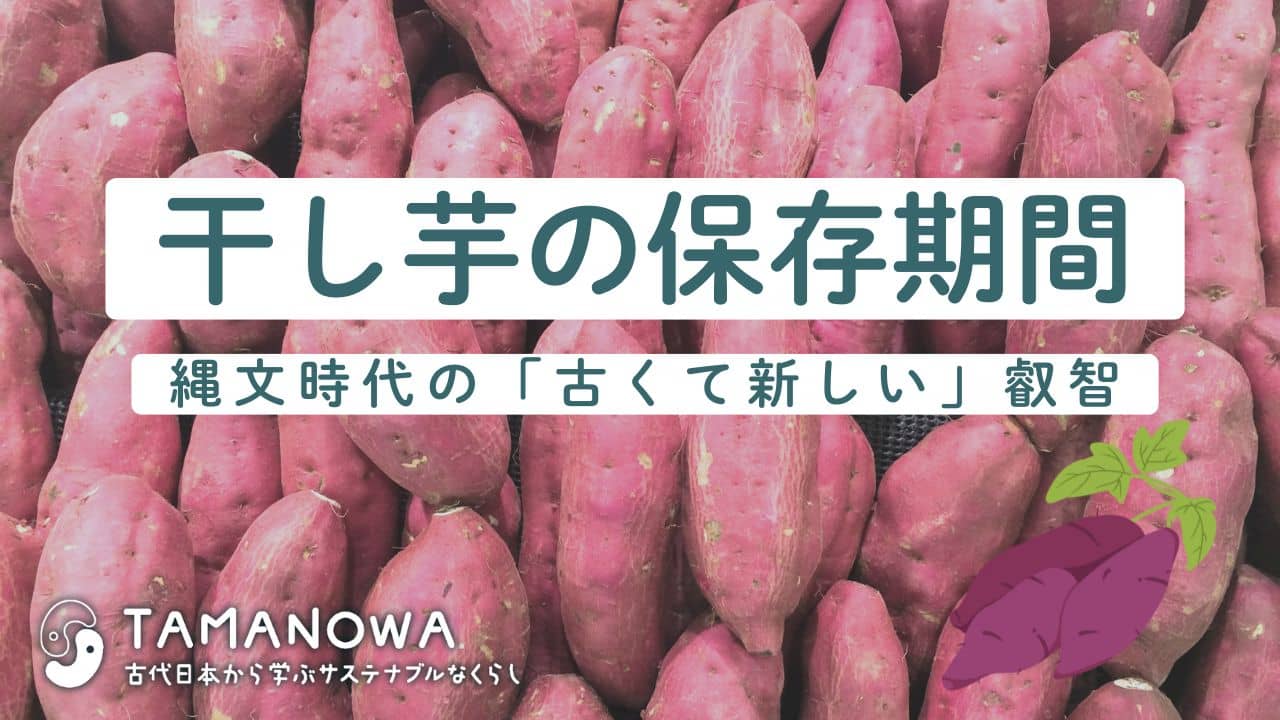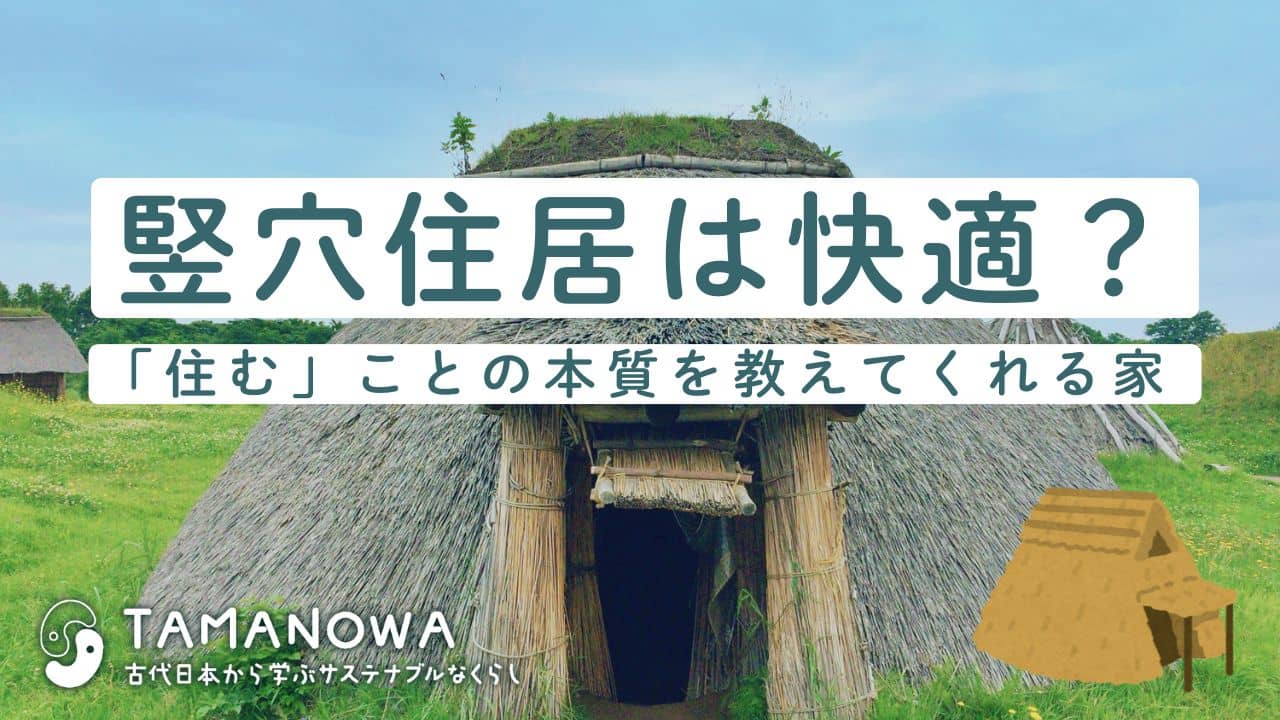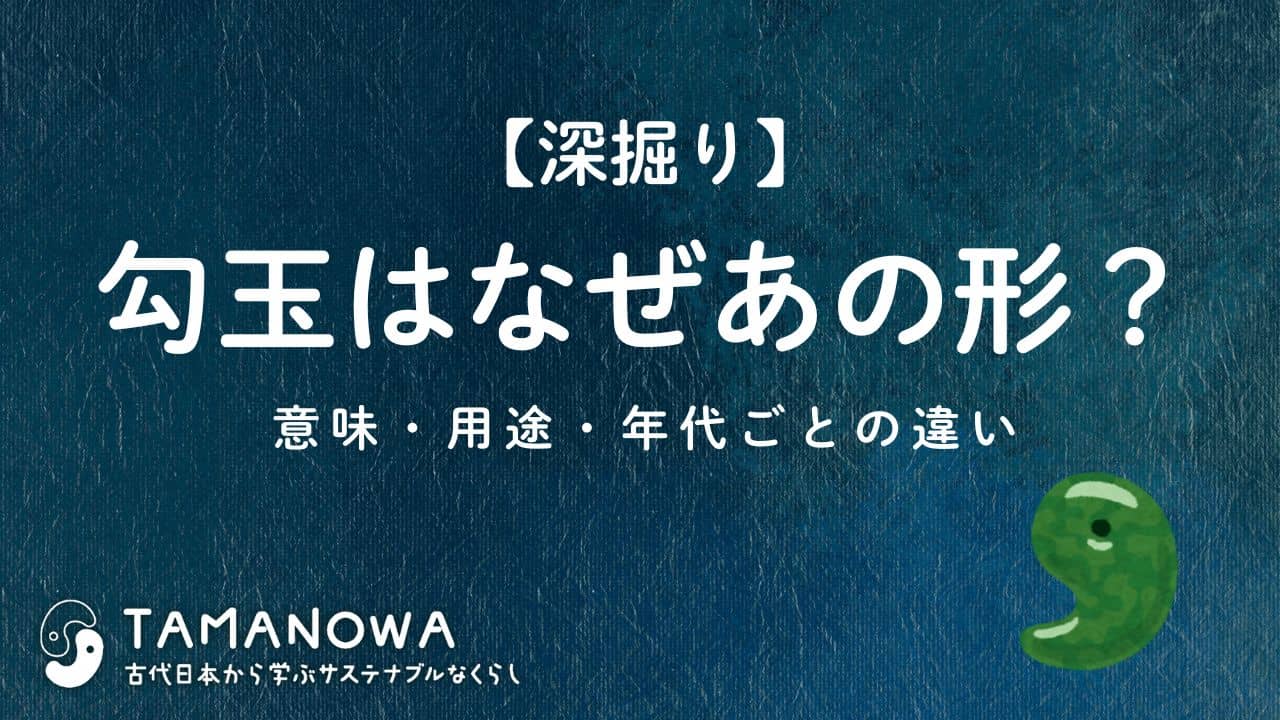今の暮らしでは、水は「あるのが当たり前」です。
朝起きて顔を洗い、食器を洗い、お風呂に入る。
蛇口をひねれば、きれいな水がいくらでも出てきます。
でも、それって本当はとてもすごいことなんです。
もし、水道が止まったらどうなるでしょう?
たとえ1日でも、水が使えなくなったら、とても不便で困ってしまいます。
このコラムでは、昔の人びと――とくに縄文時代の人たちが、
どのようにして水を得ていたのかを見ていきます。
そして、それをヒントにして、
現代の暮らしの中で、水と少しだけ近づく方法を探してみましょう。

ミミー
縄文人はどのように「水のある場所」に暮らしていたのか
なぜ、水の近くに住んだのか?
今のように水道がない時代、水は生活に欠かせないものでした。
飲み水、食べ物を洗う、火を使う、道具を作る──すべてに水が必要です。
だから縄文人たちは、水を手に入れやすい場所に住むことを大切にしていました。
でも、ただ川のそばに住めばいいというわけではありませんでした。
湧き水や湿地を選んだ理由
縄文時代の住居跡(じゅうきょあと)は、全国にたくさん見つかっています。
その多くは「湧き水(わきみず)」や「湿地(しっち)」の近くにありました。
湧き水とは、地面の中から自然にしみ出してくる水のこと。
雨水が地下を通ってろ過され、きれいな状態で出てきます。
飲むのに適していて、しかも年中ほぼ同じ場所からわいてくるので、信頼できる水源です。
湿地も、水をたくわえる自然の場所。
田んぼのように水を含んだ土地で、植物や魚などの食べ物にも恵まれていました。
なぜ川のすぐ近くではなかったの?
「じゃあ、大きな川のそばに住めばよかったのでは?」と思うかもしれません。
でも実は、大きな川のすぐ横にはあまり住んでいませんでした。
その理由の一つは、「洪水(こうずい)」です。
大雨がふると、川があふれて流されてしまうことがあります。
道具や食べ物、住まいが流される危険がある場所は避けていたと考えられます。
つまり縄文人は、水が近くにあっても、危なくない場所をうまく選んで暮らしていたのです。
地形をよく見ていた縄文人
縄文人たちは、自然の様子をよく観察していました。
どこに水がたまりやすいか、どのあたりが湿っているか、
どんな植物が育っているか──そうした小さなサインを手がかりに、
「ここなら水に困らず、安全に暮らせそうだ」という場所を見つけていたのです。
これは、現代でも役立つ力です。
どんな地形が水をたくわえやすいかを知ることは、
災害への備えや、水にやさしい暮らし方を考えるヒントにもなります。

ミミー
湧き水のそばに住むなんて、縄文人ってかしこかったんダワ…
自然をよく見て、生きる場所を選んでたの。
次の章では、そんな縄文人たちが持っていた「水を手に入れるための知恵」について、もう少しくわしく見ていきます。
縄文人の水の知恵:自然を読む力
水をきれいにしてくれる場所を見つける
縄文時代には、ろ過装置も水道設備もありませんでした。
それでも、飲み水を手に入れ、暮らしに使っていたのです。
そのために大切だったのが、「自然が水をきれいにしてくれる場所」を見分ける力です。
たとえば湧き水。
これは雨や雪が山にしみこみ、地下をゆっくりと流れるうちに、
砂や土の層で自然にろ過されて地上に出てきたものです。
見た目は小さな水たまりや岩のすき間からの水ですが、昔の人にとってはとても大事な水源でした。
こうした場所を見つけられるかどうかが、命に関わる時代だったのです。
地形のサインを読む
どこに水がたまりやすいか、縄文人たちは地形をよく見て判断していました。
たとえば、土地のくぼみや谷のようになっている場所。
また、岩や土の様子を見て、水が流れているかどうかを見きわめる。
苔が多く育っている場所や、地面がしっとりしているところも、
水が近くにあるサインとして読み取っていたと考えられます。
水が集まり、流れやすい地形を知ることで、
どこに住むか、どこで水をくみに行くかを決める判断材料にしていたのでしょう。
雨水をためる工夫も
湧き水が近くになかったときには、雨を集めて使うこともありました。
家の周りに水をためるくぼ地を作ったり、葉っぱの上を流れる水を集めたり、
石のくぼみにたまった水をすくったりと、工夫はさまざまです。
このように自然にあるものを利用して、雨の恵みをうまく使っていたのです。
水を持ち運ぶための道具
集めた水は、その場ですぐに飲むだけではなく、持ち帰って使うこともありました。
そのときに使われたのが、縄文土器です。
縄文土器は水を入れて運ぶのに便利な形をしており、深さがあるものや口がすぼまったものなど、
さまざまな形が見つかっています。
土器の重さや持ちやすさ、こぼれにくさを考えて作られていたとすれば、
かなり実用的な道具だったことがわかります。

ミミー
雨水をためたり、地面のくぼみを見つけたり。
縄文人は、自然とおしゃべりしてるみたいだったんダワ…
縄文人は、自然のしくみをじっくり観察し、水と上手につき合って生きていました。
次の章では、それを現代に生きる私たちがどう応用できるか、現実的な視点で考えてみましょう。
とはいえ…湧き水はそう簡単に見つからない
湧き水は、どこにでもあるわけではない
縄文人が暮らしていた時代には、自然の中にたくさんの水の恵みがありました。
山や森が広がり、手を加えられていない土地が多く、
そこには湧き水や湿地、小さな沢が身近にあったのです。
でも今は、どうでしょうか。
山の中や田舎には、今でも湧き水が残っているところがあります。
しかし、そうした場所は減ってきていますし、
たいていは私有地や保護された地域の中にあって、自由に使えるとは限りません。
地図で見つけることはできても、実際に足を運んで使うのは難しいのが現実です。
「縄文のように暮らそう」は、ちょっと非現実的
水を自然から手に入れて暮らす。
そんな暮らしは理想的に思えるかもしれません。
けれど、現代の都市や住宅地で、完全にそれを実現するのはとても難しいことです。
水をためる場所を作るには広い土地が必要ですし、
それを管理し、安全に保つための知識や時間も求められます。
だからといって、諦める必要はありません。
「全部を昔のように戻す」ことが目的ではなく、
昔の知恵を今の暮らしの中に少し取り入れることで、
暮らしが変わるかもしれないのです。
考え方だけなら、今すぐにでも持てる
湧き水そのものを見つけられなくても、
自然の中で水がどのように流れているか、どこにたまりやすいか、
そうした視点を持って暮らすことは、今でも十分にできます。
それはただの知識ではなく、
災害のときにどこが安全かを判断する力にもなりますし、
水とどうつき合っていくかを考えるきっかけにもなります。
次の章では、そういった「身の回りの水の気配に気づくこと」について、
さらに具体的に見ていきます。

ミミー
たしかに今の町では、湧き水なんてなかなか見ないんダワ…
どうしたらいいの?
今できること①:身の回りの水の流れに目を向けてみる
水が「見える」のは雨の日だけじゃない
私たちはふだん、水を「出す」ことに慣れています。
キッチンやお風呂、ホースや洗濯機。
どれも人の手でつくられた仕組みの中で動いている水です。
でも、自然の中にある水は、人が動かさなくても流れています。
それに気づくには、ほんの少し視点を変えるだけでいいのです。
公園や神社で「水のある場所」を探してみる
散歩の途中で、公園や神社に立ち寄ることがあるかもしれません。
そういう場所には、小さな池や井戸、水が湧いている場所が残っていることがあります。
近所の中に、水が見える場所はどれくらいあるでしょうか。
看板のすみに「飲用不可」と書かれた水場でも、
そこに水があるというだけで、少し世界の見え方が変わります。
雨の日にしか見えない流れ
雨が降った日は、自然の水の流れが見えるチャンスです。
道路のふちを流れる水が、どこへ向かっているか。
マンホールや排水口に吸い込まれていく様子。
地面のくぼみにできる水たまり。
ふだんは気にもしない場所が、雨によって水の通り道になります。
子どもと一緒に傘をさして歩きながら、
「この水、どこから来たんだろう」「どこへ行くんだろう」と考えてみるのも、
ちょっとした自然観察です。
水がある場所のサインを読み取る
晴れた日でも、水の気配を感じられることがあります。
たとえば、苔がたくさん生えているところ。
いつも地面がしっとりしている場所。
そのあたりは、地中に水が流れている可能性があります。
また、植物の育ち方にもヒントがあります。
湿った場所を好む草が群れて生えていたり、
同じ場所だけ土の色が濃くなっていたり。
そうした小さなサインは、
縄文人が住む場所を選ぶときにも大切にしていた視点です。

ミミー
雨の後に道を流れる水を見るのって、なんだか楽しいんダワ…
わたしも今度、苔の生えてるところ探してみようかしら。
ほんの少しの観察でも、
「水ってどこにでもあるわけじゃないんだな」
「自然の中にも、水の通り道があるんだな」
という気づきが生まれます。
次の章では、そうした気づきをもとに、
水を「使う」ことについて、少し視点を変えてみましょう。
今できること②:水を使いすぎない工夫をしてみる
水を「もらう」だけでなく、「使い方」を見直す
自然から水を手に入れるのがむずかしいなら、
今ある水を、なるべく大事に使うという考え方もあります。
それは、節水というより「水のめぐりに気を配る」ということ。
どれだけの水を使っているか。
その水はどう流れて、どう消えていくのか。
そういう視点を持つだけでも、水との関係が変わってきます。
雨水をためてみる
雨が降るたびに、たくさんの水が屋根や道路に落ちています。
この水をためて、植物の水やりや掃除に使うことができます。
最近では、家庭用の雨水タンクも売られていて、
ベランダや庭に設置するだけで、簡単に水をためることができます。
もちろん飲み水には向いていませんが、
自然からもらった水を、自然のまま別の用途に使うという体験は、
小さな自給の入り口になるかもしれません。
水をきれいにする仕組みを暮らしに取り入れる
水を使いすぎないためには、使った水をすぐに捨てないという方法もあります。
たとえば、台所やお風呂の排水を、植物の力でろ過して再利用するシステム。
家庭菜園をしている人の中には、
排水を砂利や土でろ過して、畑にまわしている人もいます。
本格的な装置がなくても、
「土や植物が水をきれいにする」という考え方を知っておくことで、
水に対する見方が変わっていくでしょう。
念のための備えも大事にする
自然とつながる暮らしを目指すのはすてきなことですが、
いざというときに備えることも忘れてはいけません。
たとえば、非常時のために飲み水を備蓄しておいたり、
市販の濾過ボトルや携帯フィルターを持っておいたりすること。
短期間のサバイバルであれば、こうした道具がとても役に立ちます。
濾過装置は登山用品店などでも手に入ります。
小さくて持ち運びやすく、川や池の水を飲めるレベルまできれいにできるものもあります。
自然に頼ることと、技術をうまく使うこと。
その両方をバランスよく考えることが、現代らしい生き方かもしれません。

ミミー
雨水をためたり、植物が水をきれいにしてくれるなんて、すごいのね。
おわりに──自然と少しだけつながる暮らしへ
すべてを自分でやらなくてもいい
昔の人びとは、自然の中で生きていました。
水も、食べものも、すべてを自分たちの手で手に入れていました。
それはとても大変なことであり、だからこそ多くの知恵が育まれてきました。
でも、今の私たちがそれをすべて再現しようとする必要はありません。
水をすべて自然からくみ上げる暮らしは、現代ではむずかしいものです。
それでも、「少しだけ自然に近づいてみる」という考え方なら、誰でも始められます。
気づくだけで、暮らしが変わることもある
たとえば、雨の音に耳をすませること。
湧き水を見つけたときに「ありがたい」と感じること。
どこに水が集まりやすいかを、地面や植物から読み取ってみること。
そんなささやかな行動の中に、
自然とのつながりを取り戻すヒントがあるのではないでしょうか。
水は、ただの生活道具ではありません。
生きるために欠かせないものであり、
ときに人と自然との距離を教えてくれるものでもあります。
自然とともに生きる力を、もう一度
このコラムで紹介した内容は、特別な技術や道具を使うものではありません。
むしろ、「知ること」「気づくこと」が中心でした。
それだけでも、十分に価値があります。
自然に目を向け、必要以上に奪わず、
自分の暮らしの中で水との距離を考えてみる。
それは、自然とともに生きる力をもう一度、自分の中に取り戻すことにもつながります。
TAMANOWAとして伝えたいこと
私たちが目指しているのは、「全部自分でやろう」とすることではありません。
でも、今よりほんの少しだけでも、自然のリズムに近づいてみること。
その一歩が、安心や知恵につながる暮らし方になると信じています。
水に耳をすませること。
それは、未来に向けて暮らしを見つめなおす第一歩かもしれません。

ミミー
むずかしく考えなくてもいいのね。
ちょっと水の音に耳をすませるだけで、自然と仲よくなれる気がしてくるのダワ…