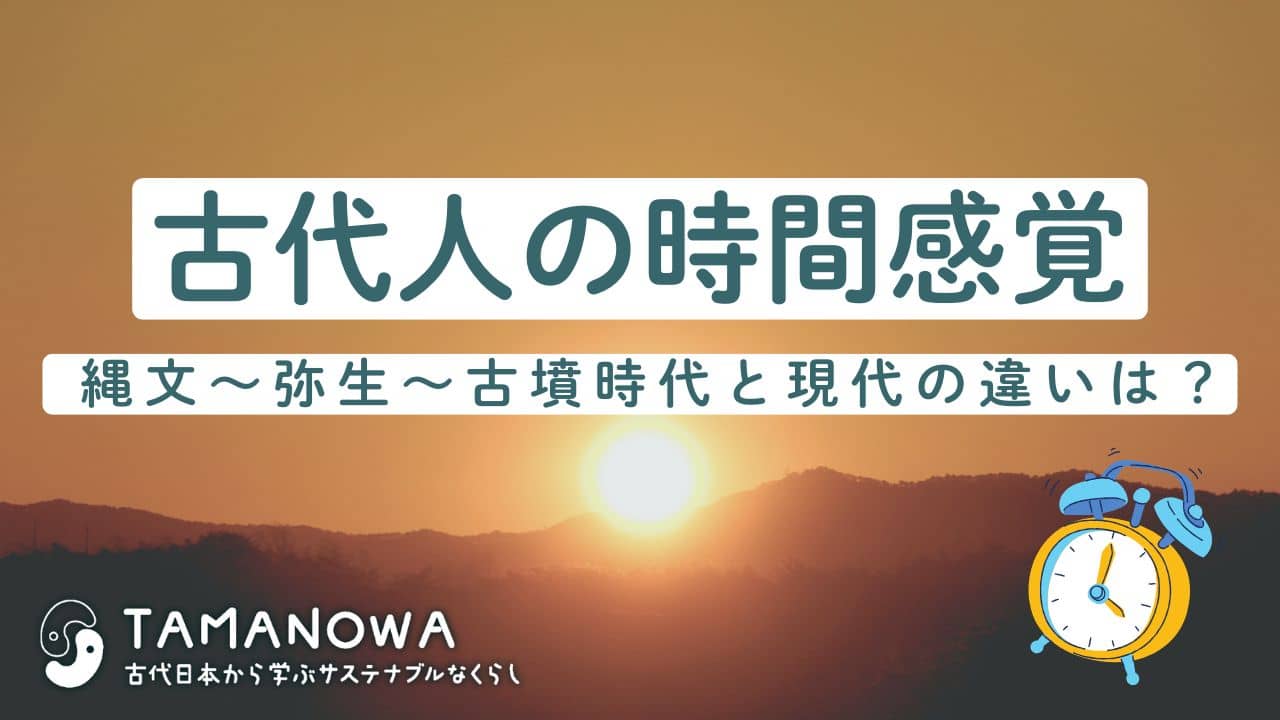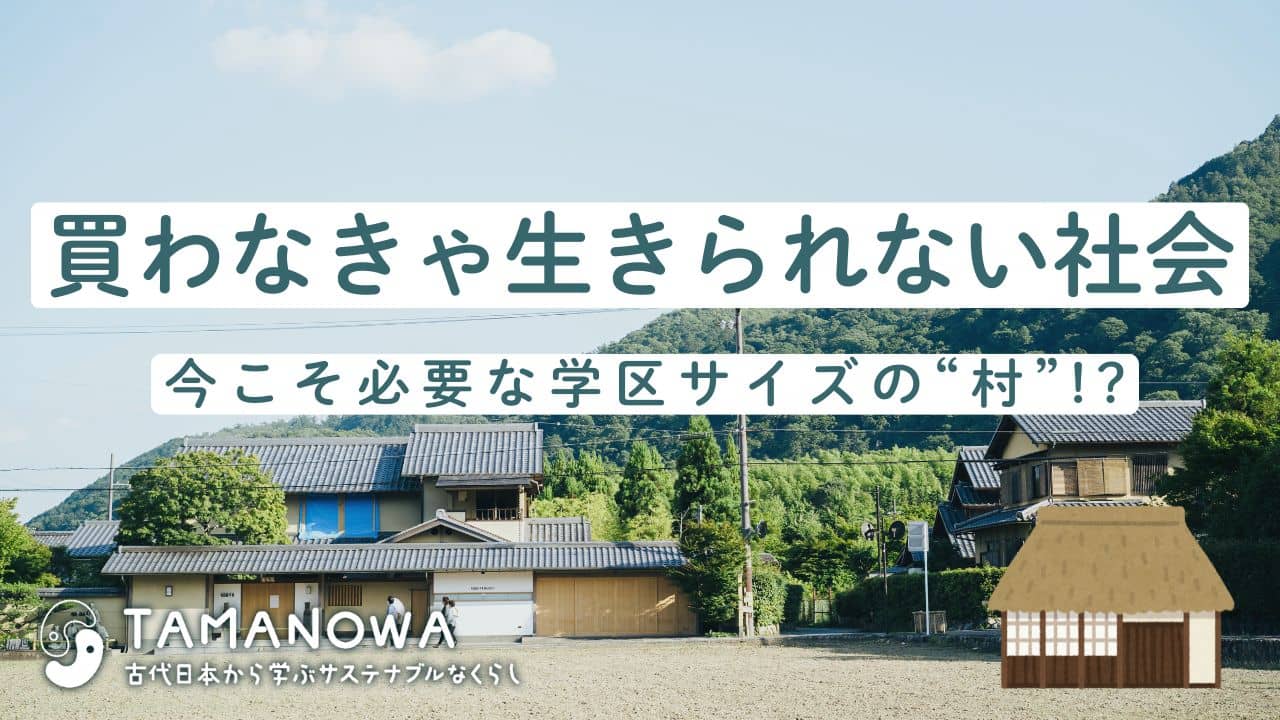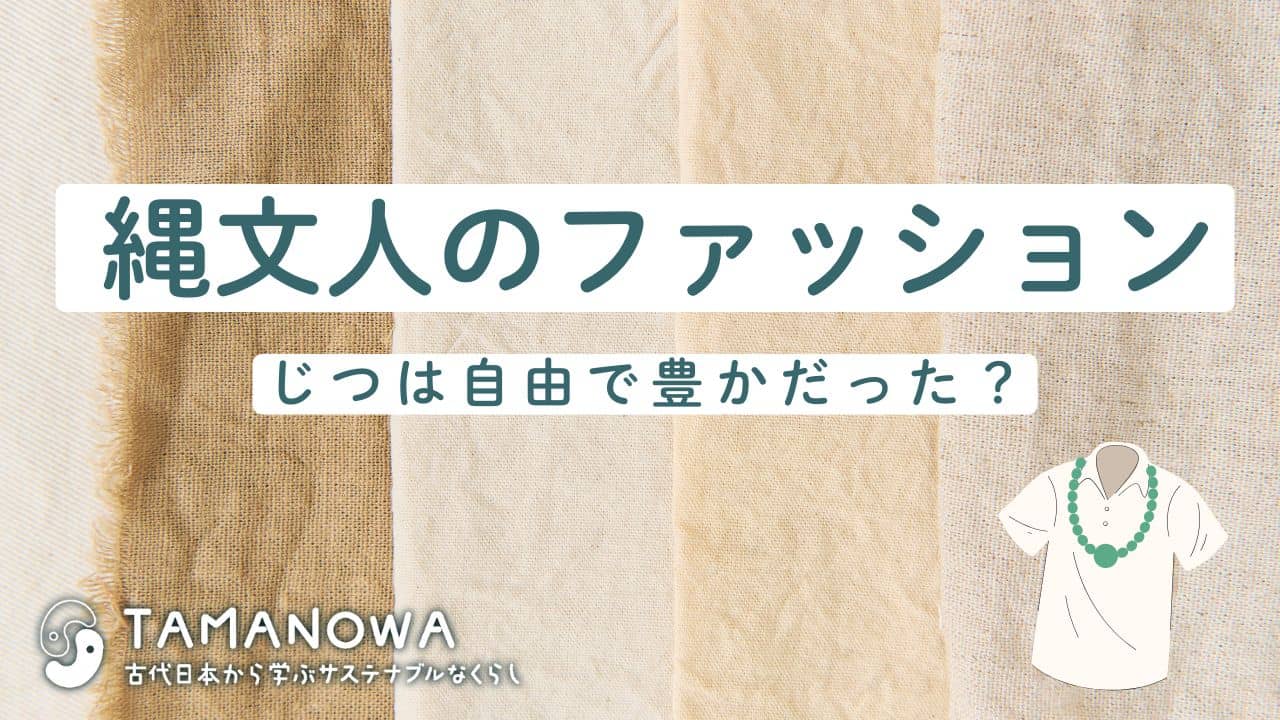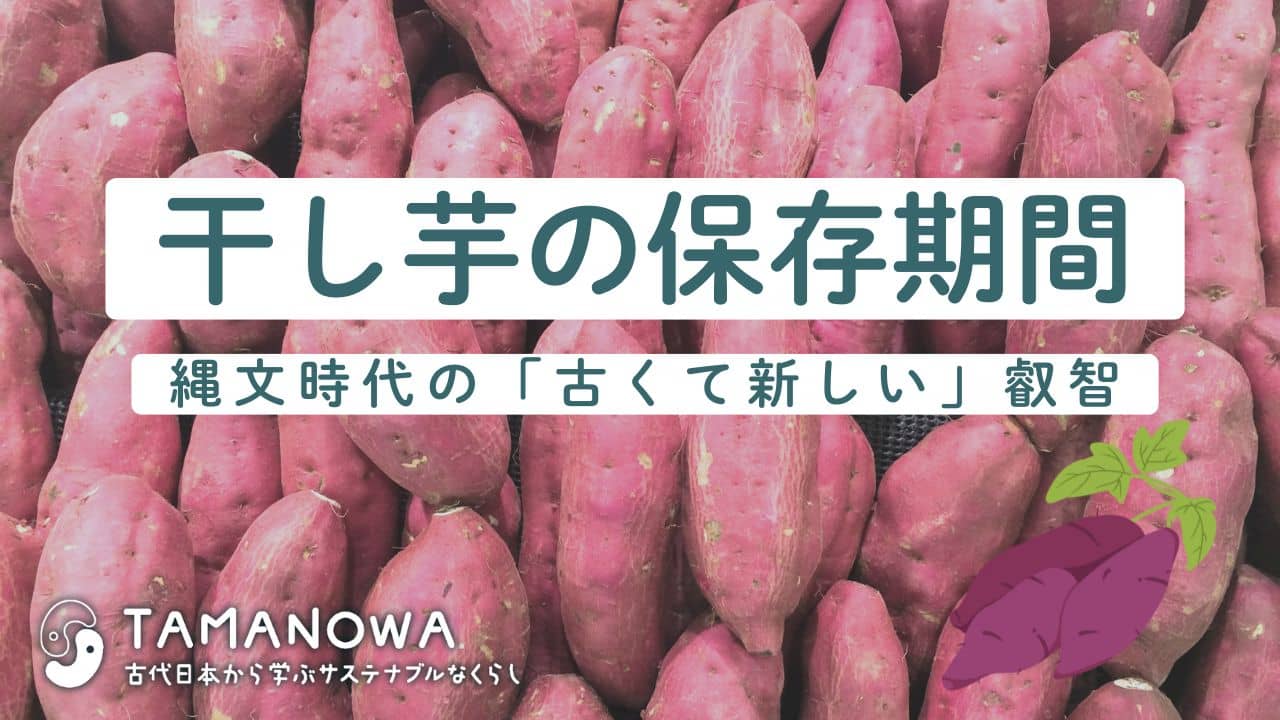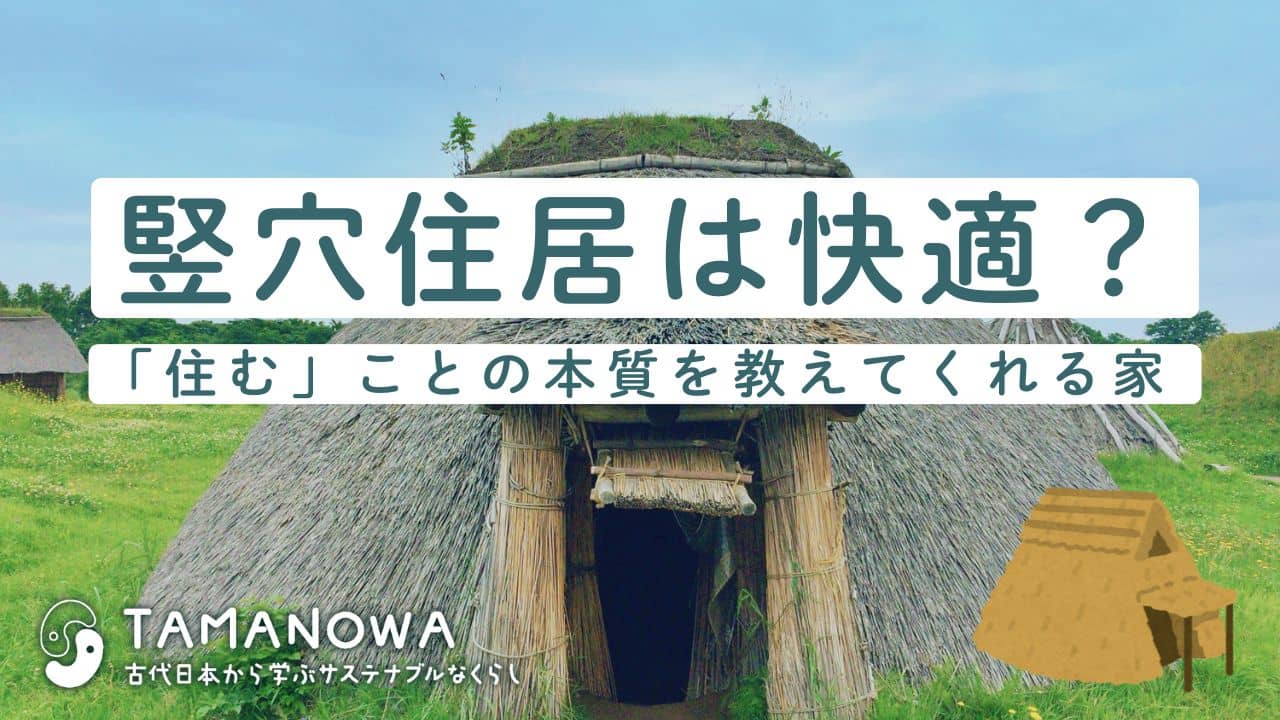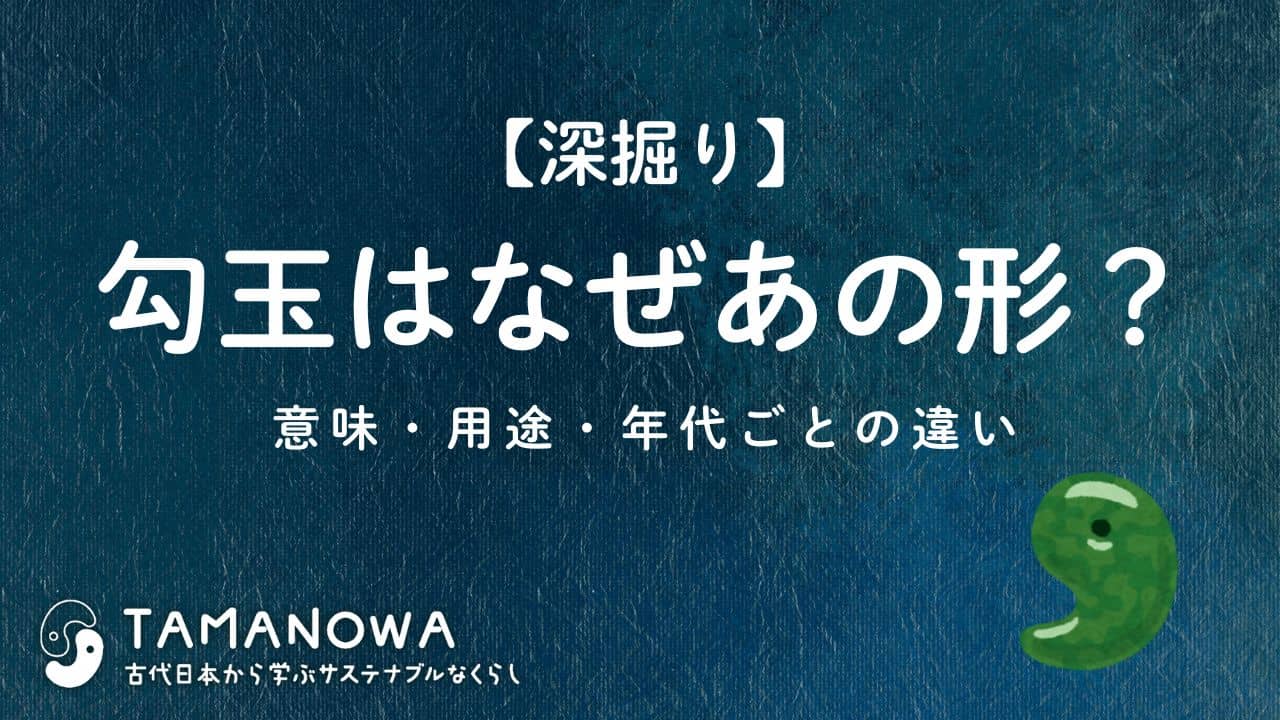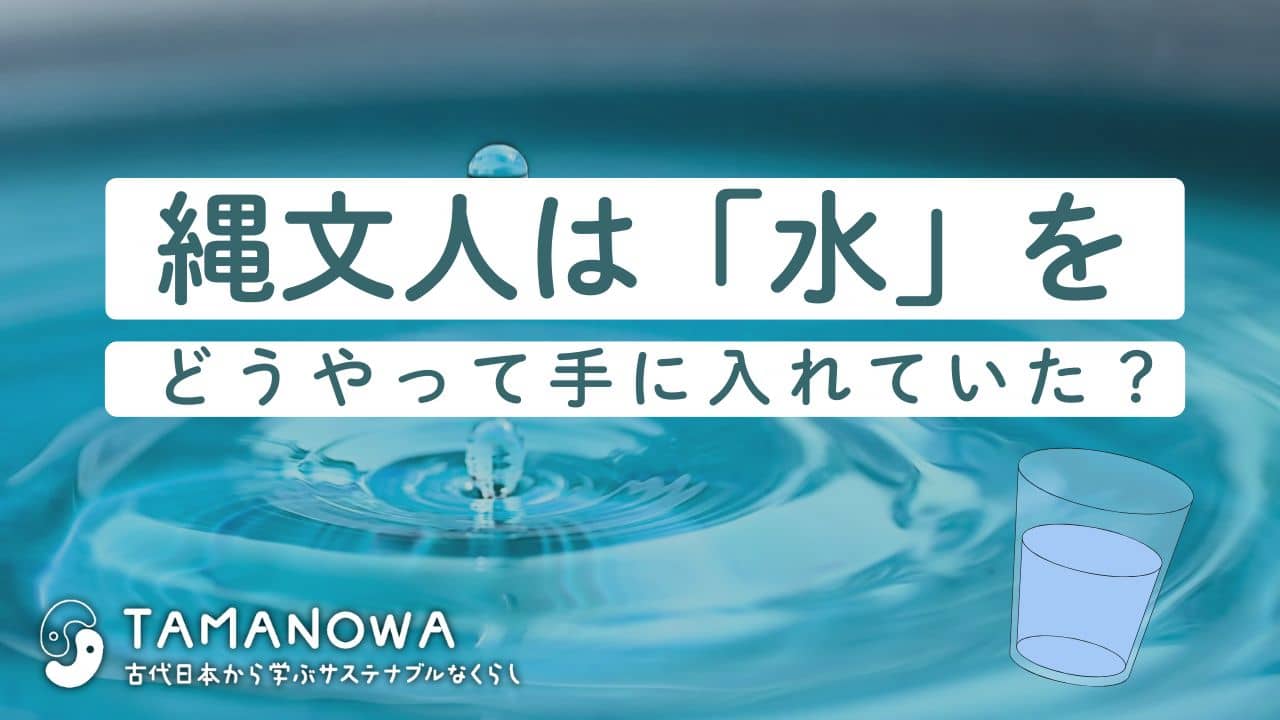「家族4人が、買い物を一切せずに毎日食べて暮らす。」
そんな暮らしができたらすごいと思いませんか?
でも同時に、「そんなの無理に決まってる」「マンガの世界だよ」って思う人も多いかもしれません。
実は、自給自足って言ってもいろんなレベルがあります。
家庭菜園でトマトを育てるのもひとつの自給。反対に、すべての食べ物を畑と自然だけでまかなうのは、かなり大きなチャレンジです。
このコラムでは、「家族全員の自給自足」について、現実的な視点で考えてみます。
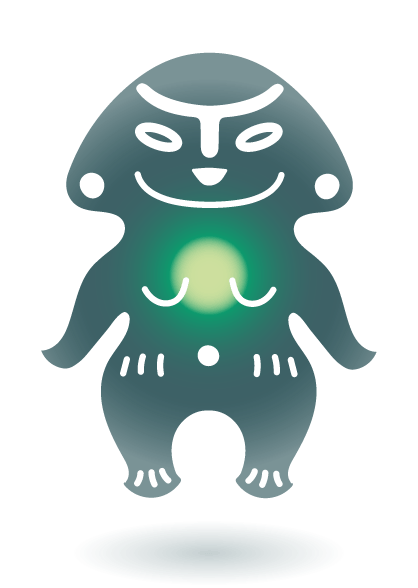
ヤマガ
はじめに|自給自足って、本当にできるの?
「もし本当に、市場(スーパーやお店)に頼らず、家族4人分の食べ物をすべてまかなうとしたら、どれくらいの面積が必要なんだろう?」
そしてそれは、今の日本でどれだけ現実的なんだろう?
私たちが日ごろ食べている野菜やお米、魚やお肉。
そのほとんどは、お金を出して買っています。でも、もし災害が起きたり、物価が高くなったり、輸入に頼っているものが手に入らなくなったら?
「食べること」って、意外とすごくもろいんです。
そんなときに、自分たちで少しでも作れるようになっていたら、安心感が違います。
しかも、土にふれたり、収穫のよろこびを味わったり、体にも心にもいいことがたくさんあります。
自給自足を考えるときに必要な視点
「どれだけの食材が必要か」と考えるだけでは足りません。
次のような視点が必要です。
| 視点 | 内容 |
|---|---|
| 食材の量 | 一年間で家族4人(例)が食べる量を想定する |
| 面積 | その食材を育てるために必要な土地の広さ |
| 時間 | 毎日どのくらい手間がかかるか |
| 保存 | 作物がとれる季節に偏りがあるので、保存する工夫 |
| タンパク質 | 肉や魚、卵などの供給方法をどうするか |
このうち、最初に大きなハードルになるのが「面積」です。
たとえば、お米を育てる田んぼや、野菜を植える畑、鶏の小屋などを合わせると、どれくらいの広さがいるのでしょうか?
次の章では、米を中心にした本格的な自給生活モデルをもとに、必要な広さを具体的に見ていきます。
面積はテニスコート何面分かで表現するので、イメージしやすくなると思います。
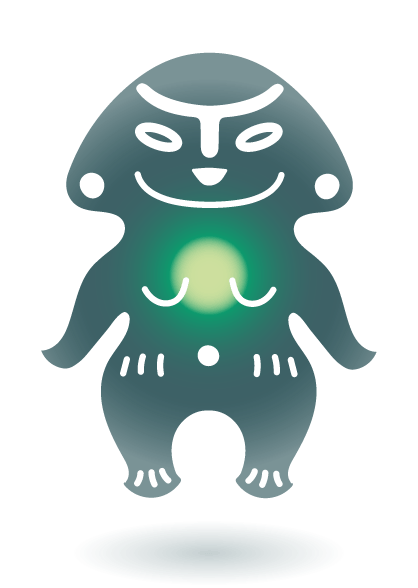
ヤマガ
たべるということは いきるということ。
たべものを どこから もらっているのか、
かんがえてみるノダ。
自給モデル①|米を中心とした“理想的だが非現実的”な方式
「日本人なら、やっぱりお米!」
そう思う人も多いでしょう。実際、今でも多くの家庭ではごはんを主食にしています。では、お米を中心にした食生活を、自分たちだけでまかなうとしたら、どれくらいの土地が必要なのでしょうか?
家族4人が1年間に食べるお米の量は?
まずは、どれくらいのお米が必要かを見てみましょう。
| 人数 | 年間に必要なお米(精米) |
|---|---|
| 1人分 | 約60kg |
| 4人分 | 約240kg |
1人あたり1日200g(お茶碗に軽く2杯分)くらいとして計算すると、年間で60kgほどになります。つまり、4人家族では240kgが目安になります。
田んぼはどれくらい必要?
お米は、10アール(=1000㎡)の田んぼから、およそ450kgの玄米がとれます。これを精米すると約360kgになります。つまり、1000㎡の田んぼがあれば、家族4人が1年食べるお米が十分にまかなえるということです。
野菜や卵のための面積も必要
お米だけでは食生活は成り立ちません。副菜になる野菜、たんぱく質として卵や肉も必要です。それぞれどのくらいの面積が必要かを見てみましょう。
| 用途 | 必要面積(㎡) | 内容 |
|---|---|---|
| 米 | 約1000㎡ | 主食(年間240kg) |
| 野菜・豆・イモなど | 約500㎡ | 副菜・保存用も含む |
| 養鶏(10羽) | 約30㎡ | 卵や鶏肉として活用 |
合計すると、約1530㎡が必要になります。これをテニスコートの広さで表すと、約5.9面分です。
テニスコート約6面分って、どれくらい?
テニスコート1面の広さは約260㎡です。つまり、畑や田んぼ、鶏のスペースなどを合わせると、
260㎡ × 約5.9面 = 約1530㎡(約460坪)
これは、ちょっとした運動場くらいの広さです。
都会や郊外の住宅地では、これだけの土地を確保するのはかなり難しいですよね。
どこが一番ハードルなのか?
答えは、田んぼの面積です。お米を育てるには、水の管理も必要ですし、平らで広い土地も必要になります。しかも、収穫は年に1回だけ。そのため、1年間分をまかなうには、どうしても広い面積が必要になります。
次の章では、お米にこだわらず、面積を節約しながら保存性も高い食材をうまく組み合わせた、現実的な自給モデルを紹介していきます。
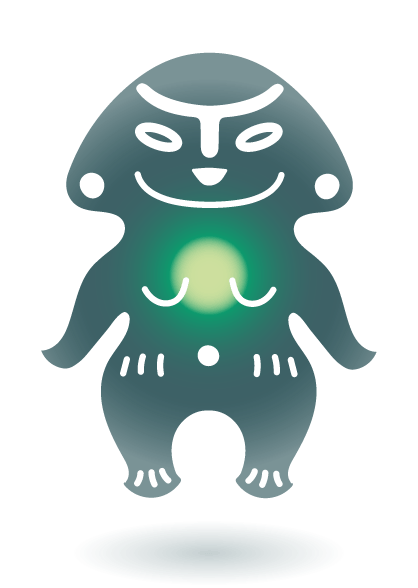
ヤマガ
コメは ちからのもと。
でも つくるには ひろいばしょと みずがいるノダ。
自給モデル②|保存性を重視した“面積節約”の現実解
前の章で紹介した「米中心の自給生活モデル」は、理想的ですが面積がとても大きく、現代の暮らしではなかなか実現が難しいと感じた人も多いと思います。
では、もう少し現実的な方法はないのでしょうか?
ここでは、「面積を節約すること」と「保存のしやすさ」を組み合わせて、もう少し身近なモデルを考えてみます。
米の代わりになる主食ってあるの?
お米はおいしいし、日本人にとって大事な主食ですが、育てるには広い田んぼと水が必要です。そこで、お米以外にも、主食になりうる作物を探してみましょう。
| 作物 | 特徴 | 保存性 | 必要面積(お米の代わりとして) |
|---|---|---|---|
| サツマイモ | 高カロリー、育てやすい | 数か月 | 約300~400㎡ |
| 雑穀(ヒエ・アワなど) | 病害虫に強い、乾燥に強い | 長期保存可能 | 約200~300㎡ |
| 大豆・小豆 | タンパク質もとれる、乾燥保存可能 | 数年単位で保存 | 約300㎡ |
こうした作物は、保存もしやすく、少ない面積で栽培できるのがポイントです。特にサツマイモは1株で大きく育ち、収穫も楽です。
面積をどこまで減らせる?
お米をやめて、イモや雑穀、豆を主食の中心に切り替えると、かなり面積を節約できます。
| モデル | 必要面積(㎡) | テニスコート換算 |
|---|---|---|
| 米中心の自給モデル | 約1530㎡ | 約5.9面分 |
| 面積節約モデル | 約800㎡ | 約3.1面分 |
実に半分近くまで削減できます。これは大きな差ですね。
保存を前提にした栽培がカギになる
面積を減らすと、どうしても「収穫量の波」が出てきます。夏はたくさん採れるけど、冬には何もない。そんな状況を防ぐには、「保存」を前提とした作物選びや加工がとても大事になります。
たとえば、以下のような方法があります。
| 食材 | 加工方法 | 保存可能期間 |
|---|---|---|
| サツマイモ | 干し芋 | 3か月~半年 |
| 大根 | 干し大根・たくあん | 数か月 |
| ナス・キュウリ | 塩漬け | 数週間~数か月 |
| 豆類 | 乾燥 | 1年~数年 |
| 雑穀 | 脱穀・乾燥 | 1年~数年 |
保存性の高い食材を中心に育てると、収穫のない季節も安定して食べていけます。
また、冷蔵庫がなくても使える「土中の保存」や「瓶詰め」「発酵」などの方法も、昔から使われてきた知恵です。
養鶏はコンパクトで効率的
たんぱく質をどうするかも重要な課題です。肉や魚は手に入りにくいですが、鶏は比較的飼いやすく、少ないスペースで卵を安定して産んでくれます。
| 飼育数 | 必要スペース | 得られるもの |
|---|---|---|
| 10羽 | 約30㎡(約0.1テニスコート) | 1日6~8個の卵、時々肉にも |
卵は料理にも使いやすく、保存もある程度ききます。鶏はエサや水、掃除の手間はかかりますが、少人数の家族ならとても頼りになる存在です。
次の章では、「そもそも昔の人たちはどうやって食べ物を確保していたのか?」という視点から、縄文人の食生活を見ていきます。実は、保存と多様性において、現代よりも学ぶところがあるかもしれません。
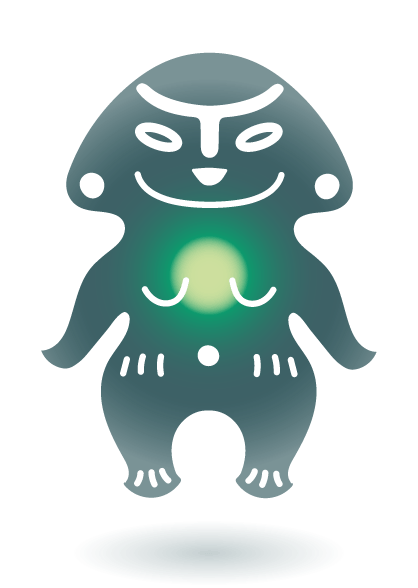
ヤマガ
すぐ たべられないなら、
ながく のこす くふうを すればいいノダ。
ちいさな ばしょでも、ながい じかんを つかえば、
たべるものは ちゃんと ふえるノダ。
ところで縄文人は?|「意外に豊か」だった狩猟採集生活
今まで見てきたように、現代での自給自足には広い土地や保存の工夫が必要です。
でも、よく考えてみると、昔の日本人、たとえば縄文時代の人たちはどうやって暮らしていたのでしょうか?
農業が本格的に始まるのは弥生時代から。
それより前の縄文時代(約1万5千年前〜2千数百年前)は、畑も田んぼもない中で、数千年ものあいだ人々は自然の中で生きてきました。
では、彼らの食生活はどうだったのでしょう?
縄文人は何を食べていたの?
縄文人は、自然の中で手に入る食べ物を季節ごとにうまく組み合わせて暮らしていました。
それをまとめると、こんなにたくさんの種類があります。
| 食材の種類 | 具体的な例 |
|---|---|
| 木の実 | クリ、ドングリ、クルミ |
| 山の動物 | シカ、イノシシ、ウサギ |
| 魚・海産物 | タイ、サケ、カツオ、貝、イルカ |
| 山菜・草の根 | ゼンマイ、ワラビ、ヤマイモ |
| 鳥の卵 | 水鳥の卵など |
| 昆虫・ハチミツ | ハチノコ、ミツバチの巣 |
驚くほど多彩です。
「食べられるものを見つけてきた」だけでなく、きちんと調理や保存もしていたことがわかっています。
主食という考え方はなかった?
現代では「白いごはんとおかず」という食事スタイルが当たり前ですが、縄文時代には「これが主食です」という決まりはありませんでした。
その時期にとれるものを、少しずつ組み合わせて食べるのが基本です。
秋にはクリやドングリをたくさん拾い、粉にして団子にしたり、
海辺では魚や貝を焼いたり煮たりして食べていたようです。
調理や保存の工夫も進んでいた
縄文人は、ただ焼いて食べるだけではありませんでした。土器を使って煮込んだり、保存用に干したり、食材のアクを抜くための手順も知っていました。
特にすごいのはドングリ。生のままでは渋くて食べられないのに、水にさらして渋みを抜いたあと、粉にして保存していたことがわかっています。
また、クリの栽培を行っていた可能性もあると言われており、食料の安定供給を意識していたこともうかがえます。
意外とバランスのよい食事だった
動物の肉や魚に加え、木の実や山菜など植物も多く取り入れていたため、現代よりも栄養バランスがよかったとも言われています。
発酵食品ははっきりとはわかっていませんが、自然発酵を利用した例があっても不思議ではありません。
保存すること、分かち合うこと、季節に合わせて食べること。
縄文人の暮らしは、自然とともにある、無理のない食のスタイルだったのかもしれません。
自然からいただく、という考え方
面積の制約がある現代の暮らしでは、食べ物すべてを自分の土地だけで育てるのはどうしても難しくなります。
そこで参考になるのが、縄文人のように「自然界からいただく」という視点です。
山に入って山菜を摘む、野草を食材として使う、近くの川で魚を釣る。
こうした行為は、畑を広げるのとは違った意味での「自給」になります。
自分の畑でまかなえるぶんは育て、足りないぶんは自然の中にあるものを知り、感謝していただく。
そうした暮らしの知恵を組み合わせることで、無理なく自給に近づく道がひらけてくるのです。
次の章では、ここまでの内容をふり返りながら、現代の私たちがどこからなら無理なくはじめられるのかを考えてみましょう。
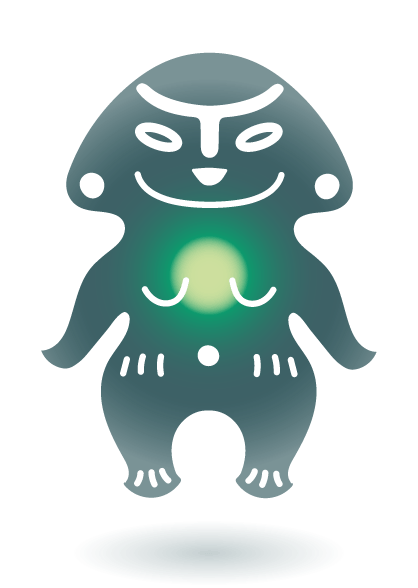
ヤマガ
むかしの ひとたちは、たべものを さがしながら、
いのちと いっしょに あるいていたノダ。
まとめ|まずは小さな一歩から、自給のある暮らしへ
ここまで、家族4人分の食生活をすべて自給するにはどれくらいの土地が必要なのか、どんな工夫をすれば面積を減らせるのか、さらには縄文時代の人々がどのように食料を確保していたのかを見てきました。
お米を主食にした場合、必要な土地はテニスコート6面分ほど。
それを面積の少ない代替作物や保存法で工夫すれば、半分程度まで圧縮することができます。
さらに、山菜や川魚など、自然界からの恵みをいただくという縄文的な考え方も合わせれば、限られた土地でも無理のない自給生活が見えてきます。
それでも、100パーセント自給はすぐには難しい
ただし、これをすぐに実行するのは簡単ではありません。
都市部や郊外の住宅街では、たとえ庭があっても畑にできる面積は限られていますし、田んぼや鶏小屋を持つことも現実的ではないことが多いです。
だからこそ、いきなり全てを自給することを目指す必要はありません。
今の暮らしの中で「少しだけでも、自分で食べ物を育てる」ことから始めるのが大切です。
はじめられることはたくさんある
以下のようなことなら、今日からでも始められます。
| できること | 内容 |
|---|---|
| プランター菜園 | ベランダでミニトマトや葉物野菜を育てる |
| 干し野菜づくり | 大根やキノコを干して保存にチャレンジ |
| 味噌づくり | 大豆と麹を使って自家製味噌を仕込む |
| 雑穀を食べてみる | ごはんにヒエやアワを混ぜてみる |
| 野草を調べてみる | 食べられる草花を知ることで視野が広がる |
これらはほんの入り口ですが、「自分で作る」「自然からいただく」感覚を身につける大きな一歩になります。
食べることは、生きること
スーパーに行けば何でも手に入る時代。
だからこそ、「食べることのありがたさ」や「自然とのつながり」を実感する機会は少なくなっています。
けれど、自分で少しでも作ってみると、食べ物ができるまでの大変さや楽しさに気づけるようになります。
そしてそれは、将来の安心にもつながっていきます。
100パーセントの自給は難しくても、自分で少しでも作り、自然を知り、暮らしの中に取り入れていく。
それだけで、毎日の食事が少しずつ変わっていくはずです。
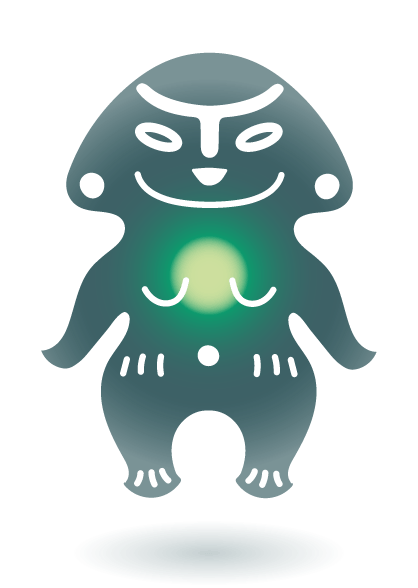
ヤマガ
ぜんぶ じぶんで つくれなくても、
ひとくちでも てから うまれたら、それで いいノダ。