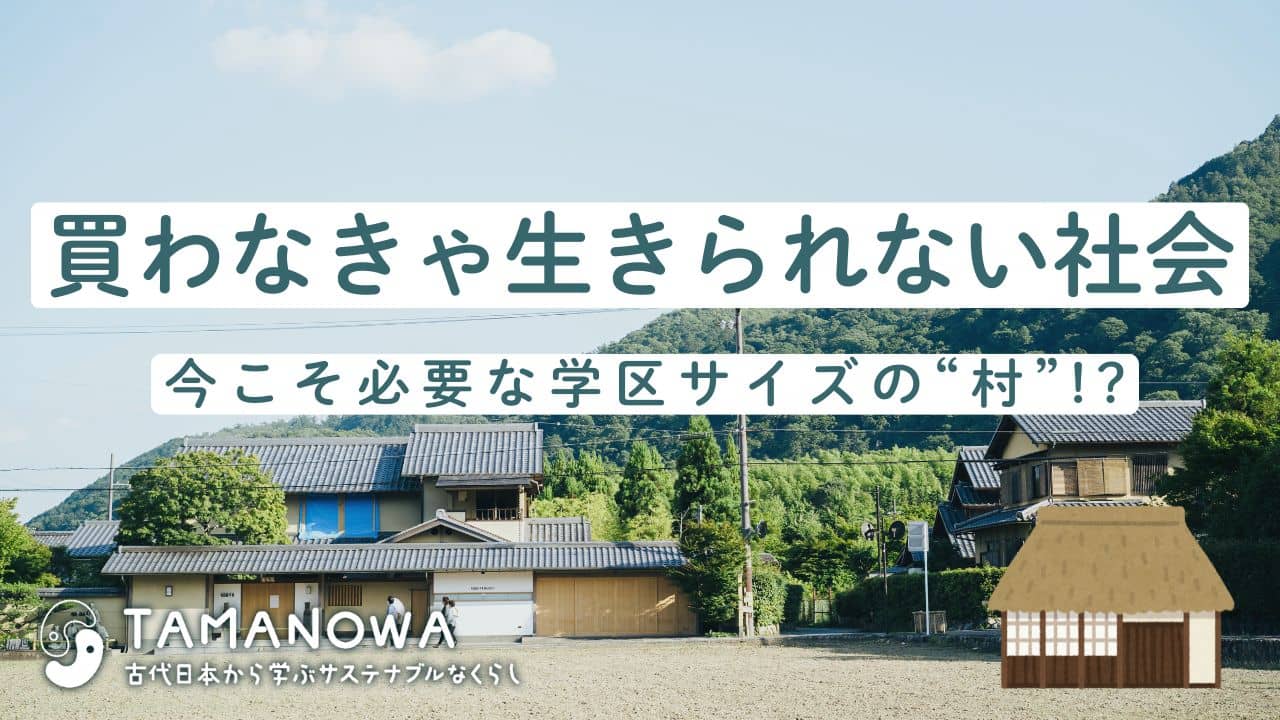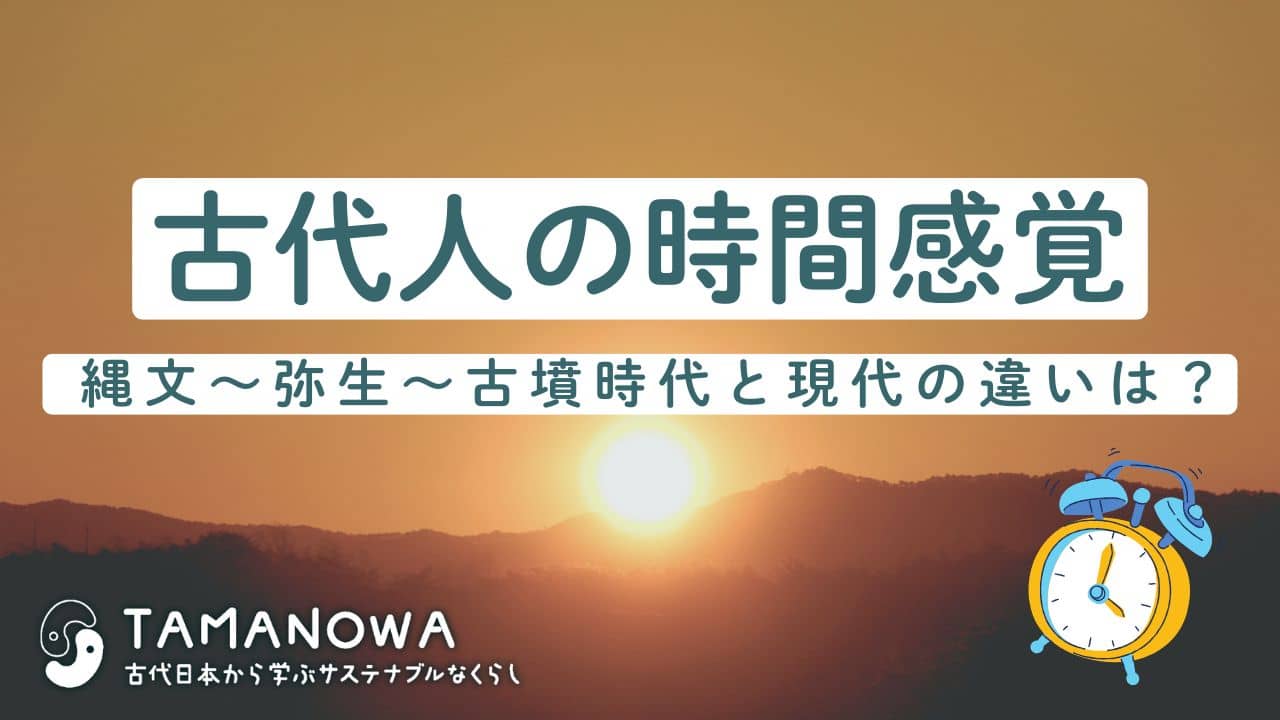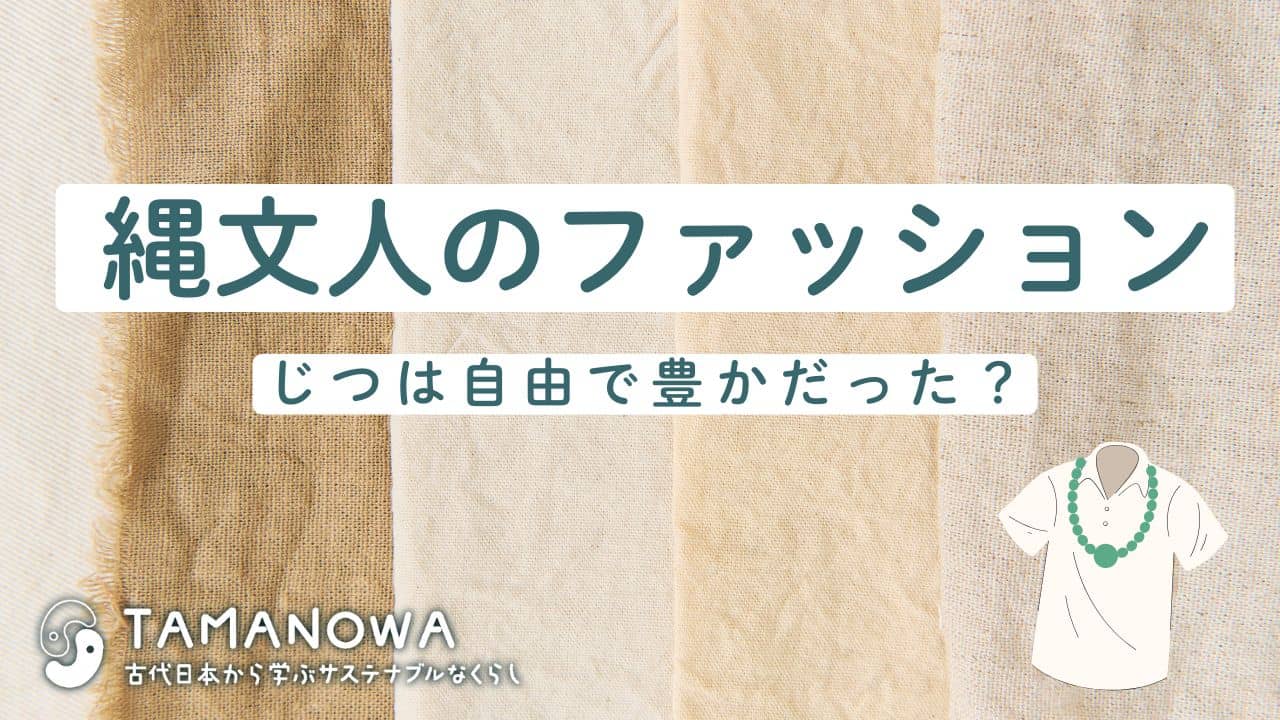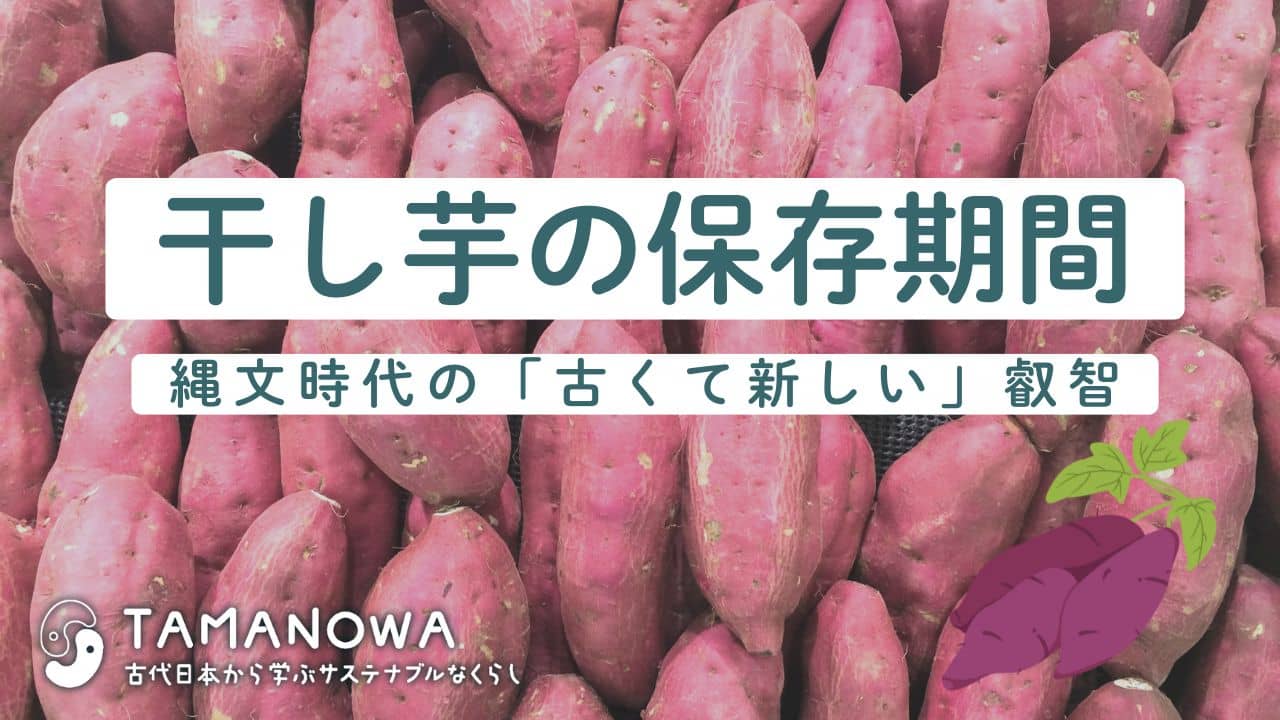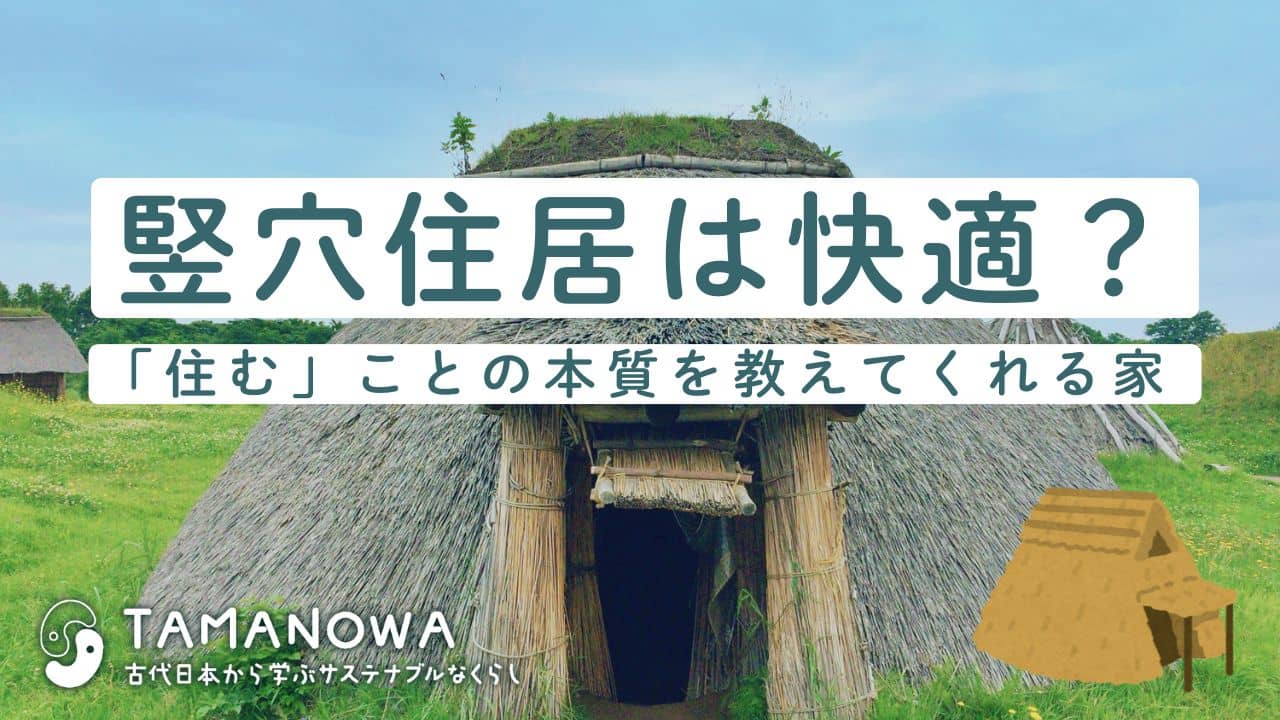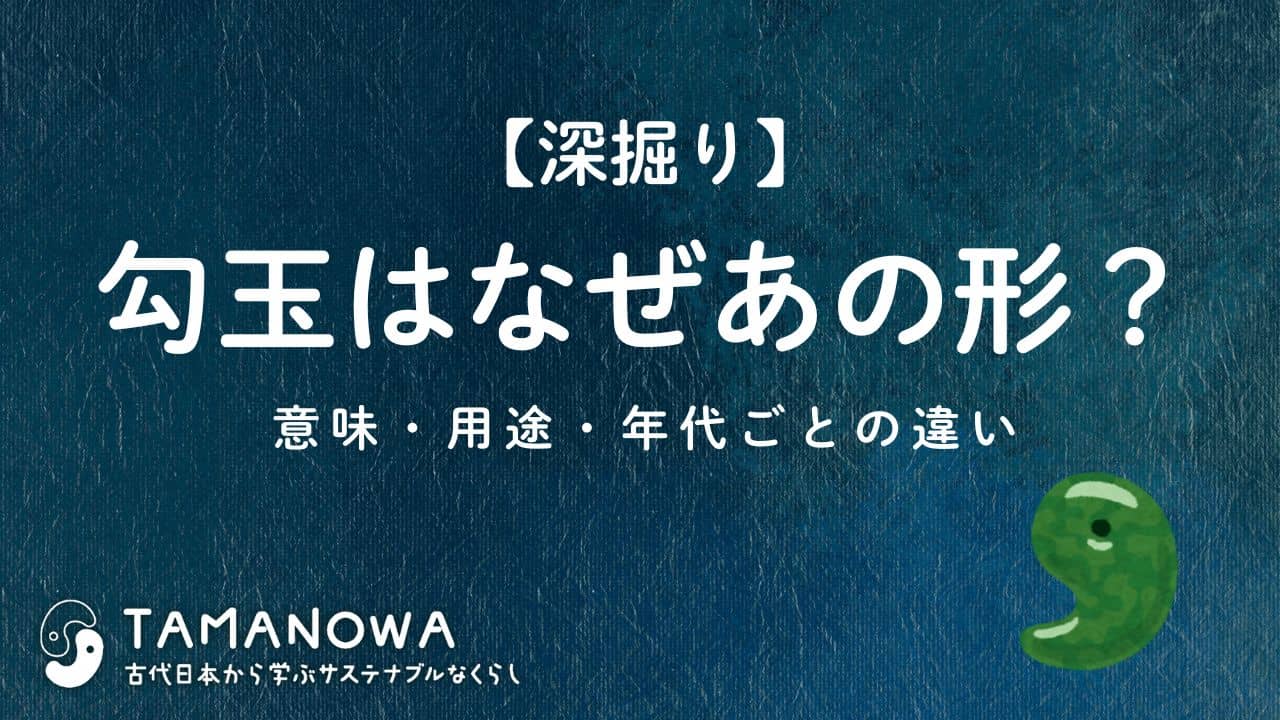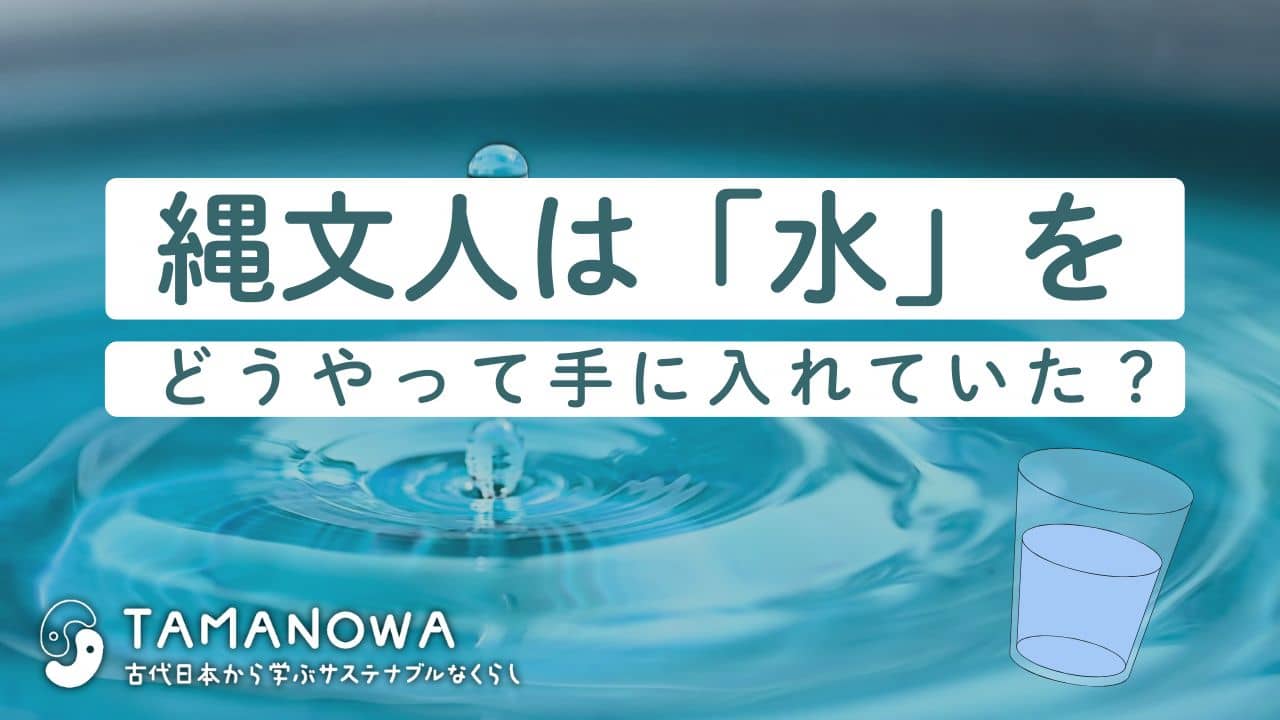もしも、明日からスーパーに食べ物が並ばなくなったら…
あなたの家は、何日生き延びられそうですか?
普段はあまり意識しないかもしれませんが、私たちの生活は多くの「外からの支え」で成り立っています。
とくに、食べ物。これを自分たちでまったく作らずに生きているということは、それだけ「買えなくなったら終わり」という状況でもあります。
では、そもそも日本って、自分の国でどれくらいの食べ物を作っているのでしょう?
今回のコラムでは、現代社会が抱える問題点と、それを根本から解決するための新しい社会のカタチについて考えてみます!
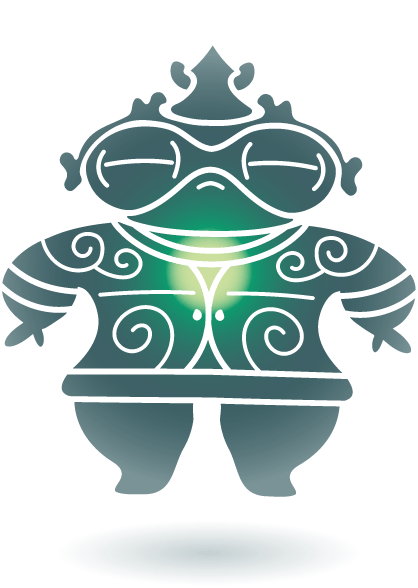
シャコー
実はこの社会、意外と“もろい”のかもしれない
農林水産省の発表(令和4年度)によれば、日本の食料自給率(カロリーベース)は38%。
つまり、食べているカロリーの6割以上を外国からの輸入に頼っているのです。
そして、筆者の暮らす静岡県では、さらに厳しいデータがあります。
静岡県の食料自給率はなんと15%。
これは、10人のうち約9人は「生きるために必要な食料を地域内では得られない」ことを意味します。
参考:農林水産省「令和4年度 食料自給率」
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/attach/pdf/zikyu_10-8.pdf
もし食べ物が来なくなったとき、どうなる?
今の日本では、食べ物の多くが船や飛行機にのって、遠くから運ばれてきます。
でももし、世界的な災害や戦争、あるいは港が使えないなどの非常事態が起きたら?
あるいは物価の急騰で、輸入ができなくなったら?
食べ物が来なければ、家族も、自分も、生きていくことはできません。
それって、ちょっと怖くありませんか?
家の近くに畑があるのになぜ自給できないの?
たとえば、自宅のまわりに畑がたくさんあったとしても、その野菜が「売るためだけ」に作られていたら、いざというときに「分けてもらう」というわけにはいきません。
さらにいうと、農地の多くでは農薬や肥料、機械や燃料といった、これまた外から買わないと手に入らないものに頼っています。
輸入資材も加味すると、ほとんどゼロに近くなるとも言われています。
つまり、「近くに畑があれば安心」とも言いきれないのです。
実際にどれくらいの人が飢える?
この食料自給率38%という数字を、別の見方をすると、10人のうち6人以上は十分に食べられないということです。
あなたや家族が、その「食べられない6人」の中に入らないという保証は、どこにもありません。
食べ物が買えなくなったとき、あなただけは助かると思えますか?
この問いに自信をもって「はい」と言える人は、実はとても少ないのです。
今の暮らしは「買える前提」に頼りすぎている
あたりまえのように毎日買い物をして、ごはんを作って、食べて、眠る。
でもその「あたりまえ」は、ぜんぶ「お金を払えば手に入る」という仕組みに支えられています。
でも、もしその仕組みが止まってしまったら?
お金を出しても食べ物が買えない。水が出ない。電気がこない。
それが現実になったら、私たちは何もできないまま、ただ待つしかないのです。
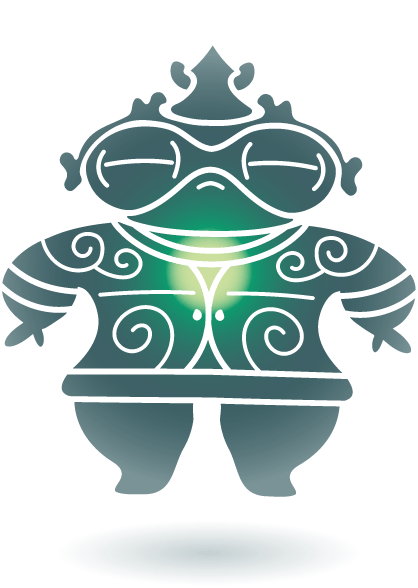
シャコー
なんでも買える時代こそ、なにかを失いやすいのデス。
おにぎり一つの重みを、もう一度かみしめてみるのデス。
なんでも自給?理想を突きつめた“限界村”の姿
ここまでで、「今の社会は意外ともろいかもしれない」ということが見えてきました。
では、その反動として、「全部を自分たちでまかなう村」を作ったらどうなるのでしょうか?
理想をとことん追い求めてみたら…
電気もガスも使わない。水は川や井戸から。食べ物は全部自分たちで作る。
服も自分で織って、道具も手作り。建物も自分たちの手で建てる。
そんな暮らしを「自給自足の理想」として思い浮かべる人もいるかもしれません。
実際、それを目指したコミュニティが、これまでいくつも日本で立ち上がってきました。
でも――続かなかったのです。
理由1:全部はとにかく無理がある
たとえば農作業に1日。服づくりに1日。火おこしや薪集め、水くみも入れたら、あっという間に時間が足りなくなります。
そして、どれも「専門技術」が必要になります。
本や動画を見ながらでは難しいこともたくさんあり、ひとつの作業を失敗すれば生活全体に影響が出てしまいます。
理由2:特別な人にしかできない
体力、知識、技術、精神力…
すべてがそろっていないと難しい暮らし方です。
若くて健康な人だけならまだしも、子どもや高齢者、障がいや病気を抱える人も含めて暮らしていくには、ハードルが高すぎました。
理想だけでは村は続かない
全部を手作業でまかなう「限界まで理想を追求した村」は、たしかに一部の人には合っていたかもしれません。
でも、それが「みんなにとってやさしい暮らし」だったかというと、答えはちがいます。
「自給できること」だけに頼るのは、また別のもろさ
買わなくても生きていける。
たしかにそれは大きな安心感です。
でも、完全に「外」との関係を絶ってしまうと、こんどは「人と支えあう」というつながりも切れてしまいます。
結果として、自給はできても孤立してしまい、村が続かなくなったケースもありました。
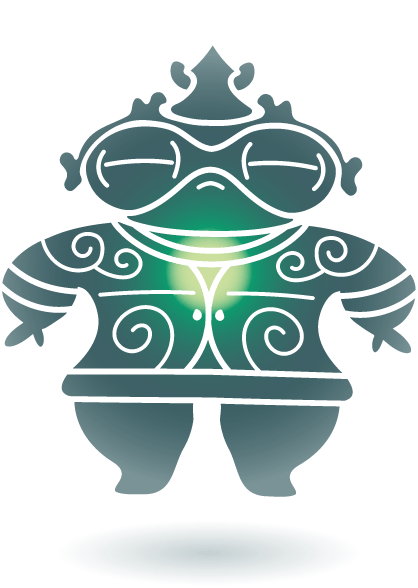
シャコー
ぜんぶ自分で、はカッコいいけど、つかれるのデス。
みんなで助けあうと、暮らしに風がとおるのデス。
“ほどよい自給”という考え方:現代人にも続けられる村の形
「全部を自分たちでつくるのは、現実的にむずかしい」
その結論にたどり着いた人たちは、次にこう考えはじめます。
それなら、「できることは自分たちで」「できないことは外から」
そんな“ほどよい自給”の暮らし方はどうだろう?と。
「自給したい」の本音は、安心がほしいから
どうして人は、自給を目指すのでしょうか。
一番の理由は「安心したい」からです。
「明日からお金がなくなっても食べていける」
「停電しても生きていける」
そんな備えが、心の安定につながります。
でも、その安心のためにすべてを背負いこむ必要はありません。
自給するのは「食べもの」と「水」で十分
食料と水は、生きていく上で最も大切なインフラです。
だからまずはここを“完全自給”にしておくと、かなりの安心感があります。
とはいえ、すべてを自分の家庭でまかなうのは大変。
そこで考え方を少し変えて、学区サイズ=村サイズで自給をめざすのが現実的です。
村のなかで得意分野を分ける
「Aさんは畑」「Bさんは養鶏」「Cさんは味噌づくり」
こうして役割分担することで、1人ひとりが全部をやる必要はなくなります。
徒歩や自転車で行き来できる範囲に、いろんな“得意”を持った人がいれば、それだけで強いネットワークになります。
これが「村」という形のメリットです。
自給しない部分はどうする?
衣服、住宅、道具、エネルギーなど、どうしても自分たちでは作れないものもあります。
それは「外の世界」とうまくつながることで手に入れます。
ここでのポイントは、「買うこと」が悪いわけではない、ということです。
ただ、いざという時に“買えなくなっても”村内で最低限の安心が保てる状態を目指すのです。
「自給と交流」のバランス
“ほどよい自給”とは、孤立することではありません。
むしろ、内と外をバランスよく行き来しながら、村のなかで支えあう仕組みをつくることです。
「みんなで生きのびるための安心な場所」
それが、学区サイズの“村”のイメージです。
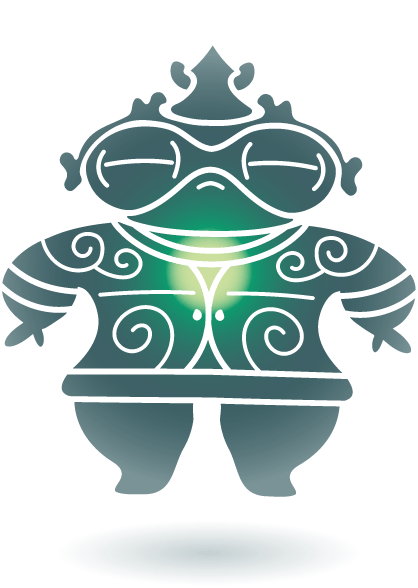
シャコー
がんばりすぎた村には、だれも寄りつかないのデス。
ゆるさと余白が、いきるチカラをつなぐのデス。
資材もすべて自給できる「菌ちゃん農法」
「食べ物は自分たちで作ればいい」と言っても、その農業が海外から輸入した肥料や農薬に頼っていたら、やっぱり外部依存です。
どこかの誰かが作ってくれたものをお金で買わないと、自分の畑も回らない。
そんな状況では、「自給」の安心感は手に入りません。
そこで紹介したいのか、資材も全て自然界から自給可能な「菌ちゃん農法」です。
菌ちゃん農法ってなに?
「菌ちゃん農法」は、農家・吉田俊道さんが提唱した、土の中の微生物(=菌ちゃん)の力を活かす農法です。
自然栽培の技法の一つとなります。
自然栽培は農家全体のわずか「1/1000」!?
現在の農業で主流なのは「慣行農法」といって、化学肥料や農薬を使用した農法です(資材の多くを海外からの輸入に頼っています)。
慣行農法は農家全体のほとんどを占めますが、逆に1%程度は「有機農法」という化学肥料や農薬を使用せず、有機肥料や天然由来の資材を使って土壌を改良し、作物を育てる農法を使っています。
そんな有機農法の中でさらに1%程度の農家が「自然栽培」という分野を選択していて、自然栽培は農薬や肥料を一切使用せず、植物と土本来の力を引き出す栽培方法です。
「菌ちゃん農法」は自然栽培の中の1つの手法です。
この農法では、海外から調達する肥料や農薬を一切使いません。
代わりに、身の回りのどこにでもある草や落ち葉、米ぬかや野菜くずといった“その場で手に入る資源”を使って、土づくりをします。
外に頼らない「資材の自給」ができる農法
菌ちゃん農法の最大の特徴は、「資材を買わなくていい」という点です。
お金がかからないだけでなく、資材を運ぶためのエネルギー消費もありません。
たとえば…
| 通常の農法 | 菌ちゃん農法 |
|---|---|
| 化学肥料を購入 | 落ち葉・草・米ぬかを活用 |
| ビニールマルチ使用 | 枯れ草や新聞紙で代用 |
| 土壌改良剤を購入 | 菌の力で自然に土壌が改善される |
これらはすべて、地域の中で手に入るものでまかなえます。
村にぴったりな理由
学区サイズの村では、農業が暮らしの中心になるかもしれません。
そのとき、菌ちゃん農法のような“資材まで自給できる仕組み”は非常に重要です。
・お金がなくてもできる
・ゴミが資源になる
・子どもでも手伝える
・肥料や農薬を使わないので安心
このような理由から、教育や福祉との相性もよく、地域全体で取り組むのにも向いています。
自分たちの足で、立つための農
「買わない農」は、ただ節約になるという話ではありません。
「いざというときにも、誰かが食べものを作れる」
その安心が、村という仕組みに厚みを加えてくれます。
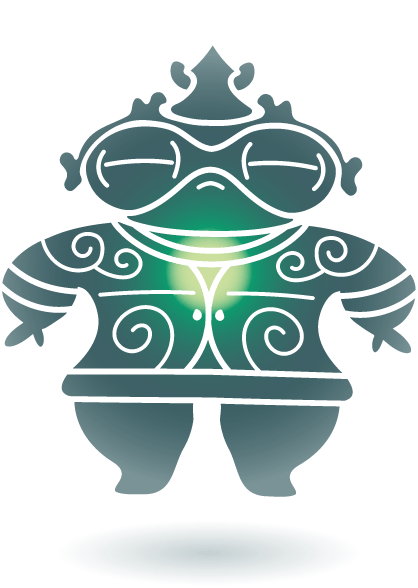
シャコー
つちの中にも、せかいはあるのデス。
ちいさな命とつながると、大きな安心がうまれるのデス。
ムラの“とくい”を外に届けよう:現金を生み出すには?
村の中で、食べものも水も作れるようになって、
住む場所も手作りできて、資材までなんとかなるようになっても――
それでもなお、「現金」は必要です。
たとえば、
- 電気や通信インフラ(太陽光や自家発電で補っても限界がある)
- 医療費
- 教材費や通学費
- 税金や保険料
こうした出費は、どれだけ自給自足が進んでも避けられません。
「何を売るか」ではなく「誰でも売れる」ことを探す
都会のマーケットに対して、村が何かを売ることで現金を得る。
そのとき、特殊な技術がある人にばかり頼っていたら、
村の大半の人は“受け取るだけ”になってしまいます。
そうではなく、
誰でも参加できて、誰かにとって価値があるものを、
村の“とくい”として形にしていく必要があります。
誰でもできる、でも価値があること
ここで少し視点を変えてみましょう。
「特別なスキルがない人にもできるけど、外から見ると価値があること」って、実はたくさんあります。
例えば:
| ムラの“とくい” | 外部に提供できる価値例 |
|---|---|
| 四季の自然風景 | 映像・写真素材、滞在型観光 |
| 手仕事(織物・竹細工など) | 地域ブランドとしての民芸品や日用品 |
| 子どもと高齢者の交流 | 教育や福祉の研修素材、モデル事例の発信 |
| 野菜の育成や収穫体験 | 体験ツアー、教育プログラム、動画販売など |
こうした価値を、インターネットを通じて外の人に届けることで、
小さくても確実な収益を生み出せるようになります。
村が“会社”になるイメージで
この村をひとつの「会社」だと考えてみてください。
社長がいなくてもいいし、競争もしなくていい。
みんなが「できることを、できる分だけ」持ち寄って、
外から必要なもの(=お金)を少しずつ引き寄せていく。
こんな形の「新しい会社」が、学区単位で成り立つなら、
それはすでに「自立した社会」と言えるかもしれません。
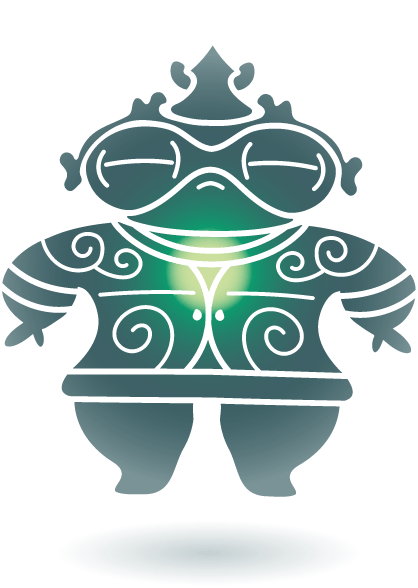
シャコー
「なにもできない」なんて、思いこみなのデス。
むらのチカラは、みんなで生んでいくのデス。
「学区サイズの村」が日本中に必要な理由
ここまで読んできた方は、こう思ったかもしれません。
そんな理想の村、ひとつ作ればいいんじゃない?
でも、実はそれだけでは不十分です。
全国に、いくつも必要なんです。
「一つだけの理想郷」では救われない
理想的な村がひとつだけあっても、そこに入れるのはごく一部の人だけ。
実際の災害や物流停止が起こったとき、
その村の外にいる人は助かりません。
逆に、全国各地に“学区単位”で村が点在していれば、
それぞれが自立しながら、同時に支え合うネットワークができます。
なぜ“学区”サイズなのか?
都市部の1区では難しいかもしれませんが、
郊外や地方であれば、学区はだいたい徒歩や自転車で移動できる範囲。
- 小さすぎず
- 大きすぎず
- お互いの顔が見える距離
このバランスがとれたサイズだからこそ、
地域の資源と人手を活かして支え合うのにちょうどいいんです。
それぞれの村が、“違う得意”を持つこと
全国に村が乱立したら、競争になるのでは?
と感じるかもしれませんが、実は逆です。
むしろ、
- 森が得意な村
- 漁が得意な村
- 発酵文化が深い村
- 教育ノウハウがある村
のように、それぞれが“ちがう強み”を持てば、
外貨(お金)を得る手段も、支援し合う方法も多様になります。
「買わなきゃ死ぬ」からの卒業へ
今の社会は、すべてが買わないと手に入らない世界です。
でもそれが止まった瞬間に、多くの人が生きていけなくなる。
それって、ちょっともろいと思いませんか?
学区サイズの村が各地にある社会は、
- 生きていくことが、ちゃんと身のまわりで完結し
- お金も、生きがいも、村の“とくい”を活かして得られる
そんな未来の選択肢のひとつなのです。
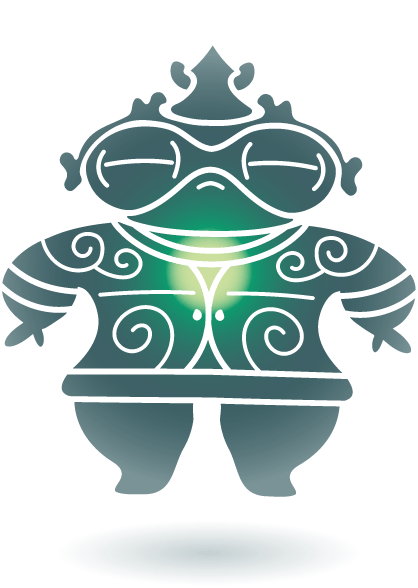
シャコー
おおきな国も、ちいさな村からできているのデス。
だからこそ、村をつくることは未来をつくることなのデス。
まとめ:「買わなきゃ死ぬ」社会から、自分たちで生きられる社会へ
私たちの社会は、便利で豊かになった一方で、
「すべてをお金で買う」ことが前提の、もろい仕組みになっています。
食料自給率は38%。静岡県に限ってはわずか15%。
災害や輸送網の停止が起きれば、多くの人が「食べられない」事態になるかもしれません。
そんな未来を変えるための方法として、
“学区サイズの村”という考え方を提案してきました。
この村では、
- 食料と水は完全に自給
- 衣・住もできる限り村内でまかなう
- 外に向けて、村の「とくい」を価値に変えて現金を得る
という仕組みを想定しています。
また、特別な人だけが活躍するのではなく、
老若男女だれでもできることを、お金に変える方法も考えました。
たとえば:
- 村の得意分野を活かした特産品や工芸品
- 村の知恵や風景を生かしたツーリズムや商品
- お年寄りの経験談を活かした学びの場づくり
このように、「とくべつな能力がなくても、価値が生まれる場所」が村のかたちです。
そして何より、全国に同じような村が広がれば、
お互いに支え合う「網の目」のような社会がつくれます。
買わなきゃ生きられないのではなく、
自分たちの手で暮らしを支えられる社会。
そのヒントは、実は“地域の中”に、もうあるのかもしれません。
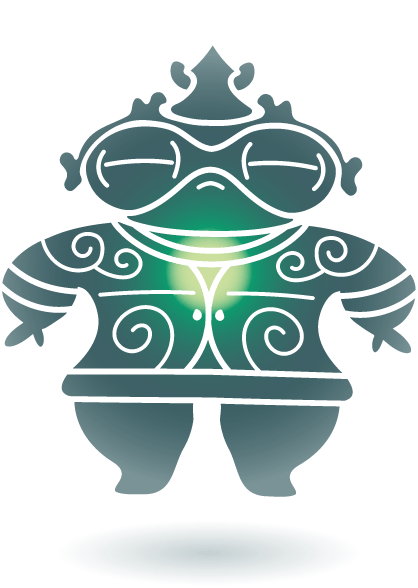
シャコー
ひつようなのは、だれかの正解じゃないのデス。
あなたの人生の答えを、ゆっくり探していけばいいのデス。