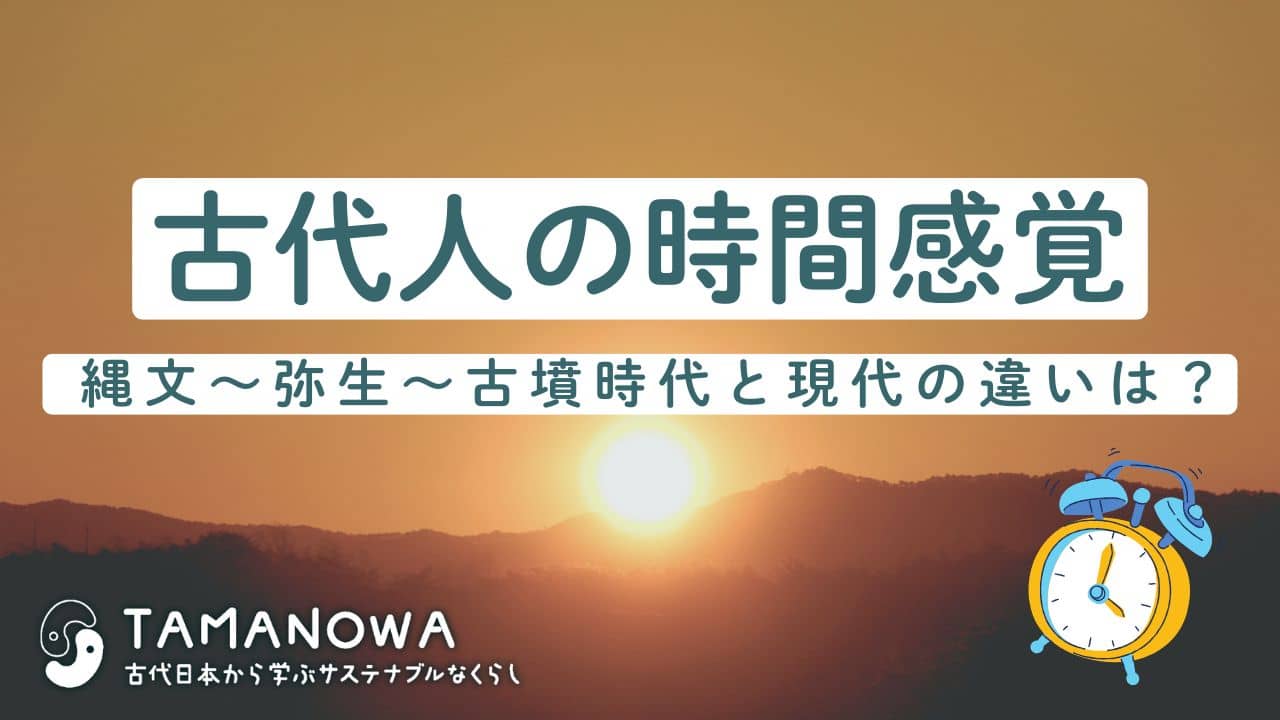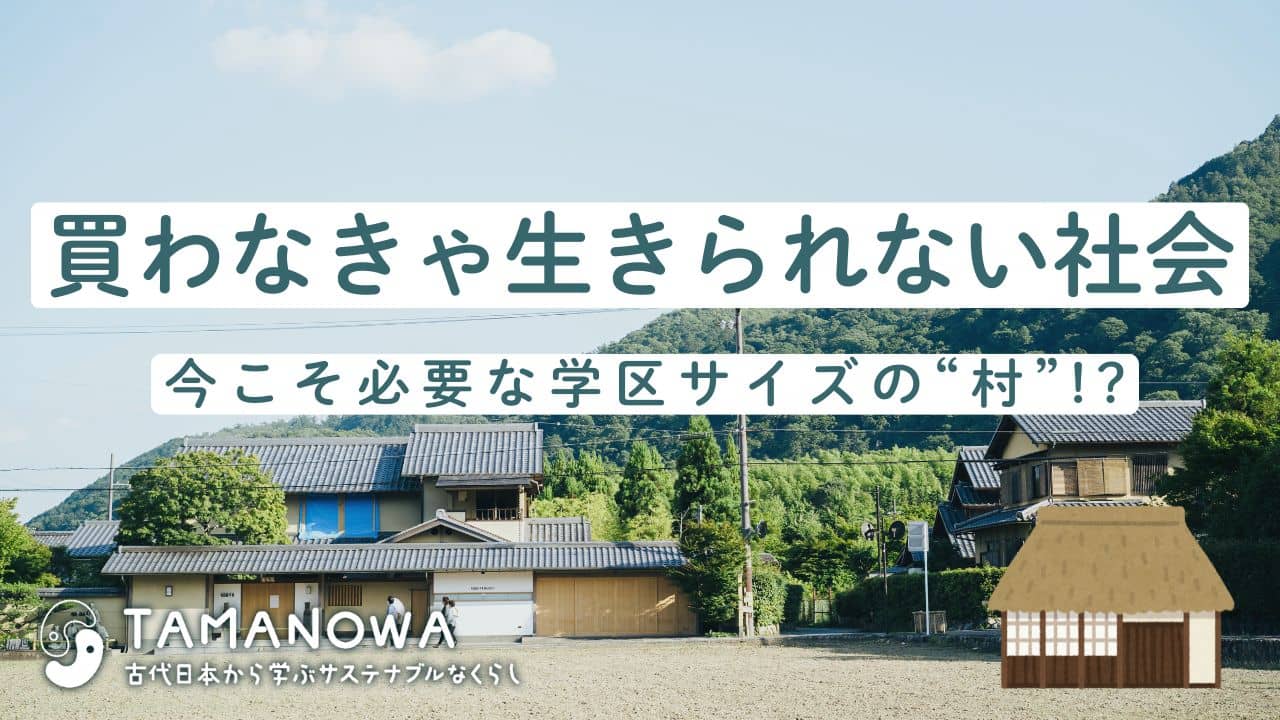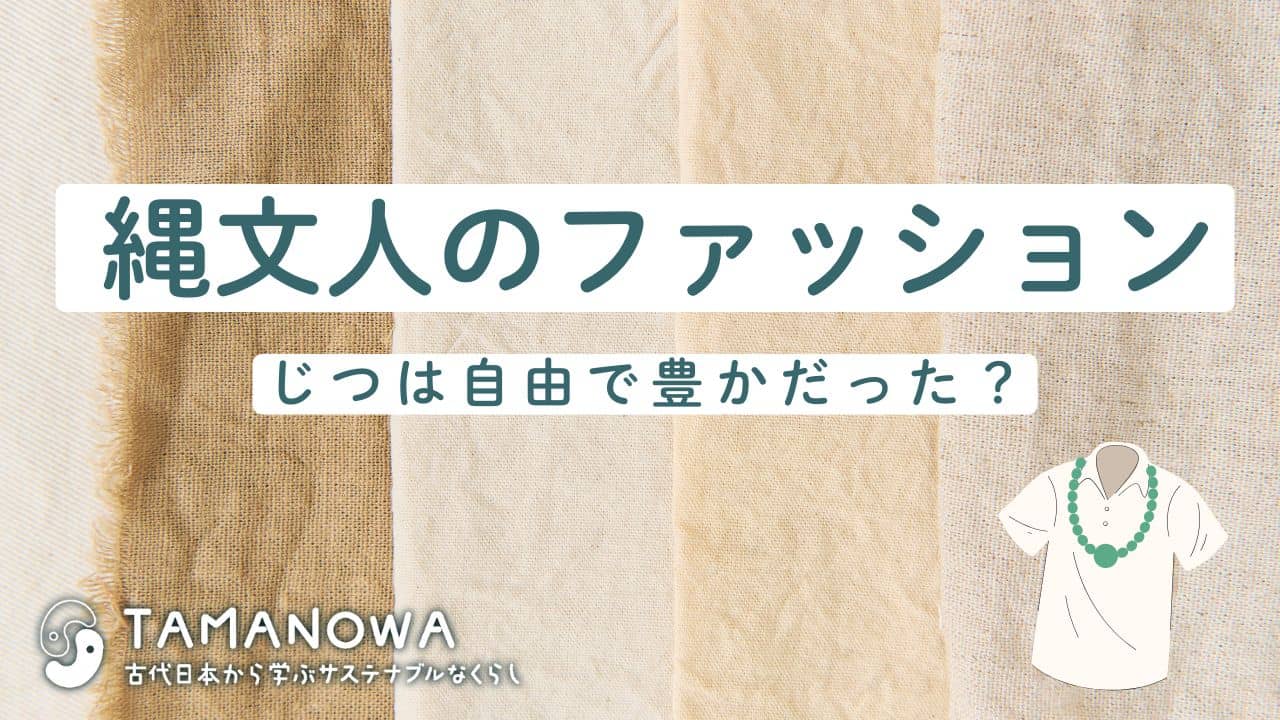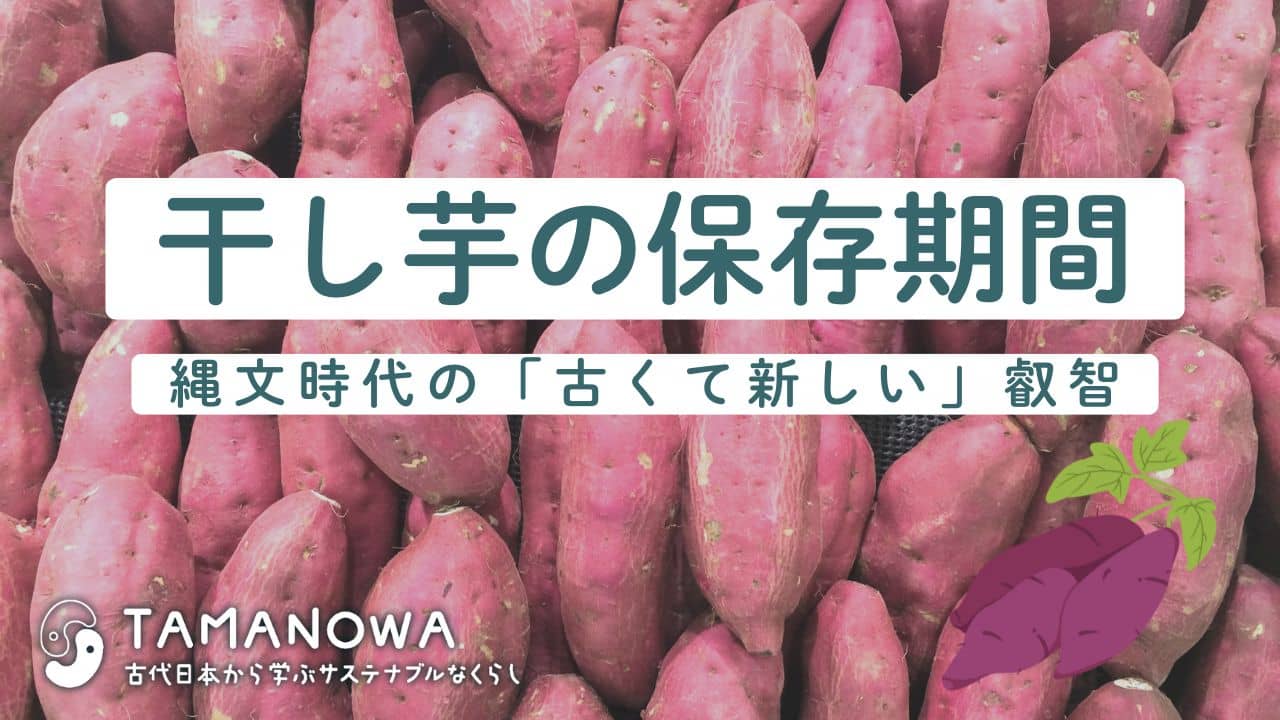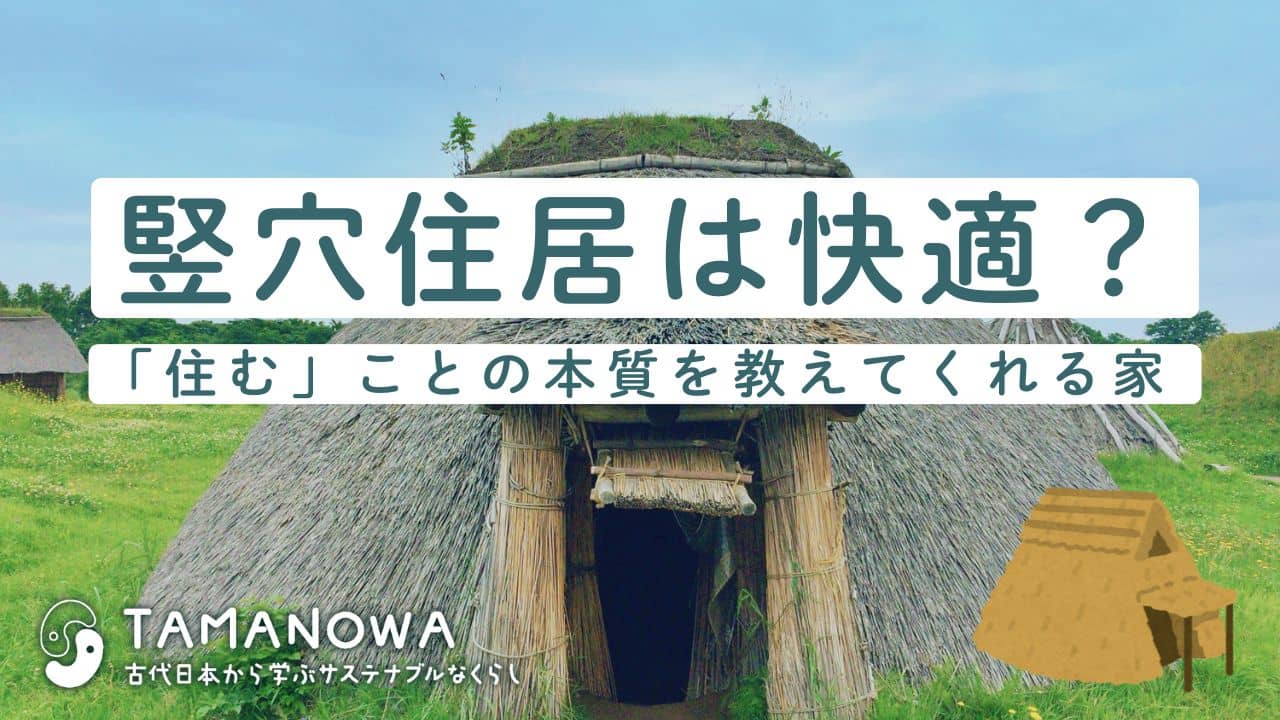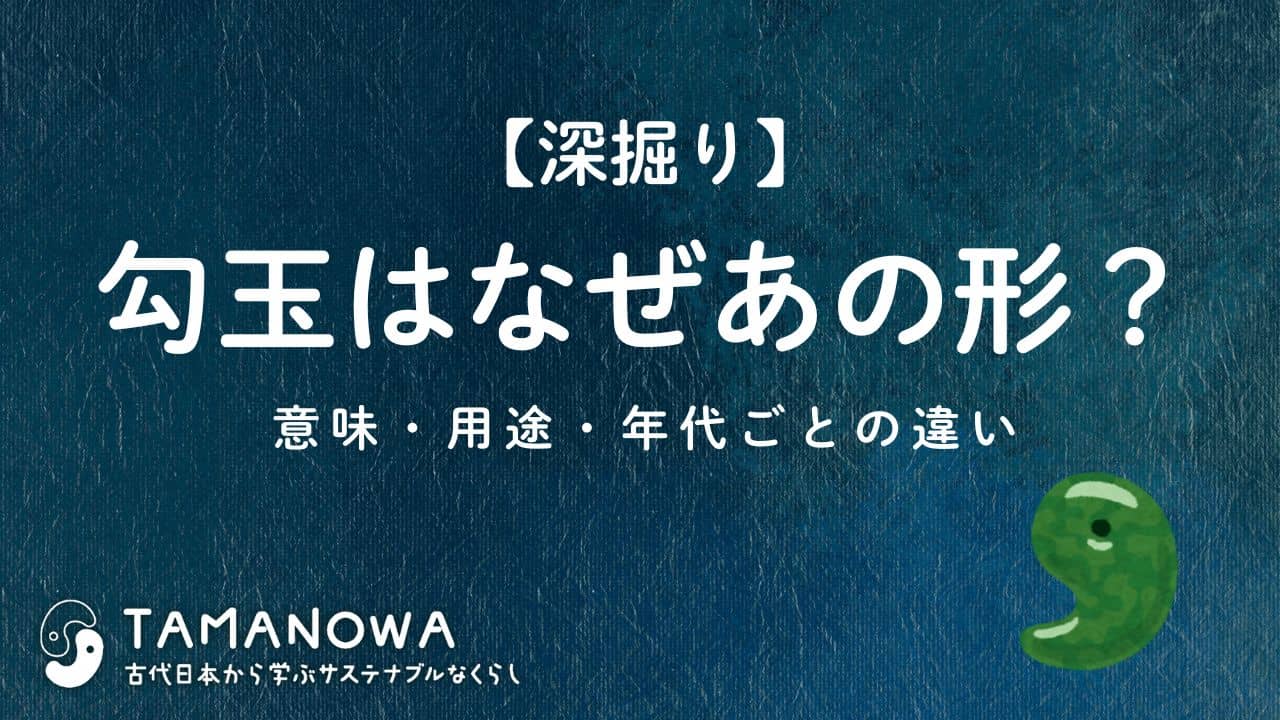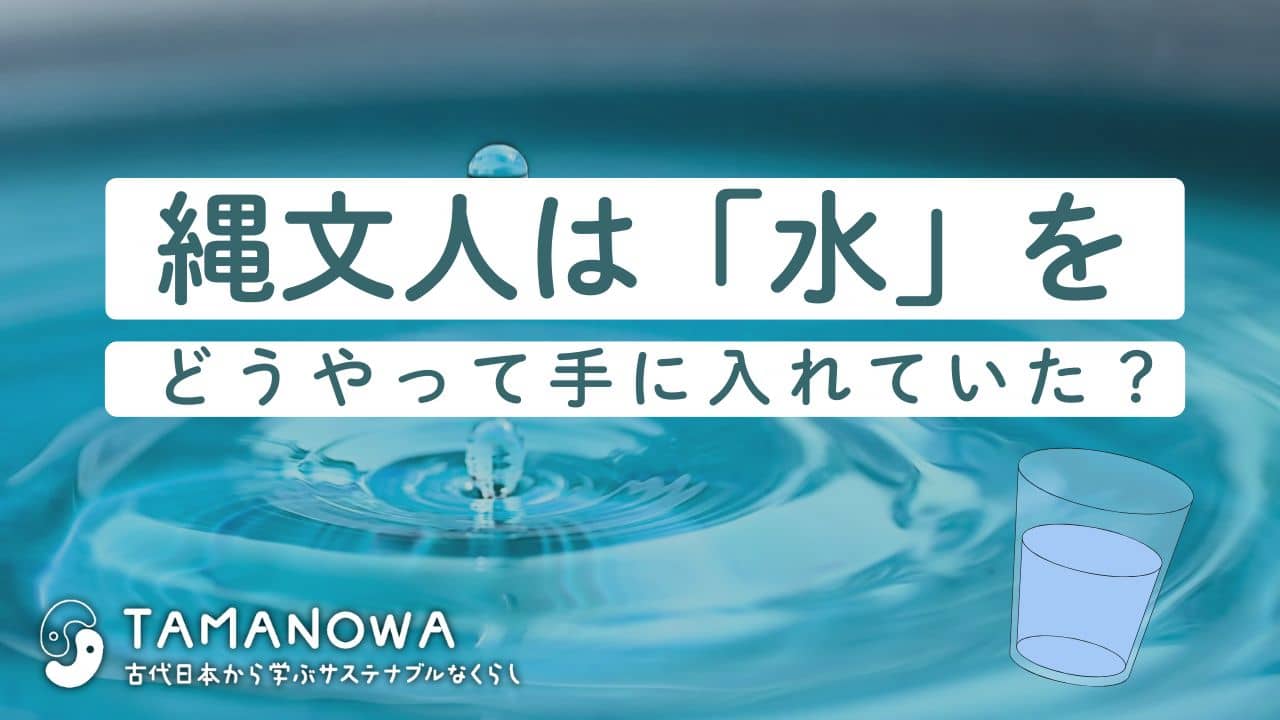もし今、腕時計もスマホもなくなって、「今は何時?」と聞いても誰も答えられないとしたら、どう感じるでしょうか。
このコラムでは、古代日本人がどのような「時間感覚」を持っていたのか、また現代人との違いについて、みていきます!

ミミー
時計のない世界で、人はどう暮らしていたのか?
多くの人が、不安になったり、予定が立てられなくなったりするかもしれません。でも、昔の人たちはそれが“ふつう”でした。
とくに、縄文時代(いまからおよそ1万5千年前〜2,300年前)は、数字の時間ではなく、自然の変化を頼りにして暮らしていた時代です。
たとえばこんな風にです:
| 時のとらえ方 | 現代 | 縄文時代 |
|---|---|---|
| 一日の区切り | 〇時〇分 | 日が昇る、日が沈む |
| 季節の把握 | カレンダーで春夏秋冬を確認 | 木の芽や虫の声、風のにおいで感じとる |
| 行動の決定 | 時計やスケジュール | 体調や天気、月の形などで判断 |
時計やカレンダーがないぶん、人びとは空や山や動物の様子にとても敏感でした。
太陽の高さ、鳥のさえずり、風の強さ。そうした自然の“サイン”が、「いま何時?」「いつ動く?」の合図だったのです。
現代人は、スマホがないと落ち着かないかもしれませんが、縄文人はスマホがあっても「風の音の方が正確だよ」と思ったかもしれません。
自然の中で暮らしていたからこそ、体の感覚や自然とのつながりが、時間そのものだったのです。

ミミー
じかんって、すこし ふしぎな言葉ダワ…
ふれても つかめないのに、いつも わたしたちの そばにいるの。
縄文時代:太陽と月と風が、時計だった
縄文時代(およそ1万5千年前〜2,300年前)は、文字も数字もない時代です。もちろん「〇時に集合」なんて言い方もありませんでした。
では、縄文人はどうやって一日の流れや季節の移り変わりを感じ取っていたのでしょうか?
一日の中の時間感覚
基本は、太陽の位置です。
- 朝日は「目覚めの合図」
- 日が真上にくると「お昼ごはんの頃」
- 太陽が傾きはじめると「そろそろ家に帰る時間」
- 日が沈むと「眠る準備」
時間を“見る”のではなく、肌で“感じる”暮らし方。
火を焚いて明かりをとれるとはいえ、夜は暗く、行動範囲も限られていたため、自然と昼中心の生活になりました。
季節のリズムをどう知った?
「今日は春分の日です」なんて教えてくれるニュースもない時代、季節のうつろいも自然のサインで受け取ります。
- 川辺でカエルの声がしたら春
- セミが鳴いたら夏
- 木の葉が赤くなれば秋
- 動物たちが姿を隠せば冬の気配
さらに、月の満ち欠けも重要なヒントでした。
新月から満月までの約15日間というサイクルを使って、狩りや採集のタイミングを計っていたとも考えられています。
自分の体が“時計”だった?
「今日は体が重いから、まだ動く時間じゃないかも」
「今日は風が冷たいから、魚は川にいないかも」
こんなふうに、自分の体や自然界の変化をとても細かく感じ取って、暮らしのリズムを整えていた可能性があります。
つまり、自然の時計に合わせて暮らすことが、体と心にとっても自然だったのです。

ミミー
火のゆらめきと、木の葉のゆれで じかんを感じるなんて…
縄文のくらしは、まるで うたのようだったのダワ…
弥生時代:時間に“計画性”が生まれた
弥生時代(約2,300年前〜1,700年前)は、稲作の本格的な広がりとともに、時間に対する意識が大きく変化した時代です。
自然の流れを感じ取るだけでなく、「いつ」「どこで」「何をするか」を前もって考えることが、暮らしの中で必要になってきたのです。
稲作には“時間の読み”が必要だった
お米を育てるには、こうした段取りが必要です。
- 種もみをまく(春)
- 苗を育てる
- 田んぼに植える
- 雑草をとる
- 害虫を防ぐ
- 刈り取る(秋)
- 乾かす・貯める
この工程をこなすには、「この作業は〇月くらいに」「この作業は天気が崩れる前に」といった、先を読む力が求められます。
つまり弥生時代には、自然まかせの暮らしから、自然を相手に“戦略”を立てるような生活へとシフトしていったのです。
太陽や星を“道具”にしていた?
太陽の高さや昇る位置、星の動きも、農作業の目安として使われていたと考えられています。
例えば、北斗七星やオリオン座などは季節によって見える位置が変わるため、それを目印にして田植えや収穫のタイミングをはかっていた可能性もあります。
暮らしに“スケジュール”が生まれた
この時代の人々は、少しずつ「農業カレンダー」のような時間感覚を持つようになります。
- 春は準備
- 夏は管理
- 秋は収穫
- 冬は保存と祭り
このように、1年の中に役割やリズムがはっきりと生まれたことで、暮らしが「自然の流れ」と「人の計画」のあいだでバランスをとるようになっていきました。

ミミー
田んぼとともに、生きる時間を数えていったのね。
空をみあげて、ことしの風を よむ人たちの まなざしが見えるダワ…
古墳時代:社会の“秩序”が時間をつくった
古墳時代(約1,700年前〜1,300年前)は、豪族と呼ばれる支配層が現れ、身分や役割の分化が進んだ時代です。
この時代になると、「時間」は自然のリズムだけでなく、「人の都合」や「社会の都合」に合わせて動くようになっていきました。
みんなが同じ動きをする、ということ
弥生時代までは、集落単位で生活していたため、それぞれの地域が独自に農作業をしていたと考えられます。
ところが古墳時代になると、地域の統合が進み、より大きな集団で動くことが増えました。
たとえば:
- ある日にみんなで田植えをする
- お祭りの日を決めて村中で祝う
- 王や豪族の死を悼む儀式の日がある
このように「特定の日に、特定の人が、特定のことをする」という予定=スケジュールが社会の中で重要になります。
大きな建造物には“段取り”が必要
古墳(お墓)はとても大きな土の建造物です。
大勢の人が協力して、数か月〜年単位で土を盛ったり、石を運んだりしていました。
つまり、プロジェクト型の作業が始まったということです。
- いつ始めるか
- どこから手をつけるか
- だれが、いつ、どこで動くのか
こんな「時間割」的な発想が必要だったのです。
これこそが、「時間を人が設計する」時代の始まりだったのかもしれません。
暮らしの中にも“制度”としての時間
このころには「年」や「月」の概念がより確かなものになっていたと考えられます。
渡来人(朝鮮半島からの移住者)によって、暦や季節の知識も伝わったことが影響しているかもしれません。

ミミー
ひとびとが きそいあい、大きな時をつくっていったのね。
それは うつくしくも ちょっぴり さみしいことだったのかも、ダワ…
古代日本人の時間感覚まとめと、私たちへのヒント
縄文から古墳時代までの時間感覚をふり返ってみると、それぞれの時代で「時間のとらえ方」が少しずつ変化していたことが見えてきました。
| 時代 | 主な時間感覚 | その特徴 |
|---|---|---|
| 縄文時代 | 自然とともに生きる「循環」 | 太陽の高さや風のにおい、虫の声など、感覚に寄り添った暮らし |
| 弥生時代 | 作物を育てる「予測と管理」 | 農業に合わせた計画性のある生活 |
| 古墳時代 | 社会の都合に合わせた「秩序」 | 暮らしが他者と結びつき、決まった日取りで動く暮らし |
どの時代にも共通していたのは、「自然の流れを感じながらも、少しずつ人の手で時間をデザインしてきた」ということです。
私たちは今、どんな時間に生きている?
現代の生活では、スマートフォンやカレンダーアプリが手放せません。
1日24時間が“秒単位”で刻まれて、5分遅れるだけで謝ることもあるような社会です。
でも、それが本当に「自分に合った時間の使い方」なのでしょうか?
古代日本人のように、風の変化や季節のにおいを感じながら、「自分の体が欲している時間」で動くことは、今でもできるかもしれません。
たとえばこんなことから始めてみるのはどうでしょう
- 天気にあわせてスケジュールを柔軟に変えてみる
- 毎朝、同じ時間に空を見上げてみる
- カレンダーではなく「自分のリズム」で決める一日をつくってみる
「時間を守る」ことばかりに気を取られるのではなく、
「自分の時間に戻る」ことが、現代人にとって必要な感覚かもしれません。

ミミー
きのうと、きょうと、あしたが つながってる…
そんなやわらかい じかんの中で、いきていきたいダワ…