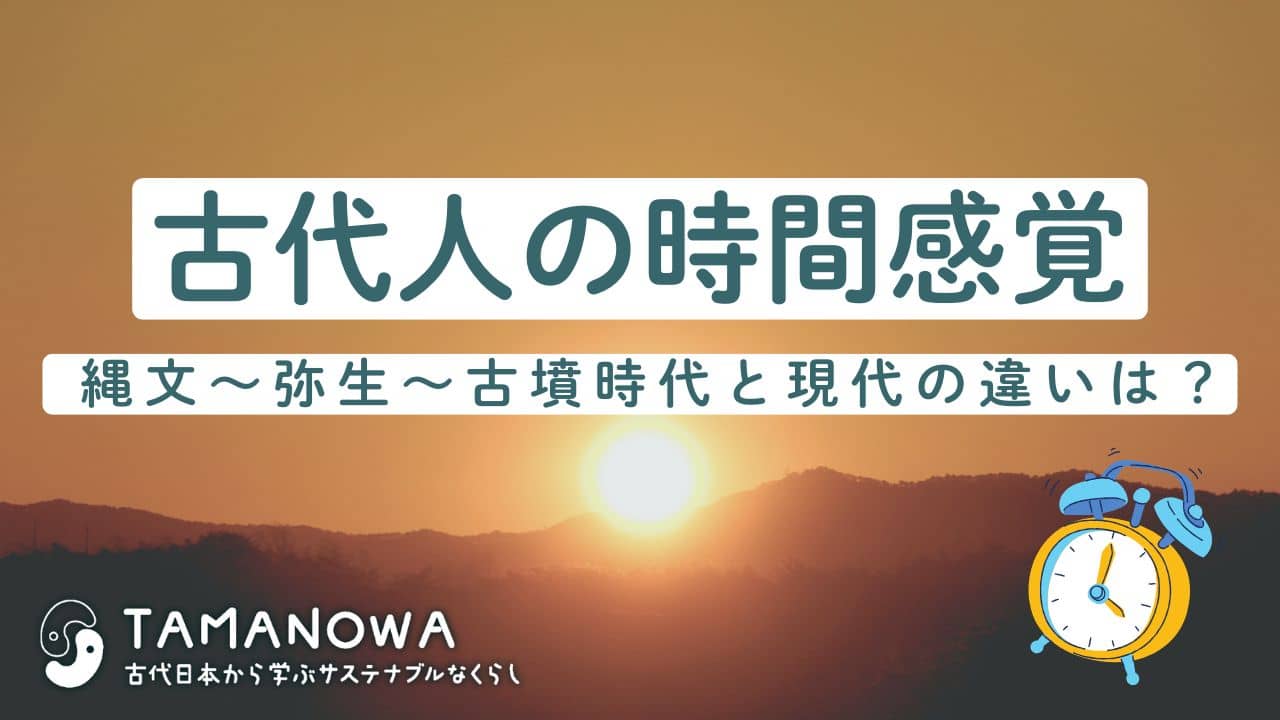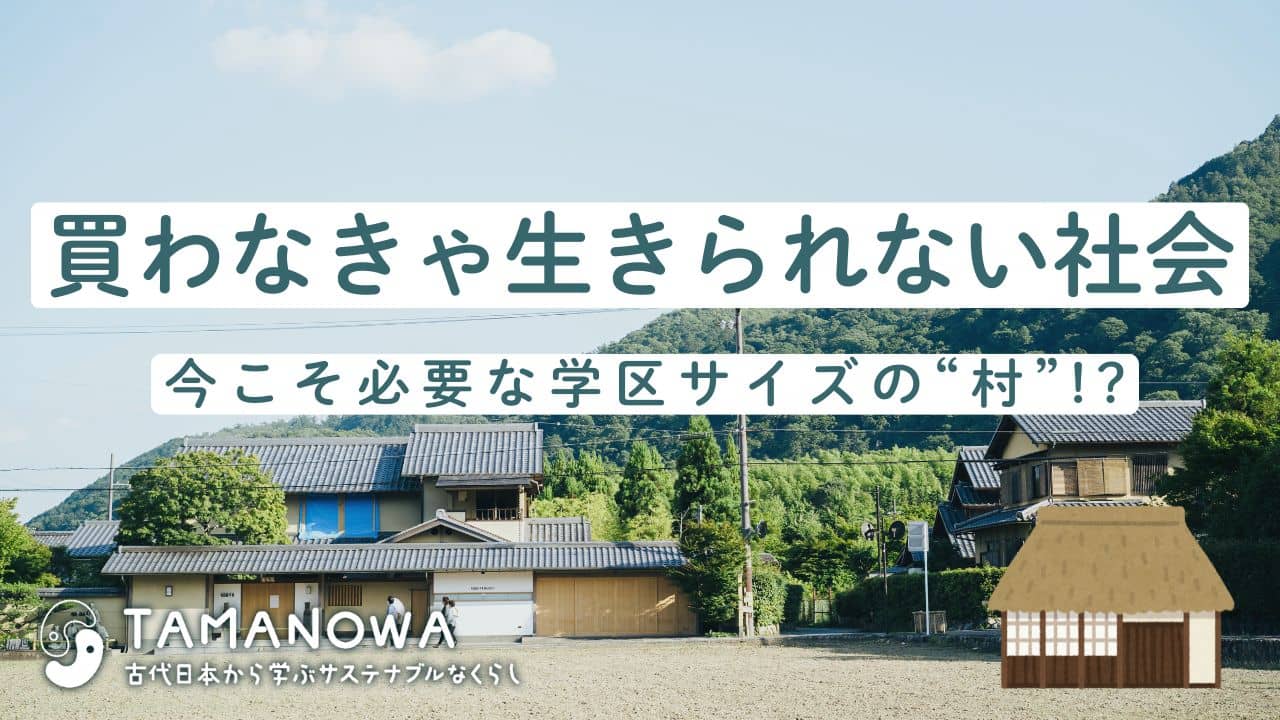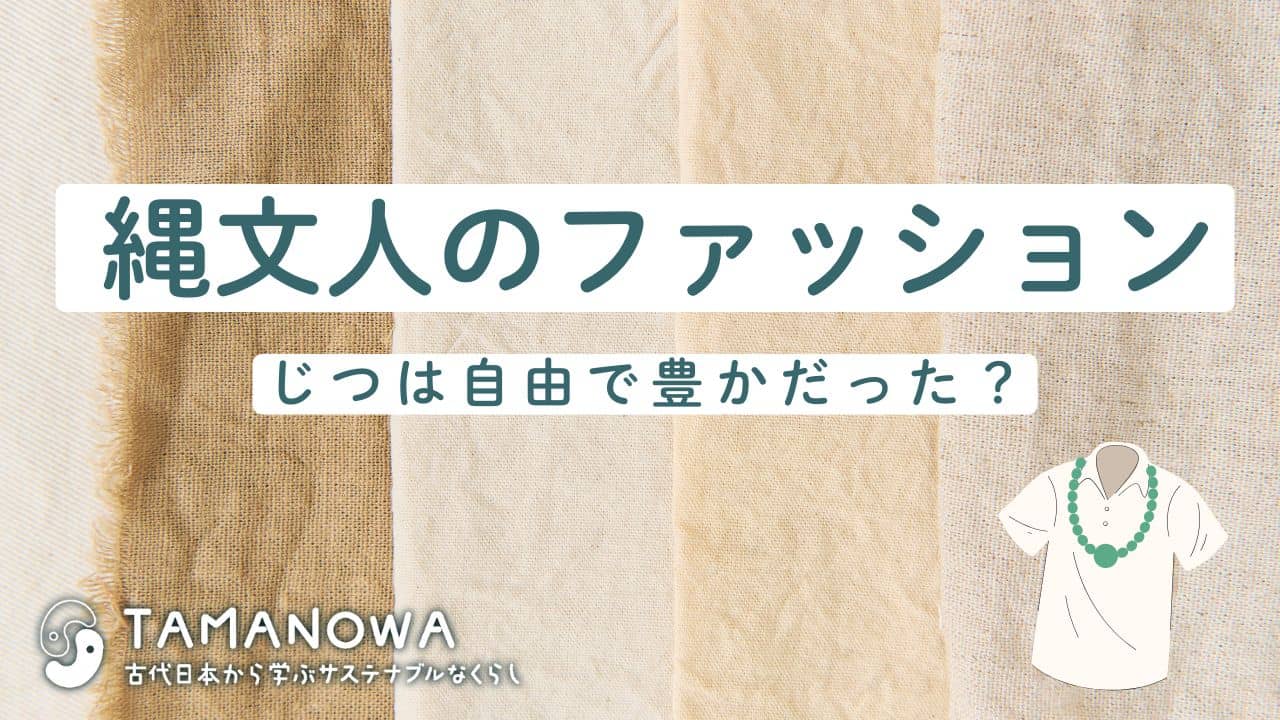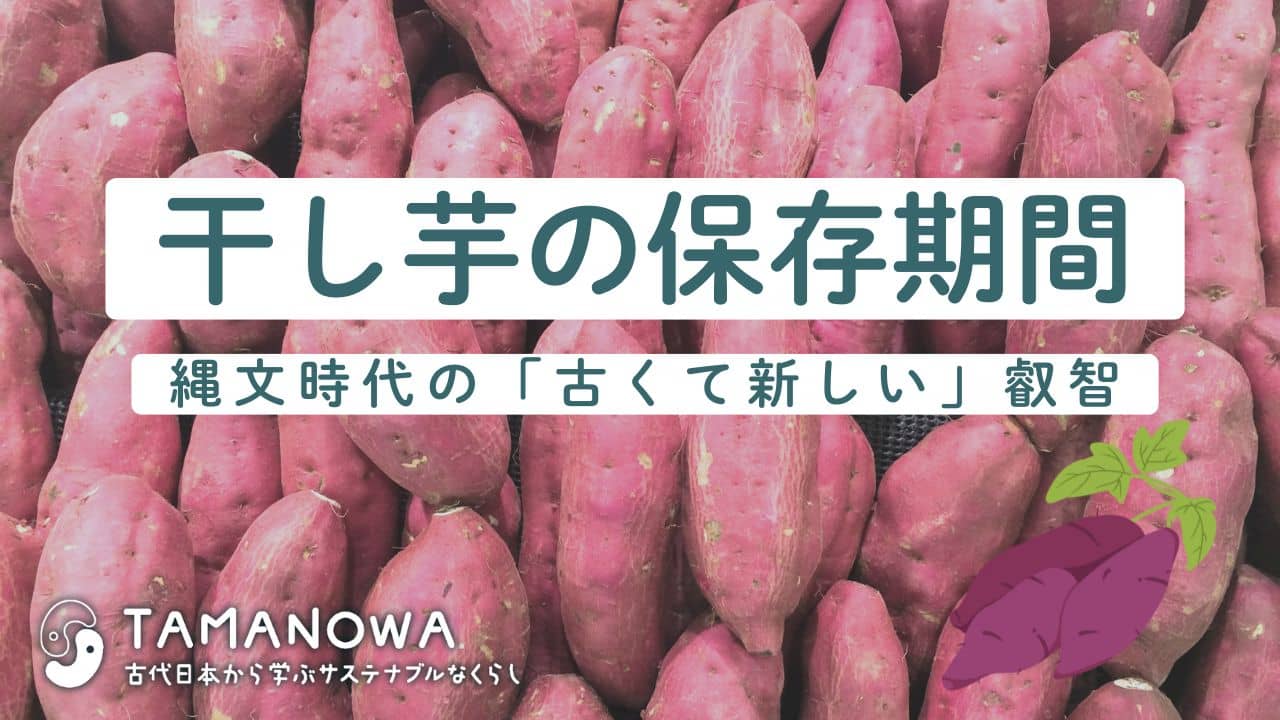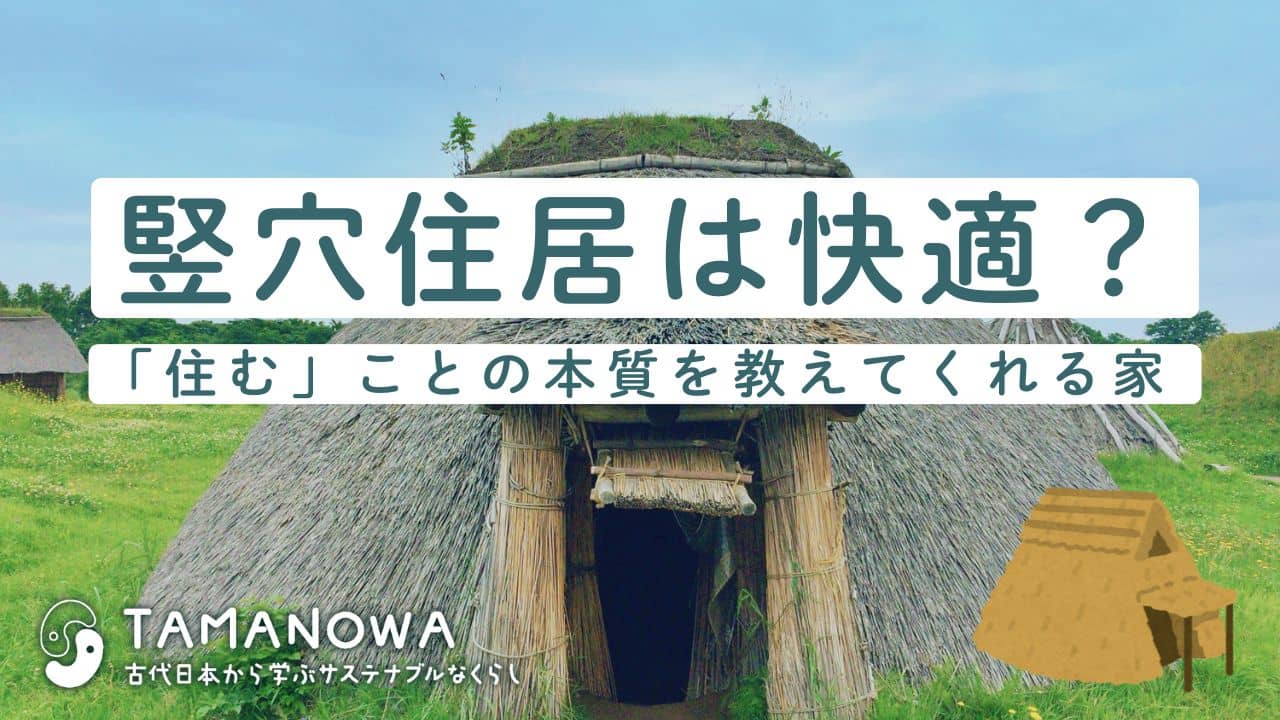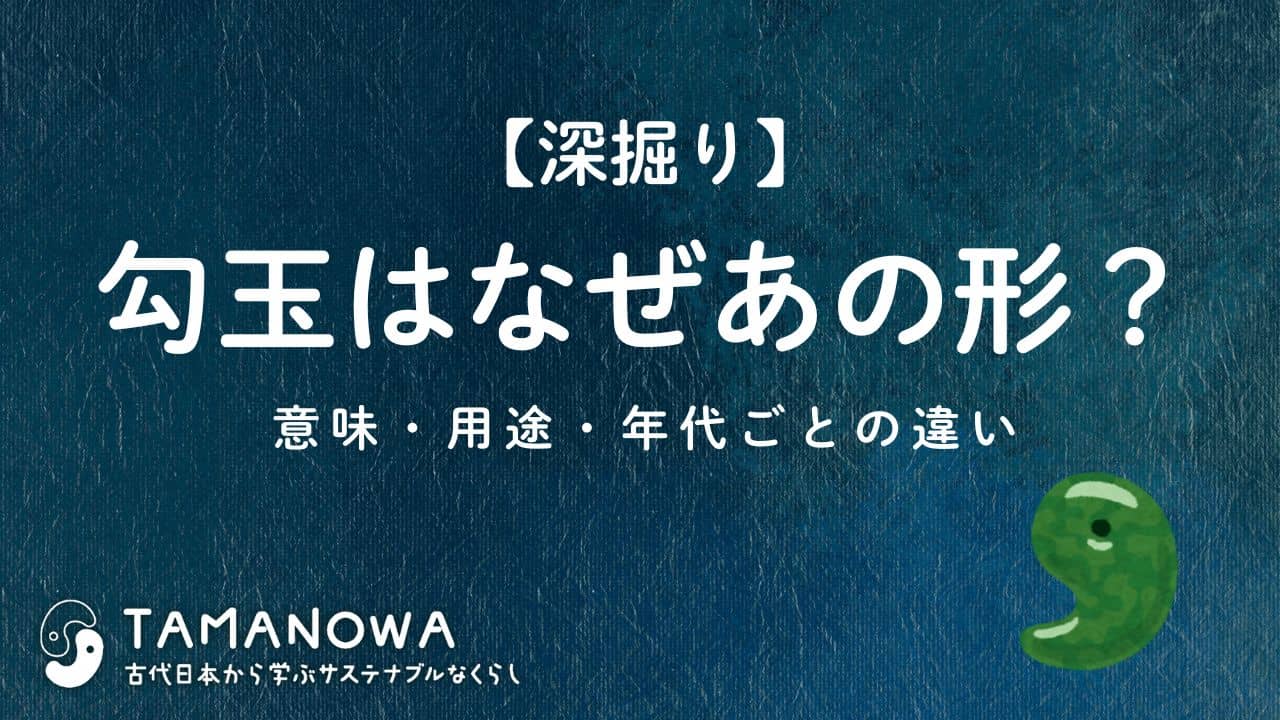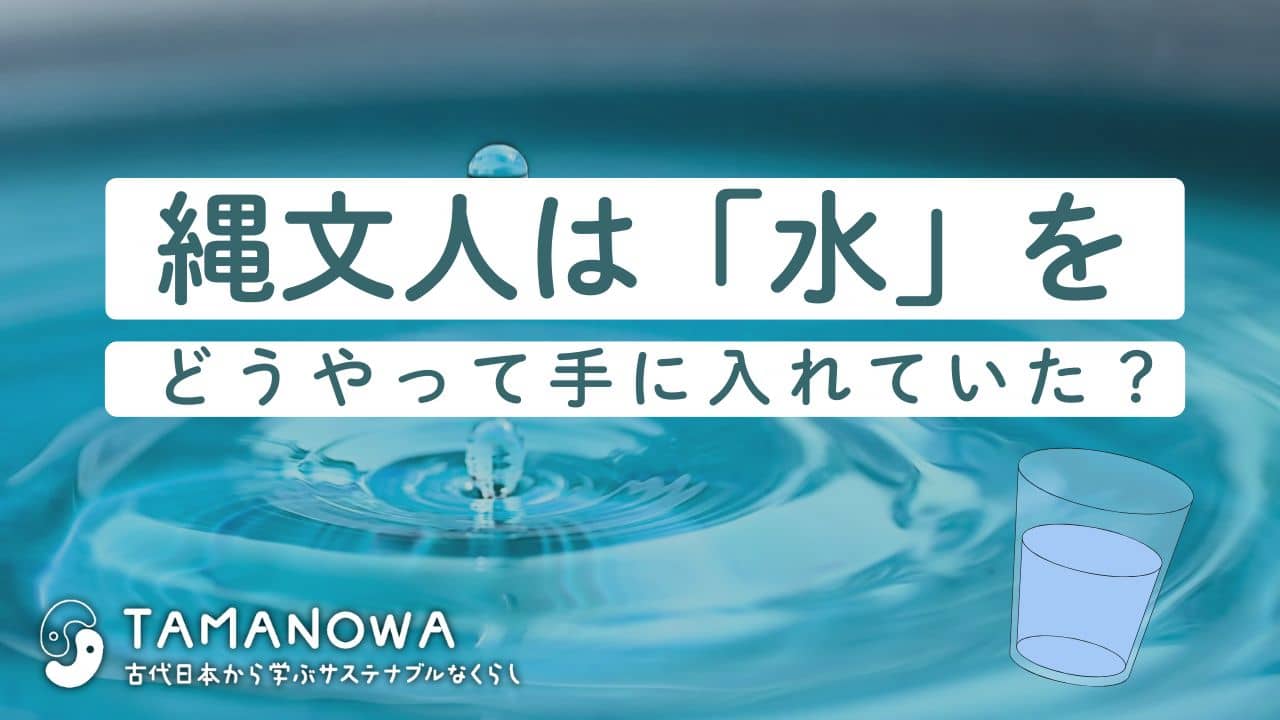はじめに:「サステナブル素材」という言葉の誤解と現実
「サステナブルな服」と聞いて、どんな素材を思い浮かべるでしょうか。
オーガニックコットン、リサイクルポリエステル、テンセル、ヘンプ…。世の中には“環境にやさしい”とされる繊維が数多くあります。
しかし本当に、それらは“やさしい”のでしょうか?
たとえば、
・再生素材の衣類がリサイクルされずに焼却されていること
・オーガニックなのに大量の水を使っていること
・天然素材が生産効率の悪さから過剰な土地や人手を消費していること
こうした事実は、意外と知られていません。
このコラムでは、そうした「サステナブル素材」への思い込みを一度リセットし、**素材ごとに本当に環境や暮らしにとって良い選択なのか?**を多角的に検証します。
評価基準:5つの軸で生地を見つめ直す
各素材は、以下の5つの視点で評価し、読みやすいよう「◎(非常に良い)」~「×(課題あり)」の4段階で比較しています。評価は主観ではなく、現時点での国際的な情報や消費者の使用感をベースにしています。
1. 仕入れコスト
その素材がどれだけ高価か。特に少量生産ブランドにとっては大きなハードルになる部分。国産での安定供給があるかも含めて評価。
2. 環境負荷
栽培や製造における水・農薬・エネルギー使用、温室効果ガスの排出、生分解性、森林破壊の有無、マイクロプラスチック排出など、多面的に評価。
3. 着心地(リアルな使用感)
消費者目線での実感を重視。チクチク感、通気性、保温性、伸縮性、蒸れやすさ、夏冬での快適さなど、実用上の肌ざわりを基準に評価。
4. 耐久性
摩耗や洗濯による劣化、型崩れ、毛羽立ち、伸びやすさなど。長く着られることはサステナブルに直結するため、重要な要素。
5. 現代における利便性
アイロン不要か、乾きやすいか、乾燥機対応か、洗濯が簡単かなど。毎日使う上での「面倒くささ」が少ないことを重視。
比較表:14素材 × 5評価軸の一覧
| 素材 | 仕入れコスト | 環境負荷 | 着心地 | 耐久性 | 現代における利便性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常コットン(綿) | ◎ | × | ○ | △ | ○ |
| オーガニックコットン | × | ○ | ○ | △ | ○ |
| リネン(麻) | ○ | ◎ | △ (パリパリ・カスあり) | ○ | △ (しわ・縮みやすい) |
| ヘンプ(大麻) | △ | ◎ | △ (ざらつき・クセあり) | ◎ | △ (扱いが難しい) |
| レーヨン(ビスコース) | ○ | △ | ◎ (光沢・柔らかい) | × | × |
| リヨセル(テンセル) | △ | ○ | ◎ (シルク風) | ○ | △ (繊細で慎重さ必要) |
| トリアセテート | ○ | △ | ◎ (さらっと高級感あり) | ○ | ◎ (現代的) |
| ウール | △ | ○ | △ (チクチクする場合あり) | ◎ | △ (洗濯に注意) |
| シルク | × | △ | ◎ (滑らか・高級) | △ | × (非常に繊細) |
| ポリエステル(バージン) | ◎ | × | △ (通気性に課題も改善中) | ◎ | ◎ (シワ・乾燥に強い) |
| 再生ポリエステル(rPETなど) | ○ | △ | △ (バージンとほぼ同等) | ○ | ◎ (機能的) |
| アクリル | ◎ | × | △ (蒸れる・毛玉) | ○ | ○ |
| ポリウレタン(スパンデックス) | ○ | × | ○ (ストレッチ性抜群) | × | ◎ (快適・機能的) |
| ナイロン | ○ | △ | ○ (滑らか・軽い) | ◎ | ◎ (耐久性・利便性高) |
通常コットン(綿)
快適さと低価格。その裏に隠れた大きな代償
● 世界で最も使われている天然繊維
通常コットンは、農薬・化学肥料を使用して栽培された、最も一般的な綿花から作られる繊維です。
衣服、寝具、タオル、日用品など、生活のあらゆる場面で使われており、“綿=コットン”というイメージを作った素材でもあります。
最大の魅力は次の2点:
- 柔らかく快適な肌触り
- 価格が安く、供給が安定している
まさに「コストと品質のバランスが良い素材」として、世界中で広く普及しています。
● 着心地:万人向けの快適素材だが…
通常コットンは、着心地の良さでは今もトップクラスの天然繊維です。
- 空気を含みやすく、ふんわり柔らかな肌ざわり
- 静電気が起きにくく、敏感肌でも着やすい
- 吸湿性が高く、汗を吸い、蒸れにくい
一方で、乾きが遅く、重くなりやすいという弱点も。
特に梅雨や夏場の高湿度の時期には、着心地の快適さが逆にべたつきの原因になることもあります。
● 実は最も環境負荷が大きい天然素材のひとつ
コットンは天然素材であるがゆえに「エコなイメージ」を持たれがちですが、実際には環境負荷が非常に大きいことで知られています。
【環境への影響】
- 世界の農地面積の約2.5%を占めるが、農薬使用量は全体の16%を超える(出典:PAN UK)
- 大量の水を必要とし、1着のTシャツで2,700L以上の水を消費する
- 過剰な灌漑により、ウズベキスタンではアラル海が干上がるという実害も発生
- 単一栽培(モノカルチャー)により、土壌の疲弊や生態系の破壊も起きている
天然であることと環境にやさしいことは、必ずしもイコールではないという典型例です。
● 耐久性と扱いやすさ:悪くはないが、過信は禁物
【耐久性】
- 繊維が細く、洗濯を重ねると毛羽立ちやすい
- 色落ちや型崩れも比較的起きやすく、ヘビーユースにはやや不向き
- ただし、製品の厚みや編み方で耐久性に差が出やすいため、高品質な綿製品は長く使える
【現代における利便性】
- 洗濯・乾燥は可能だが、乾きにくくシワが出やすい
- 乾燥機使用で縮むことがあり、アイロンが必要なケースも多い
- 夏場は快適だが、冬は冷えやすく保温性は低め
「日常的に使えるが、長持ちや時短には不向き」というのが現代的な評価です。
● コストの裏にある倫理的な問題
綿花栽培が盛んなインド、ウズベキスタン、中国などでは、児童労働や強制労働の報告も少なくありません。
また、低価格で流通させるために、中間業者や小規模農家が搾取される構造が温存されているケースもあります。
「安い」ということの裏には、誰かの犠牲があるかもしれないという視点も持ちたいところです。
● まとめ:通常コットンの評価ポイント
| 評価軸 | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | ◎ | 世界中で生産されており、価格も安定。小ロットでも仕入れやすい |
| 環境負荷 | × | 農薬・水の大量使用、土地・労働問題など、負荷は天然素材で最上位 |
| 着心地 | ◎ | 柔らかく吸湿性も高く、着心地は最も安定。だがベタつきやすい場面もあり |
| 耐久性 | ○ | 毛羽立ちやすく色落ちもあるが、厚手や高密度なら長持ちも可能 |
| 現代における利便性 | △ | シワ・縮み・乾きにくさなど、時短や省エネにはやや不向き |
※それぞれの評価の根拠は、次章以降で詳しく解説していきます。
オーガニックコットン
「安心」の裏側にある、水とコストの話
● 化学薬品を使わない“やさしい綿”
オーガニックコットンは、遺伝子組み換えをしていない綿花を、農薬や化学肥料を使わずに育てたものです。
地球環境にも、そこで働く人にもやさしいというイメージから、エシカルファッションやベビー用品などに多く使われています。
環境面でのメリットとしては:
- 土壌の生物多様性や微生物バランスが守られる
- 農薬による周辺住民や労働者への健康被害を軽減できる
- 化学肥料を使わないことで土壌の劣化や水系の汚染を防ぎやすい
「持続可能な農業」のモデルとして、世界中で取り組みが進んでいる素材です。
● 着心地:柔らかいが、そこまで違う?
オーガニックコットンは、通常のコットンと比べて格段に柔らかいという印象を持たれがちです。
しかし実際のところ、製品として仕上げられた段階での肌触りの違いはそれほど大きくないこともあります。
- 肌あたりは柔らかく、静電気も起きにくい
- 特にベビー用品や敏感肌向け製品では安心感が高い
- ただし、糸の太さや織り方による違いの方が着心地に与える影響は大きいことも
つまり、オーガニックかどうかより、製品としてどう仕上げられているかが着心地に直結するといえるでしょう。
● 見過ごされがちな環境負荷とコスト
オーガニックコットンは「農薬を使わないから環境にやさしい」と言われますが、水の使用量に関しては決して少なくありません。
- 綿花はもともと水を大量に消費する作物(1着のTシャツで約2,700L)
- 有機栽培により収穫効率が下がると、単位収穫あたりの環境負荷は逆に高まることもある
- 病害虫対策が難しく、収穫量が安定しづらい
さらに、認証(例:GOTS)を得るには監査・管理コストもかかるため、販売価格も自然と高くなる傾向があります。
● 現代における利便性:扱いやすさは普通のコットンと同じ
オーガニックコットンは、素材としての性質は通常のコットンとほぼ同じです。
- 洗濯可能で乾きやすく、日常使いには向いている
- ただし、シワがつきやすく、乾燥機や高温乾燥で縮むリスクがある
- 速乾性や防臭性は低めで、汗ばむ時期はややベタつきやすい
「やさしいけれど、管理には少し気を使う」素材だといえます。
● まとめ:オーガニックコットンの評価ポイント
| 評価軸 | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | △ | 認証コスト・収穫効率の低さにより、通常綿より価格が高め |
| 環境負荷 | ○ | 農薬不使用だが、水の使用量や生産効率の低さが課題 |
| 着心地 | ◎ | 柔らかく安心感はあるが、通常綿との差は製品加工によることも多い |
| 耐久性 | ○ | 通常綿と同程度。品質の個体差はあるが、日常使いには十分 |
| 現代における利便性 | △ | 洗えるが、シワや縮みには注意。乾燥機非推奨で管理に少し手間がかかる |
リネン(麻)
涼しいだけじゃない、“麻”の本当のポテンシャルと扱いにくさ
● 夏の定番“麻”は、実はかなり昔からサステナ素材
リネンは、フラックス(亜麻)という植物の茎から採れる天然繊維で、人類最古の織物素材の一つとも言われています。
その歴史はなんと紀元前8,000年まで遡るとされ、古代エジプトでもミイラの包帯に使われていたほど。
- 吸水性と通気性に非常に優れ、夏でも快適に過ごせる
- 少ない水で育ち、農薬もほとんど不要。環境負荷がきわめて小さい
- 使い込むほど柔らかく風合いが出てくる、“育てる布”の代表
現代においても、ナチュラルなライフスタイルやミニマリズムと親和性の高い素材です。
● 着心地:ひんやり快適、でも“パリパリ&カス”に注意
リネンはシャリ感と通気性が魅力ですが、実際に着てみると意外な注意点があります。
- 【プラス面】
・涼しく、風を通しやすい
・汗をかいてもベタつきにくい
・着込むほどにやわらかくなる変化が楽しい - 【マイナス面】
・繊維が太いため、最初はゴワゴワ・パリパリした着心地がある
・肌が弱い人には刺激を感じる場合もある
・摩擦により細かな繊維くず(カス)が肌や下着に付着することがある
・天然色のままではシミが目立ちやすい
特に安価なリネン製品は加工が不十分でチクチク・カスが出やすいため、実用面での好みが分かれやすい素材でもあります。
● 環境面ではかなりの“優等生”
【農薬・水・肥料の消費が少ない】
- フラックスは痩せた土地でも育ち、農薬や肥料の使用量が少ない
- 綿のように大量の灌漑用水を必要としないため、水ストレスが少ない
- 栽培から製造までのCO₂排出も比較的少ない
【生分解性◎、焼却時にも有毒ガスなし】
- 完全に天然由来のため、土に還る素材として優れている
- 焼却しても有害なガスを出さない
現時点では、素材単体としてはトップレベルにサステナブルといってよい素材です。
● 耐久性と利便性:強いが、しわ・縮み・手入れは要注意
【耐久性】
- 水に濡れると繊維が強くなるという特性があり、洗濯に強い素材
- ただし、繰り返しの摩擦にはやや弱く、部分的に毛羽立ちやすい
【現代における利便性】
- シワになりやすく、ノーアイロン派には扱いづらい
- 洗濯後に縮みやすく、サイズ選びや乾燥に注意が必要
- 乾燥機は基本NG(縮む可能性が高いため)
- 最近ではしわ加工・ソフト加工されたリネンも増えており、少しずつ改善傾向にある
● まとめ:リネンの評価ポイント
| 評価軸 | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | △ | 高級素材ではないが、加工品質で価格に幅あり |
| 環境負荷 | ◎ | 水も農薬も少なくて済み、生分解も可能。非常に優れた環境性能 |
| 着心地 | △〜○ | 風通しは良いが、最初はごわつきやカスが気になることも |
| 耐久性 | ○ | 水に強く長持ち。ただし摩擦・毛羽立ち・縮みに注意 |
| 現代における利便性 | △ | しわと縮み、カスへの配慮が必要。丁寧に扱える人向け |
ヘンプ(大麻)
“地球にやさしい”の本命。だけど着るにはまだ壁がある
● 栽培面では最高のサステナブル素材
ヘンプは、大麻草の茎からとれる植物繊維で、古代から衣服・縄・紙などに使われてきた歴史ある素材です。
そのサステナビリティは、ほかの天然繊維と比較しても圧倒的です。
- 農薬や化学肥料がほとんど不要
- 生育が非常に早く、60〜90日で収穫可能
- 乾燥地でも育ち、水の使用量はコットンの10分の1以下
- 土を深く耕す根を持ち、土壌改良や炭素固定効果もある
気候変動対策、土地の再生、無農薬農業——どの観点から見ても“優等生”の素材です。
● 着心地:肌ざわりにクセがあり、好みが分かれる
ヘンプは「ザラザラして硬い」といわれがちですが、製品によって差が大きい素材でもあります。
- 未加工のヘンプはごわつきがあり、チクチク感を感じる人も多い
- ただし、洗うたびに柔らかくなるため、長く使うことで快適になっていく
- ヘンプ100%はやや硬めでも、コットンやテンセルとの混紡品は着心地が大きく改善されている
特に、肌に直接触れるインナーや夏服には向きにくい一方で、丈夫で風通しがよく、炎天下の作業着などには最適ともいえます。
● 法規制・流通・誤解という三重苦
【国内での商業栽培がほぼ不可能】
日本では、大麻草の栽培には大麻取締法による厳格な許可制度があり、産業用ヘンプであっても事実上ほぼ禁止状態です。
そのため、原料は中国・ルーマニア・カナダなどからの輸入に依存しています。
【消費者の“勘違い”によるマーケティング障壁】
「大麻=薬物」という強いイメージが根強く、商品の売り方によっては拒否反応を示されることもあります。
ヘンプ=サステナブルと理解されるには、まだ時間と教育が必要です。
【加工難易度と価格】
ヘンプは繊維が太く硬いため、柔らかく仕上げるには高度な加工技術が必要です。
結果として、コストが高くなりがちで、大量生産には不向きという一面があります。
● 耐久性と利便性:最強クラスの頑丈さ。ただし管理は人を選ぶ
【耐久性】
- 摩耗や引き裂きに非常に強く、長年の使用に耐える
- 汚れも落ちやすく、アウトドアや作業服向きの素材
【現代における利便性】
- 速乾性・通気性には優れるが、シワになりやすくアイロンが必要
- 初期は硬く、柔らかくなるまでやや時間がかかる
- 一部の製品は乾燥機NG。縮みやすい加工もある
特に手間のかかる素材ではないものの、化繊ほどの手軽さはないのが正直なところです。
● まとめ:ヘンプの評価ポイント
| 評価軸 | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | ○ | 輸入頼みでやや高価。加工や混紡によってコストに幅あり |
| 環境負荷 | ◎ | 農薬・水不要、土壌改良・炭素吸収にも優れた、栽培面で最も優等生の素材 |
| 着心地 | △ | 硬めでチクチク感があるが、混紡や長期使用で改善されることが多い |
| 耐久性 | ◎ | 摩耗や汚れに強く、長寿命。タフでラフに使える素材 |
| 現代における利便性 | △ | シワ・縮みやすさや誤解・法規制がある。手間や印象面で障壁が残る |
レーヨン(ビスコース)
● 植物由来の「再生繊維」、だけど意外とエコじゃない?
レーヨン(ビスコース)は木材パルプから作られる再生セルロース繊維。天然素材のような見た目と肌ざわりから、コットンやシルクの代替として重宝されてきました。しかし、その製造過程は化学薬品の大量使用と水質汚染の問題を含み、サステナブルな素材と呼ぶには一筋縄ではいきません。
製造工程では苛性ソーダや二硫化炭素といった有害な化学物質を使うため、環境や作業者の健康に深刻な影響を及ぼすことが知られています。特に規制の緩い国での生産では、公害レベルの問題となっている例もあります。
● 着心地:やわらかく、光沢もあり、快適
レーヨンは、しなやかで肌触りが良く、ドレープ性に優れた素材です。見た目には高級感があり、薄手で軽やか。夏服やドレッシーなアイテムに好まれるのはこのためです。吸湿性もあるため、汗ばむ季節にも快適です。
しかし一方で、水に濡れると極端に弱くなるという欠点があります。濡れた状態での洗濯や摩擦に弱いため、取り扱いには注意が必要です。
● 耐久性と利便性:繊細で扱いづらい
繊維が水に弱く、縮みやすく、シワにもなりやすい点から、自宅での洗濯や乾燥には不向きです。多くの場合、手洗いや陰干しが推奨されるため、日常使いの衣類としてはやや手間がかかります。
また、レーヨンは摩擦により毛羽立ちやすく、劣化も早めです。頻繁に着る衣類よりも、イベント用やオケージョン服に向いています。
● サステナブルと呼ぶにはまだ早い?
「木材由来=エコ」といった単純な連想でサステナブル素材と紹介されることもありますが、前述のように製造時の化学負荷は重く、森林伐採の問題も懸念材料です。特に、熱帯林などを原料にするケースでは、CO₂吸収源の減少にもつながります。
同じセルロース系でも、クローズドループ製法を採用するリヨセルとは決定的に異なり、オープンループで廃液を流すことが多いという問題があります。これにより「植物由来でも、全然エコではない」という評価になるのです。
● まとめ:レーヨンの評価ポイント
| 項目 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | ○ | 安価で大量生産可能。大量消費型ファッションに多用 |
| 環境負荷 | × | 化学薬品使用と水質汚染のリスクが高い |
| 着心地 | ◎ | しなやかで高級感があり、吸湿性も高い |
| 耐久性 | △ | 水に弱く、劣化も早い |
| 現代における利便性 | △ | 洗濯や乾燥に注意が必要で、ラフには扱えない |
リヨセル(テンセル)
“完璧”に近いサステナブル素材? でも弱点もある
● 再生繊維の理想形に最も近い存在
リヨセルは、ユーカリやブナなどの木材を溶かして繊維化した再生セルロース繊維です。
特にオーストリアのレンチング社が展開する「テンセル(TENCEL™)」というブランド名で知られ、再生繊維の中でも特に環境負荷が低い素材として注目されています。
その理由は以下のような製造プロセスにあります:
- 非有害な溶剤(NMMO)を使用し、99%以上を再利用する「クローズドループ製法」
- 原料となる木材はFSC認証(持続可能な森林管理)を受けた植林地から供給
- 生分解性があり、自然環境で分解される
素材そのものも通気性・吸湿性・手触りの良さに優れ、サステナブルと快適さを両立した希少な素材とされています。
● 着心地:まるでシルクのよう。だけど意外な落とし穴も
リヨセルの肌ざわりは、シルクに匹敵するほどなめらかで、ドレープ性(布の落ち感)も美しく、高級感があります。
- ひんやりとした接触感と、吸湿・放湿性の高さで夏も快適
- ほどよいストレッチ感があり、インナーにも最適
- 静電気も起きにくく、肌への刺激が非常に少ない
ただし、濡れると繊維が硬くなりやすいため、濡れたままの摩擦で毛羽立ちが起きやすいという特徴もあります。
洗濯ネットや脱水の工夫が求められる場面もあり、実は取り扱いには繊細さが必要な素材です。
● 耐久性と利便性:丁寧に使えば長持ち、でもラフには向かない
【耐久性】
- 摩擦や高温乾燥に弱く、パジャマや寝具など擦れが多い製品では劣化が早まることも
- ただし、着心地を重視した使用(カットソー、ブラウスなど)では十分な寿命を持ちます
【現代における利便性】
- 吸湿性が高く速乾性にも優れるため、乾きやすい
- シワはつきやすいが、自然なドレープがそれを目立ちにくくする
- 乾燥機は基本NG。洗濯にやや気を使う
「化繊のように便利」とは言えませんが、高品質な天然風素材としては十分実用的です。
● 知られざる課題:作れない日本、独占される技術
リヨセルの主原料であるユーカリは、日本の気候では商業的な大規模栽培に向きません。
さらに、製造ノウハウの大半はレンチング社などが特許で保護しており、日本企業による代替製造が難しいのが現実です。
つまり、日本国内で完結したリヨセルの生産は現時点ではほぼ不可能であり、輸入素材に依存せざるを得ない構造になっています。
● まとめ:リヨセルの評価ポイント
| 評価軸 | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | ○ | 輸入頼みで価格はやや高めだが、国内外ブランドでの採用は増加中 |
| 環境負荷 | ◎ | 溶剤回収率99%、植林原料、廃棄時の生分解性も高く、環境負荷は極小 |
| 着心地 | ◎ | シルクのように滑らかで、夏は涼しく冬は蒸れない。摩擦に弱い点に注意 |
| 耐久性 | ○ | 擦れや乾燥機には弱いが、通常の着用では問題なし。ていねいな扱いが前提 |
| 現代における利便性 | ○ | 速乾・シワ軽減などは良好だが、洗濯ケアにやや注意が必要(乾燥機は非推奨) |
トリアセテート
● 化学と自然のハイブリッド? セルロース系の“高機能素材”
トリアセテートは、木材パルプを原料とする半合成繊維です。セルロース系という点ではレーヨンやリヨセルと同じですが、製造工程では酢酸を使ってセルロースを部分的に化学変性させています。このため**「化学繊維寄りの天然由来素材」**という立ち位置になります。
高温や摩擦に強く、シワになりにくいという特徴から、スーツの裏地や高級婦人服などに使われることが多い素材です。着用時の見た目が美しく、手入れもしやすいことから、利便性の高い素材として評価されています。
● 着心地:さらっとしていて、高級感あり
トリアセテートはシルクのような光沢感と、滑らかな肌触りが特徴です。ドレープ性も高く、体のラインに沿って美しく落ちるため、エレガントな印象を与えます。
また、吸湿性と速乾性のバランスが良いため、汗をかいてもベタつきにくく、さらっと快適な着心地です。夏用のブラウスなどに最適です。
ただし、肌が敏感な人にはやや乾いた質感が気になることもあり、好みが分かれる可能性があります。
● 耐久性と利便性:現代生活にフィットする性能
トリアセテートは耐熱性に優れており、家庭用のアイロンや乾燥機にも対応可能。シワになりにくく、型崩れしにくいのも利点です。
また、型崩れしにくいため長く着られる服になりやすく、出張や旅行にも適した素材と言えます。洗濯機で洗える製品も増えてきており、忙しい現代人にとってありがたい素材です。
ただし、摩擦に弱い面もあり、バッグとの擦れや、洗濯ネットを使わない洗濯で毛羽立つことがあります。
● 環境負荷は中程度。だけど循環は難しい
天然由来のセルロースを原料としているものの、合成酢酸などの化学薬品を用いている点では、リヨセルよりも環境負荷は高いとされます。また、製造工程での薬品処理によってリサイクルや土壌分解が難しく、循環型素材としてはやや弱い立ち位置です。
とはいえ、ポリエステルやナイロンなどの石油由来素材と比較すれば、製造時のCO₂排出量は低めであり、バランス型の素材と見ることもできます。
● まとめ:トリアセテートの評価ポイント
| 項目 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | △ | 高級衣料向けのため、価格帯はやや高め |
| 環境負荷 | △ | 半合成素材。石油系よりはマシだが、循環性は乏しい |
| 着心地 | ○ | 滑らかで高級感あり。吸湿性もバランス良く快適 |
| 耐久性 | ○ | 熱・型崩れ・シワに強く、扱いやすい |
| 現代における利便性 | ◎ | 洗濯・乾燥対応でシワにならず、日常使いに最適 |
ウール
天然なのに敬遠される? チクチクと高価格の狭間で揺れる素材
● 動物の恵みを利用した、高機能な天然繊維
ウールは羊の毛を刈り取って加工した動物由来の天然繊維で、何千年も前から人類が使ってきた伝統的な素材です。
とくに寒冷地での防寒着として圧倒的な支持を受けてきました。
- 吸湿性と保温性が非常に高く、冬の素材として理想的
- 繊維に自然な撥水性があり、湿気を外に逃がす通気性もある
- 汗を吸っても冷えにくく、においにくい
機能面ではまさに“万能”。
しかし、現代ではその扱いづらさや価格面から、日常着としての人気はやや低下傾向にあります。
● 着心地:高評価だが“理想と現実”が乖離しやすい
一般的なウールの印象は「高級」「あたたかい」「上品」というものですが、実際に着たときの感想はかなり分かれます。
- 【プラス面】
・温かさと軽さのバランスが絶妙
・肌にフィットしすぎず、空気の層で保温する心地よさ
・ハイゲージ(細かい編み)のメリノウールはとても滑らか - 【マイナス面】
・チクチクするという声が根強い(特に安価なウール)
・「肌に直接は着たくない」という人も多い
・家庭洗濯が難しいという不便さがある
つまり、「ウールは着心地が良い」という評価は品質が高い場合に限られるというのが実情です。
価格と品質、そして手入れの手間のトレードオフを理解することが重要です。
● 環境面では“優等生”の側面が強い
【再生可能な天然素材】
羊の毛は毎年自然に伸びるため、枯渇リスクのない再生可能資源です。
化学処理を抑えた製造工程であれば、生分解性も高く、土に還る素材として評価されています。
【ただし動物福祉・放牧地問題も】
一方で以下のような課題も存在します。
- 畜産(羊)の温室効果ガス排出
- 放牧地の過剰利用による土地劣化(とくにオーストラリア・ニュージーランド)
- ムールシング(皮膚切除)など動物福祉上の懸念
ウールの環境負荷は“製造過程では低いが、畜産由来の構造的課題がある”という複雑な立ち位置にあります。
● 耐久性と利便性:長持ちするが、手入れが難点
【耐久性】
- 正しく扱えば10年以上もつ耐久性がある
- 毛玉ができにくく、型崩れもしづらい
- 虫害に弱いため、保管には注意が必要
【現代における利便性】
- 自宅洗濯が難しく、乾燥機NG・平干し推奨
- 高温に弱く、アイロンも慎重にかける必要あり
- 一方で、防臭性・吸湿性の高さはライフスタイルに合えば強み
高機能な一方、丁寧なケアが求められる素材です。
● まとめ:ウールの評価ポイント
| 評価軸 | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | △〜× | 高級ウールは非常に高価。品質によって大きく差がある |
| 環境負荷 | ○ | 再生可能・生分解性◎。ただし畜産や動物福祉の問題は無視できない |
| 着心地 | △〜◎ | ハイグレード品は極上の着心地。安価品や敏感肌にはチクチクの不満も多い |
| 耐久性 | ◎ | しっかり扱えば長寿命。防虫保管は必須 |
| 現代における利便性 | △ | 洗濯や乾燥に制限あり。ライフスタイルとの相性が問われる |
シルク
● 天然素材の女王。古来より愛された“美と機能”
シルク(絹)はカイコの繭から採取される動物性天然繊維で、古代中国から「絹の道」を通じて世界に広まりました。吸湿性・放湿性・保温性のすべてに優れ、非常に軽くて柔らかく、自然な光沢を持つことから、長らく「高級素材」として君臨してきた存在です。
しかし現代においては、扱いにくさや価格の高さから、一般衣料としてはあまり使われなくなってきています。
● 着心地:肌あたりは最高級。だけどメンテは大変
シルクの着心地は、まさに**“第二の皮膚”**とも言われるほど自然で快適です。吸放湿性に優れ、夏は涼しく、冬は暖かいという理想的な素材です。静電気も起きにくく、肌が敏感な人にも安心です。
ただし、汗や水に非常に弱く、日光や摩擦でも劣化しやすいという性質があります。とくに日焼けや汗じみ、シミなどは一度ついてしまうと元に戻すのが難しく、実用面では非常に繊細な素材です。
● 耐久性と利便性:美しさの裏にある“扱いにくさ”
シルクは非常に細く強度のある繊維ではありますが、実際の衣類としての耐久性はかなり低めです。水に濡れると繊維の強度が落ち、洗濯機不可、アイロンにも注意が必要など、日常使いではかなり神経を使う素材になります。
また、虫食いや黄変(経年による変色)のリスクもあり、保存状態にも気を配る必要があります。メンテナンスコストの高さが、現代生活における最大のネックと言えるでしょう。
● 環境負荷は意外と低くない? 動物性素材の矛盾
シルクは天然素材であり、化学薬品を使用せずに作られることが多いため、一見サステナブルに見えます。しかし、実際にはカイコを大量に育てるための餌(桑の葉)や水、土地、温度管理など、リソース消費が大きく、CO₂排出量もそれなりに高いとされています。
また、繭を茹でてカイコを殺すという工程が避けられないため、動物倫理の面でも意見が分かれます。ビーガン素材とは相容れない側面もあるのです。
● まとめ:シルクの評価ポイント(参考)
| 項目 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | × | 高級素材として非常に高価。大量生産には不向き |
| 環境負荷 | △ | 天然素材だがリソース消費が大きく、動物倫理の課題も |
| 着心地 | ◎ | 柔らかく滑らか、吸湿・放湿・保温性すべて高水準 |
| 耐久性 | △ | 繊細で水・日光・摩擦に弱く、長期使用には不向き |
| 現代における利便性 | × | 手入れが大変すぎて、現代生活では使いづらい |
ポリエステル(バージン)
“環境の敵”とされがち。でもそれ、すべて正しい?
● 世界でもっとも使われている繊維
ポリエステルは、石油を原料とする合成繊維の代表格で、現在市場に流通する衣類のおよそ半数以上に使われている素材です。
速乾性・耐久性・価格の安さという点から、スポーツウェア・制服・カジュアルファッションなど、あらゆるシーンで使用されています。
- 製造コストが安い
- 大量生産・大量供給が可能
- 長持ち・シワになりにくい・縮みにくい
一見すると“便利すぎる素材”ですが、環境負荷の面では多くの批判も受けています。
● 着心地:本当に悪い? それ、誤解もあります
ポリエステルは「蒸れる・チクチクする・安っぽい」といった印象を持たれがちですが、最近の高機能化により、そのイメージは必ずしも当てはまりません。
- 一般的に吸湿性は低く、静電気が起きやすい
- ただし、接触冷感・ストレッチ性・速乾性に優れた加工製品も多く、夏場やスポーツ向けでは快適
- 編み方次第で風通しをよくしたり、通気性を改善したりする技術も進化中
つまり、「着心地が悪い」は一部の話であり、用途に合った設計であれば非常に快適な素材にもなり得ます。
● 環境負荷:石油由来、マイクロプラ、非分解
ポリエステルの環境負荷は、主に次の3点で批判されています:
1. 石油を使って作られている
化石燃料から合成されるため、製造段階で多くのCO₂を排出します。再生可能ではなく、気候変動の一因ともされています。
2. 洗濯時にマイクロプラスチックが出る
細かくちぎれた繊維が洗濯排水を通じて川や海に流れ込み、海洋汚染や生態系への影響が問題視されています。
3. 土に還らない
ポリエステルは生分解しないため、焼却処分されなければ、何十年・何百年も地中に残り続けます。
● 耐久性と利便性:圧倒的に優れている現代的素材
【耐久性】
- 摩耗、紫外線、汗、引っ張り、洗濯などに非常に強い
- 縮まず、型崩れしにくい
- 「すぐ傷む」という概念とはほぼ無縁のタフ素材
【現代における利便性】
- シワになりにくく、アイロン不要
- 乾きが早く、洗濯機&乾燥機対応が基本
- 保管・持ち運びも気楽で、旅行や日常に向いている
つまり「とにかく手がかからない」ことが、世界中で使われている理由そのものなのです。
● ポリエステルを使うという“戦略”
ポリエステルが環境負荷の面で問題を抱えているのは確かです。
しかし、1着を10年使う・何十回も洗っても平気・毎日着回すという前提で考えれば、むしろ寿命の短い天然素材より“持続可能”な側面すらあるのも事実です。
使い捨てのポリエステルは確かに問題ですが、長期使用前提ならポリエステルは無視できない選択肢です。
● まとめ:ポリエステル(バージン)の評価ポイント
| 評価軸 | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | ◎ | 非常に安価で安定供給可能。大量生産品に最適 |
| 環境負荷 | × | 石油依存・マイクロプラスチック・非分解性の三重苦 |
| 着心地 | △ | 吸湿性は低いが、接触冷感や伸縮性・速乾性などで用途次第では快適 |
| 耐久性 | ◎ | 摩耗・洗濯・紫外線に強く、型崩れや縮みも起きにくい |
| 現代における利便性 | ◎ | 洗濯・乾燥・収納が非常にラク。ノーアイロンで日常使いに最適 |
再生ポリエステル(rPETなど)
「ペットボトルから服」はエコか?それとも思考停止か?
● 廃プラから服をつくる時代へ
再生ポリエステル(通称:rPET)は、主に使用済みのペットボトルや廃ポリエステル製品を原料として再加工したポリエステル繊維です。
近年、環境意識の高まりとともに「エコ素材」として急速に普及が進んでおり、ファストファッションから高級ブランドまで幅広く採用されています。
- 廃棄物を原料にすることで資源の循環利用を実現
- バージン(新規)ポリエステルの使用量を削減
- 見た目や耐久性はバージン品とほぼ同等
このように、「リサイクル=サステナブル」という直感的な分かりやすさが消費者の支持を集めています。
● 着心地:ほぼバージンポリエステルと同じ
再生ポリエステルの繊維構造はバージン品と大きくは変わらないため、着心地もほぼ同等です。
- 吸湿性は乏しいが、速乾性や軽さ、ストレッチ性がある
- 夏場には接触冷感タイプの生地もあり、快適性は高い
- ただし、繊維のグレードによってはややゴワつく・毛羽立ちやすい製品もある
再生品だからといって着用に大きなデメリットはなく、機能的な衣服として十分に成立する素材です。
● 環境負荷:実は循環しないリサイクル構造?
再生ポリエステルは確かに「廃プラ→服」というストーリーを持ちますが、そこで終わってしまう=“一方向リサイクル”である点が最大の課題です。
【1回限りのリサイクルが基本】
rPET製の衣類は、再度繊維としてリサイクルされることがほとんどありません。
理由は、繊維が細くなりすぎたり、色や混紡素材が混ざって再加工が困難になるためです。
【ペットボトルの再生利用ルートを奪っている】
本来、ペットボトルは再びペットボトルに戻す方が高品質・高効率。
それが衣料に使われることで、“資源の寿命”をむしろ縮めているという指摘もあります。
【マイクロプラスチック問題は解決しない】
再生であっても構造はポリエステルのまま。
つまり、洗濯時にマイクロプラスチックが流出する性質はまったく変わりません。
● 耐久性と利便性:実用には十分。ただし劣化リスクも
【耐久性】
- 通常のポリエステルと同等の強さがあるが、繊維の劣化で毛羽立ちやすい製品も
- 摩耗や紫外線にはそこそこ強く、日常使いには問題ない
【現代における利便性】
- シワにならず、乾きやすく、アイロン要らず
- 洗濯機・乾燥機対応製品がほとんどで、ライフスタイルに完全に馴染む素材
● 結論:「やらないよりはマシ」だが、万能ではない
再生ポリエステルは、バージンポリエステルよりは確かに「マシ」です。
しかし、“循環型”と呼ぶには不完全であり、繰り返し再生できない限り「中間素材」にすぎないという冷静な視点が求められます。
エコの看板に惹かれて飛びつく前に、素材の「その後」にも目を向けるべきタイミングが来ているのかもしれません。
● まとめ:再生ポリエステルの評価ポイント
| 評価軸 | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | ○ | バージンよりやや高めだが、量産体制が進み手の届く価格に |
| 環境負荷 | △ | 廃棄物利用は◎だが、実質的には一方向リサイクル。マイクロプラ問題も未解決 |
| 着心地 | △ | バージンとほぼ同じだが、若干の硬さや風合いの個体差がある場合も |
| 耐久性 | ○ | 通常使用では問題なし。高耐久だが、品質の安定性にはばらつきあり |
| 現代における利便性 | ◎ | 速乾・ノーアイロン・洗濯乾燥可。日常での手間は最小限 |
アクリル
ウールの代わりに重宝された素材。だが“便利”の代償は重い
● 軽くて暖かく、ウールに似た化学繊維
アクリルは、石油を原料とした合成繊維で、見た目や肌ざわりをウールに似せるように設計された素材です。
フリースやセーター、マフラー、毛布など、“あたたかいのに安い”製品の定番素材となっています。
- ふんわり軽くて保温性が高い
- 発色性が良く、色落ちしにくい
- 価格が安く、大量生産に適している
「チクチクしないウール」として、ウールの代替品として確固たる地位を築いてきた素材です。
● 着心地:ふわふわだけど蒸れやすく、毛玉も出やすい
アクリルの着心地は、ウールよりもやわらかくて軽いと感じる人が多いです。
- 肌触りは滑らかで、チクチク感が少ない
- ただし吸湿性がほぼないため、蒸れやすい・静電気が起きやすい
- 汗をかいたまま着ると不快感があり、冬の室内では暑すぎることも
- 毛玉(ピリング)ができやすく、見た目の劣化が早い
つまり、初期のふんわり感は良いが、長期間快適に使うにはやや難がある素材です。
● 環境負荷:製造も廃棄も“きびしい”素材
アクリルは環境負荷の高い合成繊維のひとつです。
【CO₂排出量が合成繊維中トップクラス】
アクリルの製造過程では石油由来のアクリロニトリルを重合させるため、大量のエネルギーを必要とし、1kgあたりのCO₂排出量が非常に高いとされています。
【マイクロプラスチックの排出も深刻】
アクリルは繊維が短く、洗濯中にマイクロファイバーが剥がれやすい特徴があります。
マイクロプラスチックの主な排出源としても問題視されています。
【生分解性なし・リサイクル困難】
自然界で分解されず、焼却か埋め立てが前提。また、再生利用もしにくく、サーキュラーエコノミーとは真逆の構造です。
● 耐久性と利便性:長持ちはするが、見た目は劣化しやすい
【耐久性】
- 摩擦にはそこそこ強く、洗濯・乾燥には耐える
- ただし、毛玉・静電気・ほこり吸着が起きやすく、見た目の劣化が速い
【現代における利便性】
- 洗濯機OK・乾燥機もOK・アイロン不要と、管理は非常にラク
- 軽くて扱いやすく、家庭用衣類や毛布に向く
「気楽に使えて、ダメになったら買い替えられる」――そんな便利さ重視の素材だと言えます。
● まとめ:アクリルの評価ポイント
| 評価軸 | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | ◎ | 非常に安価で、ニットやフリース製品に広く使われている |
| 環境負荷 | × | CO₂排出・マイクロプラ・非分解と、持続可能性の点では大きな課題がある |
| 着心地 | △ | 軽くてふわふわだが、蒸れやすく毛玉が出やすい。快適さは短命 |
| 耐久性 | ○ | 洗濯には強いが、見た目の劣化が早い。ヘビーユースには不向き |
| 現代における利便性 | ◎ | 洗濯・乾燥が簡単で手入れもラク。日常使いの気軽さは抜群 |
ポリウレタン(スパンデックス)
伸びる服=ポリウレタン。でも“寿命”は想像以上に短い
● 驚異の伸縮性で現代衣類を変えた素材
ポリウレタン(米国名:スパンデックス、欧州名:エラスタン)は、驚異的な伸縮性を持つ化学繊維です。
ヨガウェア、下着、靴下、ジーンズ、マスクの耳ひもなど、身体にフィットさせるあらゆる製品に使われている不可欠な素材となっています。
- 元の長さの5〜7倍に伸びて、元に戻る
- 衣類の形崩れを防ぐ補強材としても活躍
- 単独では使われず、綿・ポリエステルなどとの混紡が主流
「動きやすくて楽な服」が当たり前になった現代のファッションは、ポリウレタンの登場によって実現したと言っても過言ではありません。
● 着心地:ノーストレス。でも“劣化”が突然やってくる
ポリウレタン混の衣類は、身体に自然になじみ、動きを妨げない快適さがあります。
- とくにフィット感・伸縮性・柔軟性は他の繊維にはないレベル
- パツンと張るのではなく、**自然に追従してくれる感じが“着てないような着心地”**を実現
- ただし、経年劣化が早く、気づいたらボロボロになるという現象が起きやすい
ポリウレタンは加水分解に弱く、空気中の水分でも徐々に分解が進むため、着ていなくても数年でゴムが切れたり、生地がベタつくことがあります。
● 環境面では“問題児”に近い素材
【生分解しない】
ポリウレタンは自然界でほとんど分解されず、焼却処理が前提となります。埋めれば何十年も残ります。
【マイクロプラスチック】
洗濯時の繊維破断により、極細で弾力のあるマイクロファイバーが流出し、生物に絡まりやすい危険性も指摘されています。
【リサイクル困難】
衣類の多くはポリウレタンを他素材と混ぜて使用しているため、分離してリサイクルすることが非常に難しいです。
また、繊維が劣化して機能を失うタイミングが早い=買い替え頻度が高くなるという点でも、環境への間接的な負荷が高い素材です。
● 耐久性と利便性:機能性は高いが、“短命”
【耐久性】
- 摩耗には強いが、熱・紫外線・湿気に非常に弱い
- 2〜3年で劣化することが多く、長期保管や中古利用には向かない
- ストレッチ性が失われると、服としての機能そのものが損なわれる
【現代における利便性】
- 着用中は快適そのもの。洗濯・乾燥も問題なし(高温は避けるべき)
- とにかく動きやすく、スポーツや育児などの動作の多いシーンでは不可欠
日常生活での快適さを最大化する素材だが、サステナビリティとは対極にある寿命の短さが難点です。
● まとめ:ポリウレタンの評価ポイント
| 評価軸 | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | ○ | 混紡用途が中心で価格は安定。衣類の幅広いカテゴリに使用可能 |
| 環境負荷 | × | 非分解・マイクロプラ・短寿命による頻繁な廃棄が大きな課題 |
| 着心地 | ◎ | 抜群のストレッチ性で着用感は極めて良好。体になじむ素材 |
| 耐久性 | △ | 劣化が早く、経年で急激にパフォーマンスが落ちる |
| 現代における利便性 | ◎ | 動きやすく、管理も簡単。だが“すぐ使えなくなる前提”での活用が必要 |
ナイロン
戦争から生まれた“万能繊維”。今なおアウトドアの主役だが――
● パラシュートからユニクロまで。汎用性の高すぎる素材
ナイロンは、1930年代に軍事利用を目的に開発された世界初の合成繊維です。
当初はパラシュートやタイヤコードとして使用され、その後はストッキングやスポーツウェア、アウトドアギア、バッグ、傘などに広がりました。
- 高い強度と引き裂き耐性を持ち、摩耗にも強い
- 撥水性・速乾性に優れ、非常に軽量
- 製造コストが比較的低く、加工しやすい
「とにかく丈夫で軽くて水を弾く」この特徴により、ナイロンは機能性素材の代表格となっています。
● 着心地:滑らかで軽いが、通気性に欠ける
ナイロンはシルクのような滑らかさを持つため、ストッキングやインナーに使われることもあります。
- 薄くても強度があるため、軽くてしなやかな着心地
- ただし通気性・吸湿性に乏しく、蒸れやすい
- 静電気が発生しやすく、冬場の着用ではパチパチ感が気になることも
- 炎には弱く、火気の近くではすぐに溶けてしまう
つまり、滑らかで快適に感じる反面、長時間着ると不快になることもあるというのがリアルな使用感です。
● 環境面での評価:悪くはないが、決して良くもない
【製造エネルギーは多め】
ナイロンは石油由来のポリアミド繊維で、生成過程で亜酸化窒素(N₂O)という温室効果ガスが多く発生することで知られています。
このガスはCO₂の約300倍の温室効果があり、環境負荷としては見逃せません。
【リサイクル可能な技術が進みつつある】
ナイロンは比較的再生処理がしやすい合成繊維で、廃漁網や古いカーペットから再生された「リサイクルナイロン」製品も増えています。
とくに「ECONYL(エコニール)」といったブランドが注目されており、循環型素材としての未来性はあると言えます。
【生分解性はなく、マイクロプラ問題は依然残る】
とはいえ自然分解しないため、長期間環境中に残留する問題は回避できません。
● 耐久性と利便性:とにかく“丈夫でラク”
【耐久性】
- 摩耗、引き裂き、伸縮などに非常に強く、長期使用向き
- 直射日光・雨風にも耐えるため、アウトドア・スポーツとの相性は抜群
【現代における利便性】
- 撥水性と速乾性があり、雨具や洗濯頻度の高い衣類に最適
- シワにもなりにくく、アイロン不要
- 家庭用洗濯・乾燥機でもへこたれない万能さがある
現代のライフスタイルにおいて、「とりあえずナイロンにしておけば安心」と言えるほど利便性は高い素材です。
● まとめ:ナイロンの評価ポイント
| 評価軸 | 評価 | 解説 |
|---|---|---|
| 仕入れコスト | ○ | 汎用性が高く、製品によっては非常に安価に仕入れ可能 |
| 環境負荷 | △ | N₂O排出・非分解性が課題。リサイクル技術の進展に希望あり |
| 着心地 | △ | 軽くて滑らかだが、蒸れや静電気が気になりやすい |
| 耐久性 | ◎ | 合成繊維でもトップレベルの強さ。雨・風・摩耗に非常に強い |
| 現代における利便性 | ◎ | 速乾・撥水・ノーアイロンで扱いやすい。スポーツや外出着に最適 |
まとめ:おすすめ素材ベスト3とその理由
これまで14種類の素材を、仕入れコスト・環境負荷・着心地・耐久性・現代における利便性という5つの視点から分析してきました。それぞれ一長一短があり、「絶対的な正解」は存在しないことが見えてきたかと思います。
とはいえ、「これからサステナブルな服作りを考えるうえで、特にバランスの取れた素材を選ぶとしたら?」という問いに答えるべく、以下の3つをベスト素材として挙げます。
第1位:リヨセル(テンセル)
再生繊維の理想形。バランス最強の万能素材
- 環境負荷が非常に低く、CO₂排出や水の使用量も最小限
- 肌ざわりもシルクに近く、着心地は非常に高い
- 原料がユーカリで、農薬や肥料をほとんど必要としない
- 生分解性もあり、製造プロセスも閉鎖系で安全
→ 最大の弱点は「価格」と「国内での製造の困難さ」。ただし輸入が可能であれば、もっとも“持続可能”に近い選択肢です。
第2位:リネン(亜麻)
最古のサステナ素材。現代との相性は調整次第
- 農薬や水をほとんど使わずに栽培可能
- 丈夫で長持ち、通気性も良く、夏に最適
- 着心地はやや硬めだが、慣れると快適
- シワや縮み・ホコリ(カス)など、現代のライフスタイルと“完全に一致”はしない
→ ラフさや自然な風合いを活かしたデザインなら最適。乾燥機を避け、シワを個性として活かせる服づくりに向いています。
第3位:再生ポリエステル(rPETなど)
現実的な落としどころとしての“循環素材”
- 使用済みペットボトルなどを原料にできる
- 着心地や機能性はポリエステルと同等
- 耐久性・速乾性・防シワ性に優れ、利便性が非常に高い
- ただし、「完全な循環」には至っておらず、環境負荷はやや残る
→ スポーツウェアやユニフォーム、機能性重視のアイテムにはベストチョイス。また、化学繊維が避けられないジャンルでは「よりマシな選択肢」として重宝されます。
最後に:サステナブルとは、“環境だけ”じゃない
本記事では、さまざまな繊維の「裏事情」にも踏み込みました。サステナブルな服づくりとは、単に自然素材を使うことでも、リサイクルマークがついていることでもありません。
- その素材は、どんな土地で、どんな人の手で作られているのか
- 長く着られる設計になっているのか
- 売れ残った後の未来も想像されているのか
そんな問いを、「服を選ぶ側」も「作る側」も共有することこそが、本当のサステナブルにつながると私たちは考えています。